以前、山村暮鳥の「聖三稜玻璃」なんかが好きで、
傷害雲雀
殺人ちゆりつぷ
墮胎陰影
騷擾ゆき
放火まるめろ
誘拐かすてえら。
といったフレーズがいまでも口を突いてでてくることがあるが、山村がこのあと、人道主義者から急激な涅槃の境地に逝ってしまったことはよく知られていよう。どうも、山村がこの詩集を出した時に酷評され、卒倒までしていることが気になる。いじめられすぎると人道主義者に転向したりするのはよくあることではないか。その人道主義は、自我の破壊からもたらされるのである。
どうでもいいが、良く考えてみると、上の詩なんか、神武綏靖安寧懿徳孝昭孝安孝霊孝元開化崇神垂仁景行成武仲哀神功皇后応神仁徳履中反正允恭安康清寧……といったものを暗唱する何かと一部種通じるところがあり(違うか)、要するに何かを強いられた末の快感物質が出ているのを感じる。天皇の名前は、大石先生世代にあたる祖母から昭和五十年代に習った。わたくしも、だいたい清寧天皇までは暗記しているのだが――しかし、昔は、昭和天皇まで覚えないとぶん殴られたりしたそうなのであった。暗記力がよくて健康なやつが褒められる点では、戦後も戦前もあまり変わらない。戦時体制もその主たる活動はいじめである。
もっとも、戦犯が曲がりなりにも吊されたり、公職追放になったり、元特高がリンチに遭ったりしたあとでは、その断罪の音みたいものをみんな覚えていた。
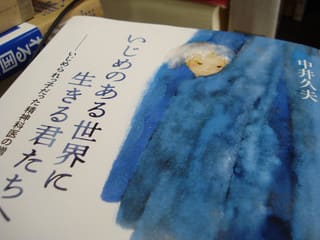
この本から響いてくるのは、断罪の音が遠ざかった世界で、権力に反抗できないように従属させられてゆく我々の社会のいじめのしくみの臨場感である。中井氏は、戦前のいじめの経験をよく覚えているようだが、戦後のある時期から臨床医として子どもとつきあううちに、更にきちんと戦中期のことを思い出すに至った。最近、忖度とか言われているものも、中井氏の説明するいじめのプロセスを辿っている。この本を読んで、何十年かの人格形成の出発点(というか目的それ自体)に、いじめへの対処があったことを思い出した人も多いだろう。なんと情けない人生か。我々の社会ではほとんどの人がいじめのおかげで自分の人生を送れないままなのである。いじめ対策は、戦争責任論と同じで、主犯をきちんと罰することが出来るかにかかっているとわたくしは思うのであるが、それを不可能にすることまでこの社会は計算していじめをやっている。
傷害雲雀
殺人ちゆりつぷ
墮胎陰影
騷擾ゆき
放火まるめろ
誘拐かすてえら。
といったフレーズがいまでも口を突いてでてくることがあるが、山村がこのあと、人道主義者から急激な涅槃の境地に逝ってしまったことはよく知られていよう。どうも、山村がこの詩集を出した時に酷評され、卒倒までしていることが気になる。いじめられすぎると人道主義者に転向したりするのはよくあることではないか。その人道主義は、自我の破壊からもたらされるのである。
どうでもいいが、良く考えてみると、上の詩なんか、神武綏靖安寧懿徳孝昭孝安孝霊孝元開化崇神垂仁景行成武仲哀神功皇后応神仁徳履中反正允恭安康清寧……といったものを暗唱する何かと一部種通じるところがあり(違うか)、要するに何かを強いられた末の快感物質が出ているのを感じる。天皇の名前は、大石先生世代にあたる祖母から昭和五十年代に習った。わたくしも、だいたい清寧天皇までは暗記しているのだが――しかし、昔は、昭和天皇まで覚えないとぶん殴られたりしたそうなのであった。暗記力がよくて健康なやつが褒められる点では、戦後も戦前もあまり変わらない。戦時体制もその主たる活動はいじめである。
もっとも、戦犯が曲がりなりにも吊されたり、公職追放になったり、元特高がリンチに遭ったりしたあとでは、その断罪の音みたいものをみんな覚えていた。
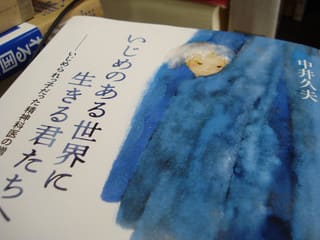
この本から響いてくるのは、断罪の音が遠ざかった世界で、権力に反抗できないように従属させられてゆく我々の社会のいじめのしくみの臨場感である。中井氏は、戦前のいじめの経験をよく覚えているようだが、戦後のある時期から臨床医として子どもとつきあううちに、更にきちんと戦中期のことを思い出すに至った。最近、忖度とか言われているものも、中井氏の説明するいじめのプロセスを辿っている。この本を読んで、何十年かの人格形成の出発点(というか目的それ自体)に、いじめへの対処があったことを思い出した人も多いだろう。なんと情けない人生か。我々の社会ではほとんどの人がいじめのおかげで自分の人生を送れないままなのである。いじめ対策は、戦争責任論と同じで、主犯をきちんと罰することが出来るかにかかっているとわたくしは思うのであるが、それを不可能にすることまでこの社会は計算していじめをやっている。









