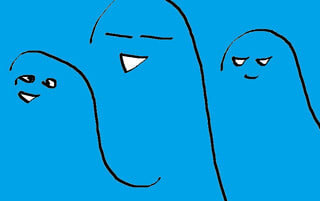
かく人に恥ぢらるゝ女、如何ばかりいみじきものぞと思ふに、女の性は皆ひがめり。人我の相深く、貪欲甚だしく、物の理を知らず。たゞ、迷ひの方に心も速く移り、詞も巧みに、苦しからぬ事をも問ふ時は言はず。用意あるかと見れば、また、あさましき事まで問はず語りに言ひ出だす。深くたばかり飾れる事は、男の智恵にもまさりたるかと思へば、その事、跡より顕はるゝを知らず。すなほならずして拙きものは、女なり。その心に随ひてよく思はれん事は、心憂かるべし。されば、何かは女の恥づかしからん。もし賢女あらば、それもものうとく、すさまじかりなん。たゞ、迷ひを主としてかれに随ふ時、やさしくも、面白くも覚ゆべき事なり。
有名な徒然草の「女性蔑視」の場面であるが、これは、百七段の全体のなかで解されるべき気分を表しているのではなかろうか。こういうひどく思われる女がいないと服装が乱れてどうしようもないのが男なのだ。彼が見ている人間の悲喜劇は、この部分を百七段の冒頭に置いて、男が女に評価されてあわてている云々をあとに持ってくるのがいいのかもしれん。。。「たゞ、迷ひを主としてかれに随ふ時、やさしくも、面白くも覚ゆべき事なり。」は、冒頭の「女の物言ひかけたる返事、とりあへず、よきほどにする男はありがたきものぞ」とて、――にループすると見た方がよい気がするのだ。
要するに、これは小林秀雄の「Xへの手紙」風に言えば、女は男の成長する場所だった、というわけだ。残念ながら?兼好法師は、女が自分の期待した者と違うことにパニックになっている発達段階にあるだけなのである。
しかしその円頂閣の窓の前には、影のごとく痩せた母蜘蛛が、寂しそうに独り蹲っていた。のみならずそれはいつまで経っても、脚一つ動かす気色さえなかった。まっ白な広間の寂寞と凋んだ薔薇の莟の匀と、――無数の仔蜘蛛を生んだ雌蜘蛛はそう云う産所と墓とを兼ねた、紗のような幕の天井の下に、天職を果した母親の限りない歓喜を感じながら、いつか死についていたのであった。――あの蜂を噛み殺した、ほとんど「悪」それ自身のような、真夏の自然に生きている女は。
――芥川龍之介「女」
芥川龍之介は、虚構の中とは言っても女に対してひどいことをしすぎている。小林のいうようにそれが「場所」であるのだとしたら、彼が自分にもひどいことをしたのは必然である。兼好法師の女性蔑視の方が遙かにましなのである。









