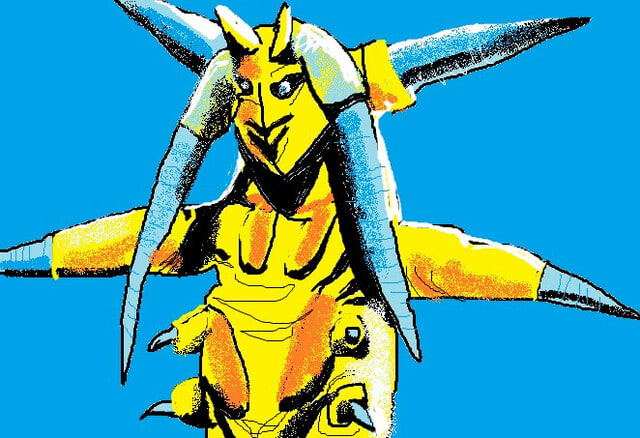
北の方かう遊ばすこと、昔、大将のおとどに対面し給ふ山に住み給ひし時弾き給ひけるままに、その後、さらに、住み給ひける世に手触れ給はず。この大将のおとどにも、さらに、この琴弾きて見せ奉り給はず。宰相の中将は、時々、紀伊国などにても仕うまつられけれど、この北の方は、さらに、里に出で給ひて後、琴に手触れ給はずあるにかくわりなく聞こえ給へば、仕まつり給ふ。なほ、年ごろ騒しくなどして、まれにこそ思ひ出で給へ、忘れものし給ふを、この琴に手触れ給ふにつけて、よろづ昔のこと思ほえ給ひて、あはれなること限りなし。
俊蔭の娘(仲忠の母)が朱雀帝の命で長年弾いていなかった琴を弾き、息子に琴を習わせたこととか南風の琴を弾いたこととかを思い出しながら素晴らしい演奏をしてゆく場面であるが、ここでは我々が過去にあったことを物に即して、反応して思い出さなければならず、そしてその思いが行為に伝染しなくてはならないみたいな、法則、――いやこれは一種の道徳が働いているように思う。隠れていたものが、影が光としてみえるような反転の世界である。
日本の古典読んでると、どうしても四書五経ぐらいはちゃんと読まなくてはおさまりがつかなくなるのは、古典の世界にどこかしら道徳の薫りが残っているからでもあろうか。――国語の先生が確信をもって古典漢文の意義をとけるのはその段階にすくなくとも達していることが必要だと思う。理屈の前に必要性を自分が感じてるかが問題なのである。難しいことだけど、教師になる前にそこまでにいこうとすれば、やはりかなり早くやった方がよいわな。どうも、四書五経を暗誦させるような教育は、封建社会の勘違いに過ぎなかったとはとても思えないのである。それは大げさではなく、源氏物語の源氏が息子に言うように、大和魂(日本文化)に到達するために必要だったのではなかろうか。
特に近代文学などやった教師は、国語が道徳に回収されてしまうのを嫌う傾向にあるし、それは一応正しいけれども、それは日本の近代にでっち上げられた道徳規範がかなり痩せててくだらないからそういうことが起こる側面がある。文学は、寓話は言うまでもなく倫理的な要素を捨てられない場合が多いし、広い意味で倫理に向かっているものは多いから、国語の勉強を大きく道徳的に捉えるのはまったく無意味というわけではないと思う。そのかわり教科書の内容をもっとゆるく雑多にする必要はある。しかし、いま定番として残っているものであったも道徳として機能している。「ごんぎつね」もあれは日本人の道徳感情を醸成させているところがあるわけである。「舞姫」だって逆説的にそうだ。我々は兵十や、豊太郎の像を自分の影として自分の像をつくる。我々の自画像とはまだそんなところが残っている。べつにそういう機能を全部否定することはない。しかし、国語をコミュ力・言語能力みたいなものとしてとらえるとよけい、倫理を担っていた部分が道徳でやらざるをえなくなりその道徳はまた修身的な馬鹿馬鹿しいものになってしまう。そもそも、いまだ倫理的感覚が我々自身と社会のなかでどういう風に機能するのがよいのか我々は訳わかってないわけで、近代日本のそれはたいがい失敗とみてよろしいのではないだろうか。



















