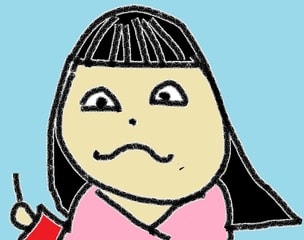昨日、「かぐや姫の物語」というのがやってた。もとの「竹取物語」との違いは明らかで、山の民の登場とか、姫の帝への態度が恐ろしく違うし、月から来た人たちが来迎図みたくなっているから、まあ……そういうことだ。
山の民は山の民であるし、帝は「源氏物語」を想起するまでもなく色好みで勢力拡大を図る人たちの象徴で、おじいさんおばあさんはとりたてて何も言うことなし、五人の求婚者は問題外、月の人たちはなにやらポップな音楽を奏でていたが宇宙人であっても仏関係者であってもいずれにせよ人間じゃねえ、かぐや姫は流刑地送りになったひと――だから、とりあえず、取り立てて特筆すべき者は誰もいないというのが、このお話である。「竹取物語」もそうである。歌物語は、歌によってクソみたいな現実を救う話であり、我々の心はそこにしかないのであった。この話でも「歌」がかぐや姫を人界に追放し、人界の心を理解させるものであった。和歌でひどさを救ってきた我が国の文化を動く絵巻物にしたてたのが、このアニメーションではなかろうか。
そういえば、萩尾望都の「ラーギニー」も似たような意味で歌が重要だったが……、それは我々の弱さとだめさと裏腹である。我々はかぐや姫とおなじで心なんかしょっちゅう簡単になくしているのであって、歌がそれを救っている、……ということになっているのが、我々の国であった。
やまとうたは、人の心を種として、万の言の葉とぞなれりける 世の中にある人、ことわざ繁きものなれば、心に思ふ事を、見るもの聞くものにつけて、言ひ出せるなり 花に鳴く鶯、水に住む蛙の声を聞けば、生きとし生きるもの、いづれか歌をよまざりける 力をも入れずして天地を動かし、目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ、男女のなかをもやはらげ、猛き武士の心をも慰むるは、歌なり
が、しかし、この作品のなかで唯一、ちゃんと生きてそうなのが、
パタリロみたいな顔をしているかぐや姫の付き人である「女童」で、かぐや姫も含めてみんな人でなしであるのに対し、ちゃんと仕事をし姫の心も分かっている。
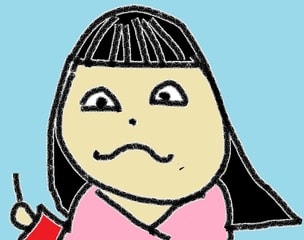
最後、姫を引き留めようとがんばるみんなが、来迎図の人々の超能力でへたっているか泣いているだけなの対し、彼女はガキどもをいつの間にか組織し、かぐや姫を人界に結びつける歌を歌わせて、姫を月に帰さないように抵抗を試みるのである。
しかし武器より歌を、大人より子どもを、といったテーゼを読み取るべきではなかろうて。
わたくしは、ここで思い切って結論を出そうと思う。
我々の最後の砦は、帝でも金持ちでも被差別者でも庶民でも少女でも兵士でも自然でも仏でも音楽でもない。「女童」、つまりお手伝いさん乃至は女公務員であろう。
……そんなはずはない。歌もなにもかも信用ならない。