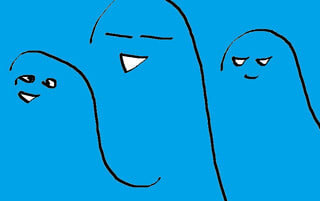双六の上手といひし人に、その行を問ひ侍りしかば、「勝たんと打つべからず。負けじと打つべきなり。いづれの手かとく負けぬべきと案じて、その手を使はずして、一目なりともおそく負くべき手につくべし」といふ。道を知れる教、身を治め、国を保たん道も、又しかなり。
そうかもしれないが、その負けないということが「国を保」つこととどう関係しているのか分からない。野球をみていても、結局強いチームは守りがきちんとしているようにみえるが、そういうことであろうか?確かに、勝つというのは、最後の曲面でうまいことやったみたいなところがあるから、一人のおかげに見えるが、負けないためには、組織の内部の各々の能力がきちんと発揮されていなければならない。サヨナラホームランは、それまでの投手と守備力に支えられていなければならないのである。
おそらく教育を社会資本みたいに考える場合には、それを保守するために、全員が頑張ることになるが、――生き残りをかけるぜみたいな行き方をすると、強力な大砲が何本が必要だみたいになって、弱い兵隊はいらんみたいな感じになる。これがダメなのは日本の敗戦で明らかだ。つまり、わたくしのような頭のおかしい奴の場合、――案外、日本は本土決戦で全員で組織戦をやった方が勝ったのかも知れないと思ってしまうところがある。一発逆転みたいな発想が間違っていることは明らかである。
無論、そんなことはできない。我々はそこまで粒ぞろいの人間ではない。現実に起こるのは、総力戦ではなく、局地的なホームラン合戦、予算=陣取り合戦だ。
現在の自分を振り返ってみても、別に出世双六と騒がれるほどの出世ではない。相変らずの貯蓄会社の外交員で、うだつがあがらぬと言ってしまえばそれまでだが、しかし、もう私にはたいした望みもない。私を誘惑する大阪の灯ももうすっかり消えてしまい、かえって気持が落ちついている。外交をして廻っていると、儲ける機会もないではなく、そしてまた何年かのちに、また新聞に二度目の秋山さんとの会合を書かれることを思えば、少しは……と思わぬこともなかったが、しかし、書かれると思えばかえって自分を慎みたい、不正なことはできないと思った。そして、秋山さんも私と同じような気持で、九州でほそぼそとしかしまじめに働いているのではなかろうか……。
茶店を出ると、蝉の声を聴きながら私はケーブルの乗場へ歩いて行ったが、ちょこちょこと随いてくる父の老妻の皺くちゃの顔を見ながら、ふとこの婆さんに孝行してやろうと思った。そして、気がつくと、私は「今日も空には軽気球……」とぼそぼそ口ずさんでいました。
――織田作之助「アド・バルーン」
結局、双六を降りたときに我々がなにか悟りの境地に達した気分になるのは、日本が勝ち負けの議論をし始めたとたん、あまりに頭が悪いからである。