過去のノートにある映画感想メモシリーズ。part1からのつづき。
この頃は音楽系にハマってたらしい。
長いけど、最初に見たバンドの第一印象って面白いからそのまま載せてみたw
若かりし頃のメモなので、不適切な表現、勘違い等はお詫び申し上げます/謝罪
なお、あらすじはなるべく省略しています。
■
『Rock'n'roll '69 the greatest years』(1989)
いやあ、訳も分からず観ちゃったけど、コンセプトがよく分からん。
ヒット曲のプロモーションビデオやら、当時の映像をかき集めた割に唐突でメチャクチャな構成。
でも'69当時のロックシーンの雰囲気をちょっと齧るには興味深いし、資料としての価値は高い。
ヒットチャートで何位だったとかゆうテロップは必要ない気もするけど、
それぞれのカットの切り替えが早いから、下の英語を読んでいるうちに演奏が終わっちゃってたりする。
やっぱりジャニスはすごいのと、D.ボウイがキョーレツだったっていうのが'69年かな。
テンション高いアンドリュースの掛け声やギターソロもイイ。ジャニスのアクションもサイコー

同じ年にヒット曲を持ってたジャスとボウイ。ほど遠い2人が出会うチャンスなんて一体あったのかしら???
【収録アーティストメモ】
Fleetwood Mac
思い切り演奏してないのがバレてるドラムス

Amen Corner
Andy Fairweatherは本当にカリスマ。ニタついた危ないヴォーカルって意味で。
Desmond Dekker
もっと笑っちゃう!黒人の怪しいロボットかなにかみたい。完全に宗教。
Clodagh Rodgers
イギリスのアイドル歌手。日本のアイドル歌手と似てる。(そいや、モンティ・パイソンのネタにも出てきたよね?w
Martha & the Vandellas
モータウン出身の女の子3人組。やっとまともになってきた(失礼だ
Beach Boys
カルフォルニア・ポップ。いまだに現役でしょ?ハーモニーがキレイ

Stevie Wonder
スゴイ

ハモニカやピアノだけじゃなく、ドラムも叩ける。盲目とは信じがたいリズム感覚。
バックのオーケストラと生演奏なのがイイ。
Janis Joplin
彼女が突然ロックシーンに飛び込んできた'69の映像だもんね。文句なしにすごいこのノリ、
どのビデオを見ても彼女のクリエイティヴでエキサイティングな才能には誰もかなわない!貴重な資料

The Who
元気だねえ、コードマイクをそんなに振り回したら危険だよ。突然ここで照明効果。
Leon Russell
速いピアノと歌がイイ。
Bill Medley & Bobby Hatfield
これは2人の名前か?
The Righteous Brothers
クラシカル。相手方の小鳥みたいなバッキンコーラスがイイ。
The Rolling Stones
若い!当時長髪のミックのマッチ棒みたいな体。跳んだりはねたりのノリは今と同じ。
David Bowie
これ絶対本人は見たくない、見せたくない映像だろうね。若すぎる。初めて見たし、ショッキング。
TOMってデカデカ書かれた宇宙服で♪スペイス・オディティの世界をそのままドラマ仕立てで演じてる。
でもスーパースターになるべく一生懸命だった第一歩だったわけよね。
それにしてもわざとらしい演出。この頃から充分にunusual。面白いアレンジで変にキレイな声で歌ってる。
■
『Rock'n'roll '70 the greatest years』(1989)
どうやらブリティッシュロック中心にU.K.チャートばかりのヒットを集めてある。
ヘヴィなサウンドがウケてた一方で名曲を数多く出したカーペンターズってデュオもいた時代。
【収録アーティストメモ】
Jimi Hendlix
いきなりジミ・ヘンから。この頃はまだギターソロもおとなしい。
スキニーボディに、コントで爆発した後みたいなヘアスタイル。
今のギタリストで影響受けてる人は多いけど、彼は誰かの影響を受けたのかしら?
Mungo Jerry
すごいもみあげ!狼男だよ。ピアノをベースにした童謡みたい。
Black Sabbath
これは前に観た。ヘビメタのはしりだそうな。
The Beach Boys
また彼ら。当時相当活躍してたんだね。イージーリスニング。
Deep Purple
噂に聞くこのバンド。ヘビメタのルーツ。現代に比べるとまだソフトだと思うけどイイ。
Blue Mink
黒人女性と白人男性のヴォーカルの組み合わせは珍しい。
歯切れのいい2人のハーモニーもイイ。
Canned Hearts
グルーヴィなロック。ちょっとヴォーカルが太めのサンタ風

Christie's Chart
♪Yellow River は知ってるけど、バンドは初めて見た。曲に合わせて船で川下りしながらって演出はニクイ。
Shocking Blue
バナナラマによってカバーされ再ヒットした曲♪ヴィーナス 日本でも知られている。
元は黒人系の思い切り'70年代ファッションの彼女が歌ってたわけだ。
ドラムスが女の子なのも当時は珍しかったんじゃないかな?
The Kinks
♪LOLA このバンドも伝説的。ライブの映像でノリがいい。完璧ロックなのにヴォーカルはスーツ着てる。
The Faces
ロッドが若い!ひよこ

ヘアはそのまま、しゃがれ声も、タイトなファッションも。
Ciarence Carter
盲目の黒人シンガー。小説風の歌。
The Carpenters
カレンの透き通った声はいつ聴いても感動的

大きな眼にブラウンの長い髪。
女性がドラムとヴォーカルってゆうのも斬新だし、今回初めて兄のリチャードがピアノとバックコーラスをしているシーンを観た。
この名曲に、このバンド。何十年経とうと不滅だね。カレン亡き後、兄は今どうしているのかしら?
Edison Lighthorse
アイドルグループっぽい。テレビとスタジオでしかプレイしなかったんだって。
James Brown
なんか若い頃から太鼓腹。ゴスペル、ソウル、今や神様。パープルのスカート風衣装で
白人の女の子とダンスも踊っちゃうパフォーマンス。
■
『Rock'n'roll '71 the greatest years』(1989)
やっぱりノリにノッてた頃の
T.REXかな。ロッドの声と曲も甘くてイイし、
生まれたてのヒヨコみたいなルックスも可愛かった

スターダムを一足先に降りて天に昇ってしまった人もいれば、20年経った今でも
ちゃんとロック界を背負って、新しい創造にチャレンジしてる人もいるってのはスゴイこと。
今の子どもたちにとっては、CDショップで手にとった時点で新しい出会い

、
新曲であり、新しいショックと驚き、感動でもあるんだよね。
【収録アーティストメモ】
The Kinks
いかにもかぶりもののApemanとバンドメンバのからみのビデオクリップ。
T.REX
イエス!これは見た。シルクのオレンジ色のスーツにシルバーのパンツ。
中がミッキーのTシャツなのがなんともキュート。こうしてロック史の流れから見ても
マーク・ボランのスタイルは画期的だ。動きのあるカメラワークも。
♪ジープスター がどんな歌かと聞かれて、ボランいわく「It's a car, of course

」て
自分じゃ絶対運転しなかった車狂なんてフシギじゃない?
スティーブも一生懸命ボンゴ叩いてる。どこかのライブ版。
Elvis Presley
エルヴィスがわざとらしく動くたびに聞こえる黄色い声が面白い。
The Who
'69のヤンキー少年から突然ツェッペリンみたいな雰囲気に転身。
ギタリストは相変わらず元気。ドラッギーなステージ。
Dawn
♪Knock Three Times 聴いたことある。胸毛の濃い、それを強調する大きなV字シャツ!
一緒に踊ってる2人のコーラスガールがいかにも'70スタイル。
Middle of the Road
スコットランドのグループ。ロリータっぽいボーカルのコ。民謡に近い。
Rod Stewart
まだ眠そうな寝起きみたいなロッドが若くて可愛い。ハスキーヴォイスで曲もスイート。
Slade
ヴォーカルの顔がルー大柴並にコワイ。金属音みたいな声。ハードロック。
ハイテンションでカメラレンズまで曇らせちゃったライヴヴァージョン。
Equals
2ギター、ベース、ドラムスのシンプルな構成。
The Carpenters
'83に亡くなったカレンがドラムから離れてマイクで歌っている姿が見れる。
上品なパープルのドレスと黒髪が美しい。兄リチャードも蝶ネクタイだもんね。クラシック作曲家みたい。
Gilbert O'Sullivan
ピアノを弾きながらのフォークロック。
Theme From Shaft
インスト。黒人指揮者に合わせてのレコーディングセッション風で観客もいる
スローな映像と軽快なリズムの組み合わせはフシギな効果。
後半に入るちょっとした歌とコーラスもなかなかイイ。
Ringo Starr
ソロ活動。ビートルズ時代のノリをそのままひきずったジョークなヴィデオクリップ。
ペンギンバンド

との演奏とか。
The Rolling Stones
エジプト人風アイメイクをしたミック。音もデビュー当時のシンプル+混乱したものに比べてペットも入っててイイ。
このパワーとアクションは今でも同じだもんね。
■
『Rock'n'roll '72 the greatest years』(1989)
とゆうわけで、これが少なくとも近所のレンタルショップに置いてあるシリーズのラスト。
'63には♪風に吹かれてを歌うディラン、♪ビー・マイ・ベイビーのロネッツなどが入ってるって
ラストの宣伝にあって、面白そうじゃないか!とにかくあるだけではこれで最後。
他にも見たいバンドはいっぱいあるけど、トップチャーターだけを扱っているからこんなもんでしょ。
相変わらず好調に走ってたロッドやボランから、洗練されたサウンドを聴かせるテンプス、
ドリフターズ、アリス・クーパー他のキョーレツな奴もたくさん見れたし、
'60、'70のロックは今でも不滅だ。こんな企画ももっと増えてほしい。
【収録アーティストメモ】
Roxy Music
ブライアン・フェリーがギター&ヴォーカルのバンド。
一本調子のヴォーカルにチンピラっぽい前髪。
Vincent Furnier
アリス・クーパー率いるバンド。猿

に電話させたり、煙草を吸わせたり、
金・金・金の扇動的な政治屋かロックスターかを風刺したヴィデオクリップはなかなか面白い。
Don Mclean
ギターの弾き語りのフォーク。ディラン風でルックスもソックリ。
ゴッホにインスパイアされたという♪ヴィンセント はボウイの曲に似てる。
Dr.Hook & the Medicine Show
♪Sylvia's Mother は世界的ヒットらしいけど知らない。土臭いスタイルのバンド。
あやしい片目の男がコーラスでキレイ。
The Faces
ファンキーなライヴアクト。シンプルなメロディで大勢の観客もノリまくってる。
Focus
♪Thijs van Leer ヨーデルを歌うキーボードがサイコー!オランダのバンド。
冗談じゃなく真剣に高音で歌っているのがイイ。ロックオペラってとこかな。
ロックとのミスマッチさがイケる。フルートまで吹いちゃって本当にぶっ飛んでる

Cat Steven's
ピアノの太ったアフロヘアの男はキョーレツ。ラヴ&ピースな歌。
The Drifters
彼らがドリフターズかあ!脚の長い4人黒人グループ。
タイトなスーツを着て、クラシックでスウィングなサウンド。
ヴォーカリストがユーモラス。低音からものすごい高音まで歌うクリクリした眼がキュート。
2人のコーラスに1人ギター。洗練されている。
Rod Stewart
一転してカラフルな青いシャツ。ソロになったロッド。アイドルっぽさから抜け出して渋さが加わってる。
メロディ・メイカーとしても才能あるよね。
The Osmonds
なんとも中性的で個性的なルックスのシンガー。ベビーフェイスだけどしっかりした音楽。
家族編成のバンド。タイトルもなんともいえない響き。
Peter Skellern
♪You're a lady 静かなバラッド。ロマンティックなラヴソング。
ピアノを弾くシンガー・ソング・ライター。弾き語りそのもの。
どうやら女性教師に恋した生徒の歌?ありがちだけど大層なコーラスがついてる。
T.REX
トップ10に5曲、そのうち3曲がトップ3だってゆう驚異的人気だったピーク
 The Temptations
The Temptations
ピンクのステージ衣装で、声といい雰囲気ですぐ分かった。
ステージ下で踊るブラックキッズたちの大きなアフロヘア!
それぞれのフィーリングで好きに楽しんでいるのがイイ。洗練されたコーラス。
Alice Cooper
♪School's Out ラクダが出たり、サーカスの世界そのもの。ハードロック。
クーパーのカリスマ性は眼を見張る圧倒的ステージ。
ケンカのパフォーマンス、メイクしたファンらを巻き込んだ暴力映画みたい。
Michael Jackson
ジャクソン・ファイブの一番若いメンバだったマイケルがまだ若い!
♪BEN は静かなラヴソング。デカい花柄パンツ。
Procol Harum
チャートのマジックで突然復活したってゆう♪A whiter shade of pale は今でもテレビCMで使われたりする。
政治的な映像も使われて、キーボードのメロディがノスタルジック。
バンドメンバは平凡だけど、サウンドには注目。
■
『WOODSTOCK 3DAYS OF PEACE & MUSIC』(1970)


監督:MICHAEL WADLEIGH
結局ラストはジミヘンのアメリカ国歌で締めたわけだけど、他にももっと出演者はいたはず。
初日に来たジャニスもプレイしたはずだし、本に書いてあった通り彼女のアクトが
映画、資料としての映像で残っていないのはなんとも残念。
やはり一番の圧巻は
ジョー・コッカーだな。とにかく天にも届くあのバラッド、あの叫び、あのリズム


主催者が集まった連中と同じ若い青年なのにまず驚かされる。ステージ建設の始まりから、
次第に集まる群衆、それが一大イベントとなり、誰も止められない前代未聞のニュースとなった。
雨が降っても人々の興奮はおさまらない。みんな口々に
"We're helping each other, and loving each other" この映画ではこれが強調されてる。
観客の視点からとらえているのがイイ。プレイヤーにはまた別の物語りがあっただろうし、そちらも興味深いけど。
何十万人のそれもアメリカの三大都市の一画、大した設備もない場所で、ほとんど暴動らしきものもなく、
平和的にことが運んだってだけで、もうこれは驚きに値する。
いろんな伝言、求婚、出産、親に電話しろだのメッセージが飛び交って、周囲の住民の反応も様々。
同じ歳の子どもを持つ人々は歓迎していたんだね。実際はもっと混乱してたはず。
個人的には、加わるにはハードすぎると思うけど。ドラッグ、酒、フリーラヴがまかり通る
フリーでピースフル、ファンタスティックなミュージック・フェスティヴァルだったとうこと。
モンタレー・ポップ・フェスティヴァルもウッドストックと同じくらい大規模なフェスだったらしいけど、
そちらも全体的な映像を映画化した映像はないのかしら?
ヴェトナム反戦、自由を訴えるという若者たちの、古い体制、考え方への反発運動でもあったこのフェス。
でも、参加者にはそれぞれの思いが十人十色あただろうし、それで何を得たのかな?
20年経った今、個人個人どう変わったのか知りたい気もする。
もう2度とこんな規模の奇跡は起きないだろうし。
(各ミュージシャンのパフォーマンスの感想も書いてあったけど長いから省略

■
『MTV CLOSET CLASSICS 栄光の60年代』(1987)
いかにもMTVらしいコンセプトで撮られた1本。いまだにヴィデオクリップじゃ口パクが主流だけど、
この頃はもろに手と音が合ってない。とくにドラムは難しいのは分かるけど・・・

他の年代のもビッグアーティストのがあるだろうし、もっと提供してほしい。
【収録アーティストメモ】
'67 CREAM/I FEEL FREE
こりゃビックリ。ボウイがアルバムで歌ってたやつだ。これが元ネタだったのね。
ボーカルがトム・ベレンジャーみたい。
エリック・クラプトンがギターだって、またビックリ。
'68 THE MOODY BLUES/NIGHTS IN WHITE SATIN
ハリウッドスターぽいシンガー。静かなラヴソング。"yes I love you"を延々と繰り返してる。
'68 THE WHO/MAGIC BUS
もちろんマイク回して、ギター回し弾き、エルヴィス風のヒラヒラ衣装のロジャー。
ドラムス危ない立ち打ち。
'68 THE BEACH BOYS/SURFIN USA
これは今でも聴く典型的サーフィン向き。バンド名からして徹底してるものね。
みんな遊んでて演奏してないのがバレまくり。
'69 STEPPENWOLF/BORN TO BE WILD
この曲も有名。でもバンドは初めて見た。曲通り、グラサンのワイルドなスタイルのシンガー。
'72 BLACK SABBATH/PARANOID
これも先日聴いたけどカラフルな映像がグラムスターっぽい。
アートをバックに長髪男たちのバンド。あんましカラフルで目がチカチカする。
ヴォーカルがオジー・オズボーンなんだ。
'71 T.REX/YOU'RE MY LOVE(JEEPSTER)
イエス!タイトルなんで違うんだろ?ボランは珍しく?実際に歌ってる

ブルーのシャツに黒いパンツ、ギラギラのグラムスターになる前?
なんか表情硬い。生のシャウトが聴けるなんてラッキー
 '70 FREE/ALL RIGHT NOW
'70 FREE/ALL RIGHT NOW
これも一部だけ見た。いいメロディ。エレキのサウンドとボーカルの恍惚とした歌い方、
グルーヴィな曲だもんね。ギターのソロといいライヴなステージ。
'66 JIMI HENDRIX EXPERIENCE/WILD THING
彼の映像が残っているだけで価値があるのに、このアクション


舌を出したり、背中でギター弾いたり、ギターでサンキューと挨拶して、
アンプに突進してプレイ。これじゃ当時の子どもたちがみんなショック受けて
ギタリスト目指しちゃうわけだな。とっても危険でセクシャル、
ヴァイオレント・ムーヴィーでも観ているみたい。誰にも敵わない。
'71 YES/ALL GOOD PEOPLE
ジミ・ヘンのあの毒を見せられちゃ、他のどのロックも甘いラヴソングに思えてくる。
'70 MUNGO JERRY/IN THE SUMMERTIME
これも先日聴いた。陽気なバンドの陽気な曲。今度は空ビンを吹いてないで
口で♪チッチチオ!っていってリズムをとってる。
このピアニスト、音はいいけど、いつまで続くんだ。
'71 THE BYRDS/SO YOU WANT TO BE A ROCK'N ROLL STAR
犯罪者グループみたい。でもヴォーカルはタイしてるんだけど。
'72 THE GREATEFUL DEAD/ONE MORE SUTURDAY NIGHT
彼らがそうか。この間観たおじさん。
ジェリー・ガルシア。顔中ヒゲだらけ。
このロックが後に影響を与えたのかしら?
'71 SANTANA/BLACK MAGIC WOMAN
この曲も知ってる。ウッドストックで歓迎されてたよね。キーボードの人が歌ってるけど、
君のほうが黒魔術師だよ。とくにパーカスのノリがサイコー。
'71 IKE & TINA TURNER(& THE IKETTES)/PROUD MARY
この曲も知ってる。スローにアレンジしてあるけど。わあ!すっごいミニスカートでセクシーダンス。
突如テンポアップして、コーラスガールとシャウト!
とりつかれたような踊りも見どころ。クロール泳ぎの速いダンス!



 が届いたと電話があった
が届いたと電話があった

 のリアルな置き物?を選んだら、
のリアルな置き物?を選んだら、 」て言わなきゃならないんだか・・・
」て言わなきゃならないんだか・・・



 、いろいろあって大変だったような。
、いろいろあって大変だったような。




 が届いたと電話があった
が届いたと電話があった

 のリアルな置き物?を選んだら、
のリアルな置き物?を選んだら、 」て言わなきゃならないんだか・・・
」て言わなきゃならないんだか・・・



 、いろいろあって大変だったような。
、いろいろあって大変だったような。












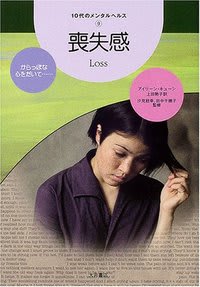
 、友だちに「あなたの服装は変ね」と言われたり(あるある
、友だちに「あなたの服装は変ね」と言われたり(あるある
 一時的であっても気分が悪くなり、相手に対する愛情や尊敬の気持ちを失う。
一時的であっても気分が悪くなり、相手に対する愛情や尊敬の気持ちを失う。 」とも呼ばれ、生活の中の変化を理解するための本。
」とも呼ばれ、生活の中の変化を理解するための本。
 」という思い込みがある。
」という思い込みがある。 、15~24歳までの第2位の死因は殺人、第3位は自殺/驚
、15~24歳までの第2位の死因は殺人、第3位は自殺/驚 、静かになる、考えまいとして忙しくする、何年もたってからやっと心の痛みを出せる人もいる。
、静かになる、考えまいとして忙しくする、何年もたってからやっと心の痛みを出せる人もいる。
 。
。




 喪失を解き放つ
喪失を解き放つ 。新たな人間関係をつくろうとしたり、これまでの人間関係を壊したりetc.
。新たな人間関係をつくろうとしたり、これまでの人間関係を壊したりetc. 、充分な睡眠をとる
、充分な睡眠をとる
 か池を思い浮かべ、水面を見る。
か池を思い浮かべ、水面を見る。
 をつける。気持ちを整理する助けになる。
をつける。気持ちを整理する助けになる。 、読書
、読書

 になっているから、
になっているから、
 」で逃げようとすると、大家さんが追ってくる。
」で逃げようとすると、大家さんが追ってくる。





 に入った者は二度と出られないから気をつけろ
に入った者は二度と出られないから気をつけろ 」と言われて
」と言われて
 トラウマ=心に強いショックを受け、傷として残ること。
トラウマ=心に強いショックを受け、傷として残ること。 、麻薬などの薬物によっても起きる。処方薬にも副作用として表れることもある。例:血圧の薬
、麻薬などの薬物によっても起きる。処方薬にも副作用として表れることもある。例:血圧の薬
 、暴力や犯罪の多い文化、そこで暮らす10代に家族がなにも助言・指導しない場合が多い。
、暴力や犯罪の多い文化、そこで暮らす10代に家族がなにも助言・指導しない場合が多い。 が短くなる秋頃に始まり、日が長くなる春にはよくなる。照射療法が効果的。
が短くなる秋頃に始まり、日が長くなる春にはよくなる。照射療法が効果的。 ADHD(注意欠陥多動性症候群)=集中できない、衝動的に行動する。
ADHD(注意欠陥多動性症候群)=集中できない、衝動的に行動する。

 には、うつ病や他の病気の人の気分を向上させ、孤独感などを癒す効果があると言われる
には、うつ病や他の病気の人の気分を向上させ、孤独感などを癒す効果があると言われる を書く。
を書く。

 、悲しい時は泣く
、悲しい時は泣く



 、レストラン、商店街、イベント。
、レストラン、商店街、イベント。


 ・砂糖類・鼻づまり薬・かぜ薬)は神経を刺激し、不安をつのらせる
・砂糖類・鼻づまり薬・かぜ薬)は神経を刺激し、不安をつのらせる
 、野菜、たんぱく質、玄米・麦などを食べ、水も多めに飲む。添加物・保存剤などの加工品は避ける(缶詰めはいい?
、野菜、たんぱく質、玄米・麦などを食べ、水も多めに飲む。添加物・保存剤などの加工品は避ける(缶詰めはいい?

 でポジティブなメッセージで元気が出るんだけど、
でポジティブなメッセージで元気が出るんだけど、 に常に納得&満足してるのかなあ?
に常に納得&満足してるのかなあ? か煙草のみが多いが、わたしはどちらもやらないんだ。
か煙草のみが多いが、わたしはどちらもやらないんだ。

 )、
)、 を建てても、絶対住みたくないよね/滝汗
を建てても、絶対住みたくないよね/滝汗



 をするシーンなんか涙が出てくる。
をするシーンなんか涙が出てくる。 を転がして小さな町をブラブラ回る若者。町中が知り合いで、ダンスパーティーではポマードをつけた
を転がして小さな町をブラブラ回る若者。町中が知り合いで、ダンスパーティーではポマードをつけた
 ってホレボレしちゃうね。
ってホレボレしちゃうね。

 ヘアはそのまま、しゃがれ声も、タイトなファッションも。
ヘアはそのまま、しゃがれ声も、タイトなファッションも。 、
、 との演奏とか。
との演奏とか。 に電話させたり、煙草を吸わせたり、
に電話させたり、煙草を吸わせたり、







