図書館で借りたCDシリーズ。
【リラクセーション・ミュージック】
▼くじらの詩~マインド・リラクゼーション~
クジラは大好きだから、鳴き声はこれまでも何度か聴いたことがあって、癒し系にはよさげ。
たくさんシリーズがあるのね。図書館にはこれしかなかったような・・・?
▼アジアン・ヒーリング
ルーマーズ・アンビエント・プロジェクト/COMP ほか
これはふつーにアジアン音楽として楽しめる。
どちらかと言うと、楽しい気分に盛り上げてくれるほうかも。
▼究極のゆらぎ「癒しの鐘」久乗編鐘(デラ)
小馬崎達也/PLAY 鈴木松美/PRD
こないだサケ友が「鐘 の音は神経を癒す」みたいなことをゆっていたのを思い出して借りてみた。
の音は神経を癒す」みたいなことをゆっていたのを思い出して借りてみた。
ヨーロッパの教会にあるような大きな釣鐘式の鐘か、日本の除夜の鐘みたいな音を想像していたんだけど、
もっと優しくて、やわらかな響きの余韻に包まれる音。「おリン」て仏壇にあるアレのこと?驚
監修は、あの「バウリンガル」の開発にも関わった、鈴木松美さん。
演奏は、小馬崎達也さんが即興のイメージから仕上げたんだって
【ライナーノートメモ】
 f/1ゆらぎ:
f/1ゆらぎ:
なんだか難しいことは分からんが、音の周波数(高低)と振幅(大小)の時間的変化が関係していて、
fはfrequency(周波数)のこと。
このゆらぎの定義に適った音を聴くとα波が増加してリラックスできるんだって
 4種の脳波(それぞれ聴く音楽で反応する脳波がある
4種の脳波(それぞれ聴く音楽で反応する脳波がある
・β波:通常におきて活動している状態。緊張している時、ストレスで優勢となる。→沈んでいる時、気分を高揚させたい時に聴く
・α波:リラックスしている時→リラックスしたい時に聴く
・θ波:まどろみ、または覚醒時
・デルタ波:無意識、熟睡中

脳が情報処理を行っていない時:α波+β波の両方が活動している。
→情報処理を行っている時:α波+β波がともに減少するが、α波のほうがより多く減少する
 リラックスが大切!
リラックスが大切!
リラックスしている時には、自律神経系の副交感神経が優位に働く
→消化酵素が適度に分泌され食事も美味しい 、イライラや不安感が緩和される、
、イライラや不安感が緩和される、
熟睡、緊張による肩凝りや頭痛も軽減、血圧・呼吸・脈拍も安定する
 おリン
おリン
・2400年前の中国では、編鐘という楽器だった/驚(12音階あった
・単体でも効果はあるけど、複数だとより良い=西洋の教会での賛美歌合唱や、東洋の寺院での聲明にもみられる
▼疲労回復~なぐさめとはげまし~ 決定盤アルファー波分析によるストレス解消クラシック②
貫行子/企画・監修
穏やかな音調で、聴きなれたクラシック曲も入っている。
【ライナーノートメモ】
・音楽の起源=祭礼・病気治療
・アリストテレス、プラトンらは「アポロン(音楽と医術の神)」+「ディオニュソス(酒神)」に例え、
精神を平静に導くもの+興奮させるものの2つの機能性を述べた。
 テクノストレス(PC・OA機器)には、音楽などの芸術が効果あり
テクノストレス(PC・OA機器)には、音楽などの芸術が効果あり
・ベトナム戦争の帰還兵たちの心身症がミュージック・セラピーによってのみ治癒できた/驚
・日本では東京芸術大学の桜林さん+貫行さん(このCDの監修者)が20年前に初めて音楽療法を紹介
・ストレス→緊張→ホメオスタシス(自己治癒力)が崩れる→病気になる
 同質の原理→カタルシスへ
同質の原理→カタルシスへ
・聴く人のその時点での気分から始める→目標とする感情に導く
・カタルシス:抑圧された感情や、コンプレックスを発散・浄化する
緑は、安らぎの色(リンク・最近のわたしのお気に入り
▼月経前のストレスをやわらげる 女性のためのリラックス・クラシックス6
松野 弘明/vn 渡辺 一正/P ミシェル・ベロフ/P
実際、わたしも月経前の1週間は、わけもなく憂鬱になり、ネガティブになるから 、
、
月経前だと意識していないと、本気で落ち込んでしまうので、音楽で解消できるなら嬉しいけど、
意外と最初から刺激的なヴァイオリンの音色なんだね/驚
【ライナーノートメモ】
 女性のバイオリズム:①月経期→②卵胞期→③黄体期
女性のバイオリズム:①月経期→②卵胞期→③黄体期
①同じストレスでも過剰に反応。ネガティブになる
②安定期。ポジティブ。肌の調子も良い
③肌荒れ。感情的になる(あれ?じゃあ、調子の悪い時のほうが多いじゃん
 自分のバイオリズムを知り、女性であることを肯定的にとらえ、気持ちを抑え込まないこと
自分のバイオリズムを知り、女性であることを肯定的にとらえ、気持ちを抑え込まないこと
PMS(月経前緊張症)←わたしもコレの傾向があるってこないだ主治医に言われた
・黄体ホルモンのピーク→急激な消退→不快症状と感じる
例:顔や背中にできるニキビ、肌荒れ、頭痛、便秘、下腹部緊満、下腹痛、乳房緊満、便秘、むくみ、不眠、眠気、集中力の低下などなど・・・
・マグネシウム、ビタミンB6不足、エストロゲンの急激な消退
【対策】
・まずPMSだと認識する。
・月経1週間前はスポーツ、趣味で気分をほぐす。
・同質の原理→カタルシス→リラックス→α波で満たす→ハッピーにって過程は、上記の「疲労回復」と同じなんだ。
【リラクセーション・ミュージック】
▼くじらの詩~マインド・リラクゼーション~
クジラは大好きだから、鳴き声はこれまでも何度か聴いたことがあって、癒し系にはよさげ。
たくさんシリーズがあるのね。図書館にはこれしかなかったような・・・?
▼アジアン・ヒーリング
ルーマーズ・アンビエント・プロジェクト/COMP ほか
これはふつーにアジアン音楽として楽しめる。
どちらかと言うと、楽しい気分に盛り上げてくれるほうかも。
▼究極のゆらぎ「癒しの鐘」久乗編鐘(デラ)
小馬崎達也/PLAY 鈴木松美/PRD
こないだサケ友が「鐘
 の音は神経を癒す」みたいなことをゆっていたのを思い出して借りてみた。
の音は神経を癒す」みたいなことをゆっていたのを思い出して借りてみた。ヨーロッパの教会にあるような大きな釣鐘式の鐘か、日本の除夜の鐘みたいな音を想像していたんだけど、
もっと優しくて、やわらかな響きの余韻に包まれる音。「おリン」て仏壇にあるアレのこと?驚
監修は、あの「バウリンガル」の開発にも関わった、鈴木松美さん。
演奏は、小馬崎達也さんが即興のイメージから仕上げたんだって

【ライナーノートメモ】
 f/1ゆらぎ:
f/1ゆらぎ:なんだか難しいことは分からんが、音の周波数(高低)と振幅(大小)の時間的変化が関係していて、
fはfrequency(周波数)のこと。
このゆらぎの定義に適った音を聴くとα波が増加してリラックスできるんだって

 4種の脳波(それぞれ聴く音楽で反応する脳波がある
4種の脳波(それぞれ聴く音楽で反応する脳波がある・β波:通常におきて活動している状態。緊張している時、ストレスで優勢となる。→沈んでいる時、気分を高揚させたい時に聴く

・α波:リラックスしている時→リラックスしたい時に聴く

・θ波:まどろみ、または覚醒時
・デルタ波:無意識、熟睡中


脳が情報処理を行っていない時:α波+β波の両方が活動している。
→情報処理を行っている時:α波+β波がともに減少するが、α波のほうがより多く減少する

 リラックスが大切!
リラックスが大切!リラックスしている時には、自律神経系の副交感神経が優位に働く
→消化酵素が適度に分泌され食事も美味しい
 、イライラや不安感が緩和される、
、イライラや不安感が緩和される、熟睡、緊張による肩凝りや頭痛も軽減、血圧・呼吸・脈拍も安定する

 おリン
おリン・2400年前の中国では、編鐘という楽器だった/驚(12音階あった
・単体でも効果はあるけど、複数だとより良い=西洋の教会での賛美歌合唱や、東洋の寺院での聲明にもみられる
▼疲労回復~なぐさめとはげまし~ 決定盤アルファー波分析によるストレス解消クラシック②
貫行子/企画・監修
穏やかな音調で、聴きなれたクラシック曲も入っている。
【ライナーノートメモ】
・音楽の起源=祭礼・病気治療
・アリストテレス、プラトンらは「アポロン(音楽と医術の神)」+「ディオニュソス(酒神)」に例え、
精神を平静に導くもの+興奮させるものの2つの機能性を述べた。
 テクノストレス(PC・OA機器)には、音楽などの芸術が効果あり
テクノストレス(PC・OA機器)には、音楽などの芸術が効果あり・ベトナム戦争の帰還兵たちの心身症がミュージック・セラピーによってのみ治癒できた/驚
・日本では東京芸術大学の桜林さん+貫行さん(このCDの監修者)が20年前に初めて音楽療法を紹介
・ストレス→緊張→ホメオスタシス(自己治癒力)が崩れる→病気になる
 同質の原理→カタルシスへ
同質の原理→カタルシスへ・聴く人のその時点での気分から始める→目標とする感情に導く
・カタルシス:抑圧された感情や、コンプレックスを発散・浄化する
緑は、安らぎの色(リンク・最近のわたしのお気に入り

▼月経前のストレスをやわらげる 女性のためのリラックス・クラシックス6
松野 弘明/vn 渡辺 一正/P ミシェル・ベロフ/P
実際、わたしも月経前の1週間は、わけもなく憂鬱になり、ネガティブになるから
 、
、月経前だと意識していないと、本気で落ち込んでしまうので、音楽で解消できるなら嬉しいけど、
意外と最初から刺激的なヴァイオリンの音色なんだね/驚
【ライナーノートメモ】
 女性のバイオリズム:①月経期→②卵胞期→③黄体期
女性のバイオリズム:①月経期→②卵胞期→③黄体期①同じストレスでも過剰に反応。ネガティブになる

②安定期。ポジティブ。肌の調子も良い

③肌荒れ。感情的になる(あれ?じゃあ、調子の悪い時のほうが多いじゃん

 自分のバイオリズムを知り、女性であることを肯定的にとらえ、気持ちを抑え込まないこと
自分のバイオリズムを知り、女性であることを肯定的にとらえ、気持ちを抑え込まないこと
PMS(月経前緊張症)←わたしもコレの傾向があるってこないだ主治医に言われた
・黄体ホルモンのピーク→急激な消退→不快症状と感じる
例:顔や背中にできるニキビ、肌荒れ、頭痛、便秘、下腹部緊満、下腹痛、乳房緊満、便秘、むくみ、不眠、眠気、集中力の低下などなど・・・
・マグネシウム、ビタミンB6不足、エストロゲンの急激な消退
【対策】
・まずPMSだと認識する。
・月経1週間前はスポーツ、趣味で気分をほぐす。
・同質の原理→カタルシス→リラックス→α波で満たす→ハッピーにって過程は、上記の「疲労回復」と同じなんだ。











 祝×∞
祝×∞
 クドカンも出てたの
クドカンも出てたの 驚×5000 観たいなあ!
驚×5000 観たいなあ!
 でよく歌った♪
でよく歌った♪




 を無意識に見ている視聴者に与える
を無意識に見ている視聴者に与える を自分で買うっ
を自分で買うっ




 だったけど、
だったけど、 デラックスツアーになかった曲だったのか、キミノリさんのドラムが即興っぽかった?
デラックスツアーになかった曲だったのか、キミノリさんのドラムが即興っぽかった? 「興ざめと書いて鈴木興~!」って紹介が笑った
「興ざめと書いて鈴木興~!」って紹介が笑った
 持っての2ショットもあり(ほんと似てた!
持っての2ショットもあり(ほんと似てた!



 ユキさんコーナー
ユキさんコーナー
 /爆
/爆

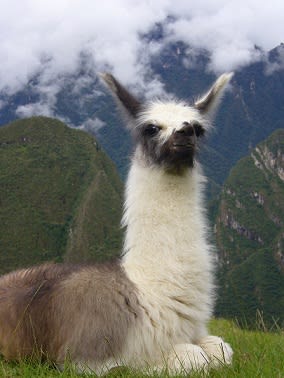
 でも落ち着かず、ソラナックスを半錠飲んだ。
でも落ち着かず、ソラナックスを半錠飲んだ。 などが気になることを伝えた。
などが気になることを伝えた。 )から、それに関する本をこんど教える」と約束してくれたv
)から、それに関する本をこんど教える」と約束してくれたv
 が、
が、


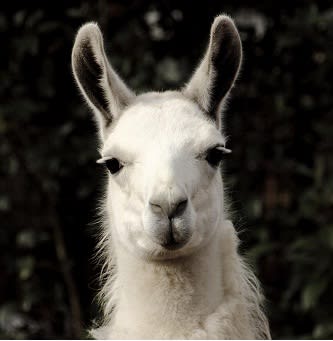



 。
。
 、FR値が上がる
、FR値が上がる なら10分入って、10分休むならやってるよ
なら10分入って、10分休むならやってるよ
 などに含まれるイミダゾールジペプチドはFRを作るv
などに含まれるイミダゾールジペプチドはFRを作るv も良いv
も良いv
 なんてテレビでゆっちゃうと、
なんてテレビでゆっちゃうと、
 のち雨
のち雨 。
。 大好きなF氏と、うどんブームなわたしが行ったのは、こちら。
大好きなF氏と、うどんブームなわたしが行ったのは、こちら。
 まであって、とっても落ち着ける雰囲気。
まであって、とっても落ち着ける雰囲気。
 (たまにわんこ
(たまにわんこ








 を注文。
を注文。


 3×2で入って、1回転倒。
3×2で入って、1回転倒。 最後までスピード落ちずにキメタ。
最後までスピード落ちずにキメタ。 もスゴイ!
もスゴイ!
 みたいなのが苦手で、
みたいなのが苦手で、


 w 戻ってきてもものすごいガッカリ顔
w 戻ってきてもものすごいガッカリ顔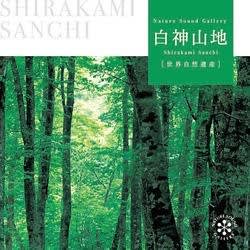



 、携帯
、携帯 、メール中心で、直接的な対話ではなく、無機質なデジタルの媒介が入っている
、メール中心で、直接的な対話ではなく、無機質なデジタルの媒介が入っている の光を浴びる。早起きはセロトニンを合成する
の光を浴びる。早起きはセロトニンを合成する
 、家族との食卓を囲んでの対話、女子会など、他人とのコミュニケーション。
、家族との食卓を囲んでの対話、女子会など、他人とのコミュニケーション。 。マッサージやエステに行くなど。
。マッサージやエステに行くなど。





