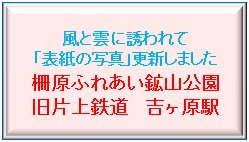しかし、調べを進めるうちにここで一つの疑問がわいてくる。
東高野街道の起点が、なぜ京都南部の石清水八幡宮なのだろうか。
同じ京都とは言え、この地は当時の都の中心から見れば数里も離れた地である。

都人にとって、起点の石清水八幡宮まではどのようなルートを辿ったのか、色々
調べては見るのだが、これが今一つ釈然としない。

資料によっては、高野街道は「京都の東寺を起点として・・・」と書かれているもの
もあるし、後日実際に東高野街道を歩いてみると、その道中の案内板にも同様な
ことが書かれていた。しかし、石清水八幡宮から先は色々紹介したものがあるのだ
が、その東寺から具体的に高野街道と呼んだルートを示すものには中々お目に
かかれないのだ。

昔から京都には東に鴨川、西に桂川が流れ、それはやがて宇治川や木津川と
合流し、最後は淀川となって瀬戸内海に注いでいるが、その合流地点が淀であり、
丁度その対岸が石清水八幡宮のある地であることが地図を見るとよく解る。

昔から淀には「津(今で言う港)」が有ったことが知られているので、当時は舟便が
発達していて、これから迎えるであろう過酷な道中に備え体力を温存するためにも
都からここまでは舟で往来したのでは・・などと愚考してみたりもする。

しかし、それにしては数里もの舟旅とは、余りにも距離が長すぎる。
貴人や通信使なら兎も角、お参りの庶民の交通の足としては考えにくく、やはり陸
路を歩いていたと考えるのが自然である。
そうなると思い当たるのはあの街道しかない。

(写真:四国遍路道・歯長峠越え)(続)
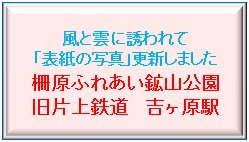

 にほんブログ村
にほんブログ村
東高野街道の起点が、なぜ京都南部の石清水八幡宮なのだろうか。
同じ京都とは言え、この地は当時の都の中心から見れば数里も離れた地である。

都人にとって、起点の石清水八幡宮まではどのようなルートを辿ったのか、色々
調べては見るのだが、これが今一つ釈然としない。

資料によっては、高野街道は「京都の東寺を起点として・・・」と書かれているもの
もあるし、後日実際に東高野街道を歩いてみると、その道中の案内板にも同様な
ことが書かれていた。しかし、石清水八幡宮から先は色々紹介したものがあるのだ
が、その東寺から具体的に高野街道と呼んだルートを示すものには中々お目に
かかれないのだ。

昔から京都には東に鴨川、西に桂川が流れ、それはやがて宇治川や木津川と
合流し、最後は淀川となって瀬戸内海に注いでいるが、その合流地点が淀であり、
丁度その対岸が石清水八幡宮のある地であることが地図を見るとよく解る。

昔から淀には「津(今で言う港)」が有ったことが知られているので、当時は舟便が
発達していて、これから迎えるであろう過酷な道中に備え体力を温存するためにも
都からここまでは舟で往来したのでは・・などと愚考してみたりもする。

しかし、それにしては数里もの舟旅とは、余りにも距離が長すぎる。
貴人や通信使なら兎も角、お参りの庶民の交通の足としては考えにくく、やはり陸
路を歩いていたと考えるのが自然である。
そうなると思い当たるのはあの街道しかない。

(写真:四国遍路道・歯長峠越え)(続)