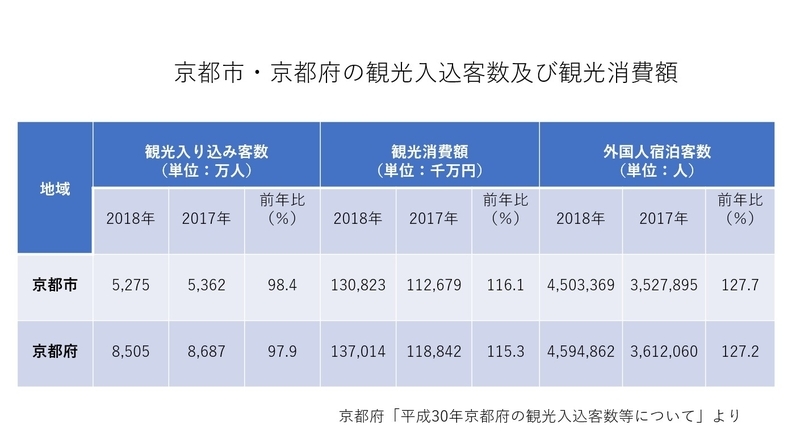jlj0011のblog
まず三馬鹿トリオ打倒<本澤二郎の「日本の風景」(4456)
2022/05/26 08:241
前の記事
ホーム
まず三馬鹿トリオ打倒<本澤二郎の「日本の風景」(4456)
<安倍・小泉・森の3人が日本を破綻させた真犯人>より、転載させて頂きました。
三馬鹿トリオ?よく分からないので、ネットで調べると、アメリカでは三馬鹿大将という3人の芸人が、日本では漫画か小説に三馬鹿トリオが。永田町の三馬鹿トリオとは、日本の内外政を破綻させた清和会の極右・日本会議神社神道派の安倍・小泉・森を指す。清和会の歴史と共に歩んできた御仁の指摘で、このままでは15年後の日本は、極東の小さな島国になると予言する。想定できるだろう。
古来より国家の盛衰は、指導者の資質に左右される。舵取りいかんにかかっている。この3人とも福田赳夫が創立した清和会と縁が薄いか、全くない大バカ者である。清和会を飛び出して、政権を手にした面々ばかりだ。安倍の実父・晋太郎は、清和会事務総長の塩川正十郎が「安倍は清和会の人間ではない」と断じていた。
息子の安倍晋三は、清和会候補の町村信孝を蹴落として政権を手にした。町村は怒り心頭して他界した。無知蒙昧の徒である長州の田布施晋三を男にしたのは、薩摩の田布施小泉純一郎だった。小泉がなぜ清和会を除外して、晋三にテコ入れしたのか。それは小泉が繰り返し靖国神社を参拝し、アジア諸国民を恐怖に陥れたことから、二人とも靖国派・日本会議の有力メンバーであった、そのためだった。
森喜朗が政権にありついた理由も怪しい。時の首相の小渕恵三が倒れ、官邸と党本部役員の談合でその地位に就いた。亀井静香もその中にいた。事情を知る人物だ。告白してもらいたい。案の定森は神道政治連盟という、神がかりの原始宗教・神社神道・神社本庁指揮下の集会で「日本は天皇中心の神の国」と時代錯誤の本性をさらけ出した。原始宗教のカルト教団が生み出した人物であることを、自ら明らかにして、墓穴を掘って小泉と交代した。
もはや福田赳夫が創立した清和会は存在しない。三馬鹿トリオの清和会に堕してしまった。最近まで清和会会長だった原子力ムラのボスのような細田吉蔵の倅・博之を、歴史を知らないジャーナリストは今も記憶している。年収5000万円以上の血税を懐に入れている細田博之衆院議長は「月収100万円」と大嘘・出鱈目発言をして、国民の怒りを買っている。それどころかセクハラ事件で追及されて、辞任必至である。
安倍はというと、民衆の生活苦を屁とも思わないで、急激な円安物価急騰を放置、相変わらず莫大な円刷りを強行するだけで、物価高の日本に追い込んでいる。日銀の黒田は、庶民の敵である。そんな輩を日銀総裁にした安倍は「日銀は政府の子会社だ」と大嘘を垂れた。安倍に屈する岸田文雄も、これには国会で「そんなことはない」と否定答弁した。清和会OBは「安倍は日銀法も知らないで首相を8年も。安倍を担いできた日本人が問われている。それを許してきた新聞テレビに反吐が出る」と今朝ほどの電話で痛撃した。
清和会三馬鹿トリオを打倒しないと、10年15年後の日本は消えるだろう。本心からそう思う。言論人は覚醒して、まともな記事を書け、と叫ぶしかない。
<戦争三法を強行したアジア蔑視の晋三と太田ショウコウ>
安倍の罪は三馬鹿の中でも突出している。教育勅語の戦前教育の猛省から誕生した教育基本法を改悪しただけではなかった。戦争する日本へと戦争法を強行した。安倍一人ではできない。公明党創価学会の代表だった太田ショウコウも動員した。
特定秘密保護法・自衛隊参戦法・共謀罪の戦争三法は、憲法に違反する。「安倍も大馬鹿、彰晃ならぬ太田も、憲法を読んでない大馬鹿三太郎」と指摘されている。あまつさえ「防衛費を倍増せよ」とがなり立てている晋三に腹が立つ。しかし、安倍を擁立した日本国民が存在したことを忘れてはなるまい。
「半島出身者がなぜ半島の韓国をいびるのか。信じられない」と指摘する声も紹介せざるを得ないだろう。国民は何も知らない。ヒロヒトが昭和天皇であることも。戦後教育の悪しき実績である。
<小泉の靖国参拝でアジアの孤児となった日本>
小泉は、戦争神社として、国際的に指弾されている一宗教法人にすぎない靖国神社を、繰り返し参拝した。
日本国民の国際的評価を貶めた罪は計り知れない。赤紙一枚で戦場に犬猫同然に引きずり出され、命をなくした元凶である国家神道に合祀されというカラクリに興じ、満足する現代人がいるであろうか。子供じみたお祓いカルト教に再び?賭ける日本人がいるはずもない。
再び人の尊い命を、二度と犬死させるカルト教団は百害あって一利なしだ。福田康夫のいうように、靖国に代わる非宗教的な記念碑を建てることが、国際社会を安心させることである。靖国はいらない!
<「天皇中心の神の国」と戦前の国家神道復活宣言した喜朗>
安倍の靖国参拝、小泉の靖国参拝は、つまるところ森喜朗の狂気の日本論に集約することが出来る。
それはすなわち自民党に巣食う神道政治連盟という、戦前の国家神道をそっくり継承した宗教法人・神社本庁というカルト教団の政治組織、その主要メンバーが極右派閥・清和会ゆえである。明治が人工的に作り上げた戦争体制の中枢に位置するカルト教である。ここが天皇制国家主義の元凶なのだ。
ロシア・ウクライナ戦争でも、背後に宗教が控えて、戦場に散る若者を鼓舞する役割を担っているように、すべての戦争に宗教が関与する。そうして双方の若者の命を奪うもので、女子供が多く犠牲にされる。そのための装置を、到底容認することは出来ない。
小泉・安倍の靖国参拝は、新たな死者を作り出そうとする悪しき権力者の野望と見て取れるだろう。こんな幼稚な罠にかかる現代の若者がいるだろうか。戦場へとおびき出すカラクリ組織を憲法が容認しない。
神社神道の集会で、森は「日本は天皇を中心とする神の国」と途方もない日本論をがなり立てた。正に戦前の侵略戦争も持さないキチガイじみた国家論を提起して見せた。戦前の国家神道復活が見て取れるだろう。戦争こそが、空前絶後の利権を生み出すことも承知すべきだろう。
<10年後の小さな島国=清和会OBの天皇制廃止論が見えてきた>
三馬鹿トリオの実績は、つまるところ日本の衰退を裏付けている。アベノミクスで日本は、1%族を除いて絶望の淵を歩かされている。1%のための軍拡だけが具体化している。新たな戦争へと鎌首をもたげている自公政府だ。
バイデン来日と台湾有事は、一本の糸で結びついている。日本を第二のウクライナにしようとしている。日中激突へとワシントンは狙いを定め、それに掉さす自民党と公明党創価学会、維新それに連動する労働組合・連合の姿が見えるだろう。
さればこそ、清和会OBが根源である天皇制について「廃止せよ」と大声を上げ始めた。10年後の小さな島国に、警鐘を鳴らしている。同意できる。
2022年5月26日記(東芝製品不買運動の会代表・政治評論家・日本記者クラブ会員)
コメントを書く
コメント(0件)
カテゴリなしの他の記事
ゼレンスキー効果<本澤二郎の「日本の風景」(4455)
はしゃぐ日本国の文雄君<本澤二郎の「日本の風景」(4454)
慟哭の人生を出版<本澤二郎の「日本の風景」(4453)
人間はカラスより下等動物<本澤二郎の「日本の風景」(4452)
岸田文雄首相にもの申す<本澤二郎の「日本の風景」(4451)
前の記事
ホーム
LINEで送るこのエントリーをはてなブックマークに追加
コメントを書く
読者登録
Feedlyで購読する
日記 カテゴリ人気ブログ
1
白一色 #Twitterでしかできない話
ガレ速@滝沢ガレソまとめ速報
2
WEFは新世界秩序実現のための最後の攻撃を準備する
メモ・独り言のblog
3
天皇夫妻 沖縄復帰50年特別展「琉球」を鑑賞
remmikkiのブログ
4
[イコラブ] オサレカンパニーさん『 あの子コンプレックス...
イコラブ@プレス(イコラブまとめ)
5
ノジマオンラインにて販売中!映画「五等分の花嫁」 ~君と過...
★レアモノ在庫再販速報
もっとみる
ブログ
ランキング
ブログ速報
livedoor Blog
PCモード
トップへ
Powered by livedoor Blog