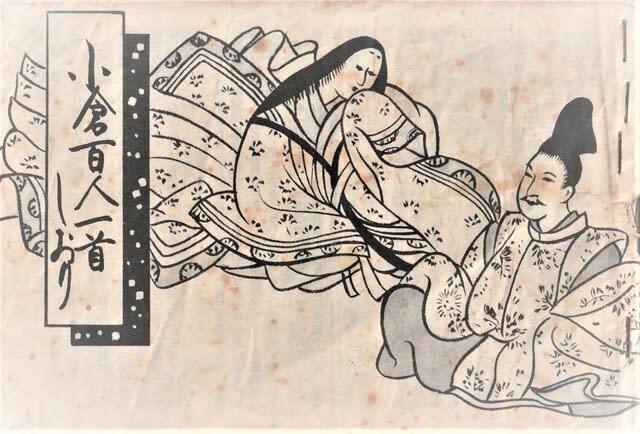長男、次男がまだ保育園、小学生だった頃は、夫婦共働きで、時間的余裕も、精神的余裕も、経済的余裕も無い自営業を続けていた時代ではあったが、せめて子供達の思い出になれば・・・との思いが有って、春、秋の行楽シーズン等の休日には、忙中敢えて閑を作り、強引に?、家族で周辺の低山を、よく歩き回っていたものだった。その後、次男が小学生になった頃からは、「せめて毎年1回、夏休みには、家族で登山しよう」と決め込んで、尾瀬や八ヶ岳や白馬岳、乗鞍岳、木曽駒ケ岳、仙丈岳等、夏山登山をしていたが、それまで、登山の経験等ほとんど無く、体力にも自信が無く、山の知識情報にも疎かった人間が、よくもまあ思い切って出掛けたものだと、後年になってからつくづく思ったものだった。長男、次男が巣立ってからも、その延長線で、夫婦で細々、山歩きを続けてはいたが、10数年前に完全に仕事をやめてからは、時間が出来たものの、今度は気力体力が減退、あの山もこの山も、今や、遠い思い出の山となってしまっており、今となっては、あの頃、思い切って、登山を敢行していて、本当に良かったと思うようになっている。ブログを始めてからのこと、そんな山歩きの思い出を、備忘録、懐古録として、ブログ・カテゴリー「山歩記」に書き込み、古い写真は、「デジブック」にし、ブログに貼ったりしていたものだが、その後、「デジブック」が終了したことで、ブログから写真が消えてしまい、改めて、順次、古い写真を引っ張り出して、過去の記事をコピペ、リメイク(再編集)しようと思っているところだ。昔のことを懐かしがるのは、老人の最も老人たるところだと自嘲しながら・・・・。
古い写真から蘇る思い出の山旅・その68
「湯ノ丸山」(再)
かれこれ27年前の1997年6月に、妻と二人で、長野県の東部、群馬県との県境にある「湯ノ丸山」を訪れたことが有った。
当時はまだ、自営業を続けていた頃で、時間的余裕も、精神的余裕も無かった頃だったが、6月下旬の土曜日、たまたま仕事の予定無しで、「6月上旬から下旬にかけて、山肌を真っ赤に染める湯ノ丸山のレンゲツツジの花期も終盤」等という情報も目にして、折しも、台風8号が九州に接近中、梅雨前線が刺激され、各地で大雨という天気予報が出ていて、甲信越地方も、まったく天気回復の見込み無しの、最悪の状態だったが、「現地に行って見なけりゃ分らない・・・」、等と、一縷の望みを持って強行した気がする。
山行コース・歩程等
地蔵峠駐車場→つつじ平→湯ノ丸山山頂南峰・北峰→つつじ平→地蔵峠駐車場
(標準歩行所要時間=約2時間)
(昭文社の「山と高原地図」から拝借)

毎度のこと、自宅を夜明け前に出発、
関越自動車道、上信越自動車道、小諸ICから国道18号線を走り、
7時頃、湯ノ丸高原、「地蔵峠駐車場(標高1,700m)」に着いたようだ。
国道18号線走行時には、やや雨雲が薄れ、天気回復を期待したりもしたが、
標高を上げるに従い、雨脚が酷くなり、駐車場到着時は、
「どうする?」、状態。
車の中で、思案しながら、一時待機。
諦めて、信州ドライブ旅にでも、切り替えようかと迷ったが、
続々とハイカーの車が到着、
みるみる、駐車台数が20台前後にもなり、
次々と雨具着用で出発していくハイカーを見て、
「その内いつかまた・・・」なんて言ってられないという思いも有り、
背中を押され、やおら 雨具、スパッツを着用、出発と相成った。
もともと、レンゲツツジの見頃は、梅雨時期と重なるため、
雨降りは覚悟は上で、その準備はしていたのだったが・・・。
雨中山歩きだったこともあり、
バカチョンカメラ(ポケット型小型フィルムカメラ)しか持っていなかった頃で、
証拠写真?的スナップ写真、数枚しか撮っていなかったが、
プリントした写真が古いアルバムに貼って有る。
ブログを始めた頃に一度、スキャナーで取り込んで、
ブログに書き込んだことが有ったが、
その写真、外付けHDに保管されており、改めて引っ張り出して、
コピペ、リメイクしてみることにした。
7時15分頃、「地蔵峠駐車場」を出発、

ゴゼンタチバナ、 コイワカガミ





つつじ平
レンゲツツジの群落、

9時頃、湯ノ丸山山頂(南峰)(標高2,103m)に到着、
残念ながら、雨は降り止まず、大展望叶わず、



9時15分頃、大きな岩が積み重なったような、
湯ノ丸山(北峰)山頂に到着、


お目当ての360℃大展望は、叶わずだったが、
一瞬、ガスが途切れ、眼下の「つつじ平」の景観が見られ・・、
ラッキー!、

天候が良ければ、湯ノ丸山から、さらに鳥帽子岳往復も予定していたが、
中止し、下山することにした。
皮肉にも、下山途中から雨が上がり始め、周辺が見えだし・・・。




11時頃、地蔵峠に戻った頃には、すっかり雨が上がって、周辺の山が見えだし・・・、
なんだかなーー、だったが、
とりあえずは、湯ノ丸山山頂までピストン出来たことと、
好天だったら、大変な人出だったはずで、
むしろ、静かな山歩きが出来たことで、納得、
時間的にはゆとりが有ったが、早々、帰路に着いたのだった。
当時は、「また来る時には、笑っておくれ♪」的気分だったはずだが、
その後、訪れる機会は無く、
足、腰、痛!、痛!になった今となっては、
「湯ノ丸山」も、遠い思い出の山になってしまっている。
雨で煙ったレンゲツツジ大群落の景観が、脳裏に焼き付いた山旅だった。