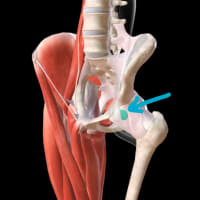さて、前回の続きです。
前回は傷めた時には傷めた時の攻め方がある と申し上げました。
と申し上げました。
後編ではその攻め方について、治療家の視点から掘り下げてゆきます。
では、始めましょう。
【痛めている間も成長を諦めない!~「痛み」というサインの有効活用~】
前編でお話しした通り、ケガを負った個所は組織の耐久性が低くなっています。
なので、怪我を負う前には問題なく耐えられた負荷であっても、組織が耐えられずに壊れてしまうような「過剰な負荷」となってしまうような状況も生じるわけです。
そうしたときに患部が発する警報が「痛み」だという前提をご理解いただきたい。
この事実、裏を返せば「痛み」を感じない範囲の動作や負荷であれば故障を悪化させることは無いということです。
傷ついた組織も回復の速度を上回る傷がつかなければ癒えます。
脆くなった傷跡もトレーニング(リハビリ⁉)によって負荷される微細な傷が回復の範囲内のものであれば、ちゃんと超回復して強化することができるのです。
大事なのは匙加減なんですね。
その匙加減は「何%の負荷で何Repを何Sets」といった尺度ではなく「痛みが出ない範囲」であるということです。
実際は痛みが出る前に「違和感(不安感)」が出てきますから、それを感じたらその負荷を超えようとはしないよう気を付けるということです。
さて、「痛み」というサインを実際に故障時のトレーニングに有効利用するための要点は以下の2点。
1:痛みが出ない範囲の重量を選ぶ
2:痛みが出ない角度の中で運動をする
簡単でしょう⁉
もう少し具体的に言いますと、
例えば…
スクワットで深くしゃがむと膝が痛むようなケースを挙げましょうか。
このケースで言うならば、
「痛まない範囲で(つまり浅め)の屈伸にとどめてスクワットをする」
ということです。
しゃがんでいって患部に違和感を感じるか感じないかのところで切り返す。
そんな感じです。
この時、重量は「患部が痛まない範囲」で追いかける(増してゆく)ことになります。
つまり…
攻めていいんです(*^^*)
あくまで膝の痛みがない範囲で、ですけどね。(^^;
具体的な工夫としては、ベンチ台をお尻の下に置いてお尻がベンチに触れたら立つ「ボックススクワット」なんて方法や
パワーラックの中でセーフティーバーを高めに上げてバーベルのシャフトがバーに触れたら立つ、
といった工夫でしゃがむ「深さ」を「痛み(違和感・不安感)の出ない深さ」に調整してスクワットをするんです。
通常、スクワットは浅くなればなるほど扱える重量は高くなりますので、膝の状態によっては今まで担いだことの無いような大きな重量を担ぐことにもなります。
そうなると体幹に掛かる負荷は今までの経験にない領域にまで達することになりますので、体軸の強化にも役立てることができます。
普段の練習では強化しきれない能力を高めることができますね。
それが復帰後のパフォーマンスにプラスに働くことも十分に期待できます。
これぞ怪我の功名ってやつです。
それから、重くなると痛みが出るようなケースもありますよね。
重りが軽いうちは痛みなく底までしゃがむことができるのに、メインセットに差し掛かると痛くなる。
そうしたケースでは痛みが出ない範囲まではフルスクワットも「可」です。
患部に違和感が感じられ始めたら(痛みが出る手前とうこと)高さを調節したスクワットに切り替えてみてください。
この場合でも、同じく患部の痛まない範囲で重量は追いかけることになります。
ちなみに重量を追いかけるときには5~3RepMAX(87~90%)あたりまでが妥当です。
なぜ1MAXではなく3~5RepMAXなのか?というと、故障の背景に考慮しての選択です。
怪我の背景にはフォームの崩れが必ず絡んでいます。
「フォームの崩れ方=怪我の現れ方」とも言えますので、再受傷のリスクを避けるためにもフォームをしっかりとコントロールしておく必要があるんです。
患部の痛みが生じることなく、重量に挑戦しつつもフォームが安定していられる範囲が何%かは個人差があると思いますが、個人的には95%から先の重量(=2Rep)はちょっとしたフォームの崩れも立て直すのが難しくなりますから
若干のフォームの崩れもなんとか立て直しが効く範囲ということで3~5Repとしました。
あくまで私自身の練習を通じた感想なので、自身の経験と照らし合わせて決めてください。
この3~5REPが「選手クラス」の方に当てはまるかどうかは一考の余地ありなのですが、
重量挙の試合なんかをみていても、95%を超えるような場合には失敗も増えてくるように思います。
それは試合独特の緊張感の中、平常心を保ちがたいという心理的要因も作用しているのでしょう。
怪我というアクシデントに遭うと「自信の喪失」を抱きやすく、そうした心理的な脆さからもフォームが乱れやすくなります。
そうしたところを照らし合わせての「3~5Rep」です。
ま、自身があれば3、不安が勝てば5といったところでしょうかね。
それよりも、大事なのは
「痛み」を気合で乗り越えようとしない
ということです。
「痛み」は「乗り越えるべき壁」にせず、安全にトレーニングができるシチュエーションを探すための
「センサー」
として利用しましょう。
間違っても
「ボールは友達!痛くない!!」byキャプテン翼
的な発想はしないように。
ただ、この方法にも死角はあります。
運動時、私たちは興奮状態に入りますので「痛み」への感度は鈍るんです。
これが曲者…
運動を終えたあとに症状の悪化がみられるようであれば「頑張り過ぎ(やり過ぎ)」のサインです。
そうした場合は「追い込み方」を工夫してみるのも手です。
例えば、
1、痛みなく担げる範囲の角度と重量で3~5RepMAX(90%~87%)実施
2、RM法を使って40~50%の重量を算出し、スロートレーニングで追い込む
「1、」は今までの話のことです。
ここでの工夫は「2、」の「スロートレーニング」です。
「スロートレーニング」については何度か私のブログでも触れているので解説は省きますが、その利点をおさらいすると以下の通りです。
・成長ホルモンの分泌促進⇒故障部位の回復促進と筋肥大
・軽い重量でゆっくりとスクワットを繰り返すので、運動のエラーに気付きやすい⇒動作スキルの向上
ご存知の方も多いと思いますが、
成長ホルモンなどのホルモン分泌の促進は怪我からの回復に力強い味方となってくれますが
成長期を終えるとその分泌量は1/4とだいぶ少なくなってしまいます。
それを補うためにもスロートレーニングは強い味方となってくれます。
それだけをとっても「2、」のフェーズは意味を持つわけですが、その効用は「スキルの向上(フォームの正常化の意)」にも及びます。
繰り返しになりますが、怪我の背景にはフォームの崩れが必ず絡んでいます。
ですので、その点を修正するのにはじっくりと自身のフォームと向き合う必要があるわけです。
ゆっくりと動作を反復するスロートレーニングはフォームを確認しつつ修正するのに好都合。
怪我の回復を早め、怪我の原因も正してゆく
一粒で二度おいしいというか、非常にいい仕事をしてくれるのです。
と、まあツラツラと書きましたが、
故障時の対処として一番大事なのは可否の判断基準を明確に持つことだというのが私の意見です。
このように「痛み」を「安全な刺激量」を判断するための指標とするならば、
怪我というネガティブな出来事も取り組みようではポジティブに活かすことだってできる!ということを知ってほしいと思います。
とはいえ、怪我をしないに越したことはないのですがね(^^;
以上、【故障をした時も攻めのトレーニングを諦めない!!~「痛み」の有効活用法~】でした。
=おわり=