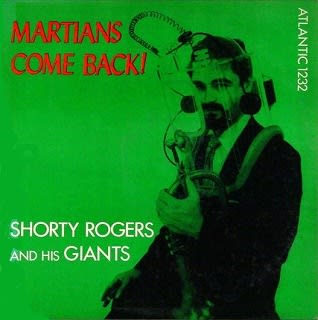■Amazig Grace The Complete Recordings / Aretha Flanklin
(Atlantic / Rhino = CD)
アメリカでは初めての黒人大統領が就任ということで、昨夜から今早朝にかけて、ついついテレビ中継を見てしまいました。なんか今日は仕事がキツイ感じです、もう若くありませんから……。
しかしそれにしても、あの黒人ゴスペル大会みたいなノリは凄かったですね。新大統領の演説には明らかにゴスペル伝道師の趣というか、明快な言葉で民衆の心を掴む説法のツボが使われていると感じました。
おまけにアレサ・フランクリンの熱唱までも!
ということで、本日は私の大好きなゴスペルアルバムを出してしまいました。
主役はレディソウルことアレサ・フランクリンが1972年に制作した、彼女自身が最大のベストセラーとなった「Amazig Grace (Atlantic)」を再発した完全版2枚組CDです。
アレサ・フランクリンは説明不要の黒人R&B歌手ですが、そのルーツはゴスペルであり、父親は有名なゴスペル説教師のクラレンス・フランクリンですから、大衆音楽の世界で成功したとはいえ、何時かはゴスペルの世界へ戻りたいと願っていたようです。
そしてその願望を最良の形で表したのが、1972年1月にLAのパブティスト教会で行った2夜連続のライブレコーディングを編集して作り上げた前述の2枚組アナログ盤LPでした。
まさに全身全霊で魂の歌を聞かせるアレサ・フランクリン(vo,p) をサポートするのは、ゴスペル界の巨匠たるジェィムス・クリーヴランド(vo,p)、南カリフォルニア・コミニュティー聖歌隊、そしてバックはコーネル・デュプリー(g)、チャック・レイニー(el-b)、バーナード・パーディ(ds)、ケン・ラッパー(org)、パンチョ・モラレス(per) という強力な面々ですから、たまりません!
そしてこの再発CDには、その2日間のコンサートが、極力編集を排除した流れで復刻されているのです。
☆Disc One / 1972年1月13日木曜日の夜
01 Organ Introduction / ケン・ラッパー
02 Opening Remarks / ジェィムス・クリーヴランド
03 On Our Way / 南カリフォルニア・コミニュティー聖歌隊
04 Aretha's Introduction
05 Wholy Holy
06 You'll Never Walk Alone
07 What A Friend We Have In Jesus
08 Precious Memories / アレサ・フランクリン&ジェィムス・クリーヴランド
09 How I Got Over
10 a. Precious Lord, Take My Hand
b. You've Got A Friend
11 Climbing Higher Mountains
12 Amaging Grace / アレサ・フランクリン&ジェィムス・クリーヴランド
13 My Sweet Lord (inst.)
14 Give Yourself To Jesus
上記演目のとおり、アレサ・フランクリンが登場する前段として、実に厳かな思わせぶりがあって、いよいよ主役が歌い出すのは、なんとモータウンの大スタアとして有名なマーヴィン・ゲイが書いた「Wholy Holy」ですよっ! あぁ、ここまでの盛り上げ方が実に上手いというか、全く見事な構成だと思います。当然、その場の観衆も出来あがっているのが、音だけでも充分に伝わってきますね♪♪~♪
で、その「Wholy Holy」はアレサ・フランクリンがピアノを弾き語り、メロウなコーネル・デュプリーのギター、ジンワリとして強いビートのドラムスとベースが、もういきなりの高得点! バックのコーラス隊も良い感じですし、もちろんアレサ・フランクリンは絶好調の泣き節が全開です。
原盤解説によれば、実はアナログ盤2枚組LPに入っていた同曲のバージョンは、この日と翌日のカラオケだけを利用して、スタジオでボーカルを録り直したそうですから、この自然なグルーヴと高揚感には、尚更に納得させられますねぇ~~♪
また有名スタンダード曲の「You'll Never Walk Alone」が崇高な雰囲気に満ちた名演に歌い直されているのには吃驚仰天! おまけにキャロル・キングやジェイムス・テイラーでお馴染みの「You've Got A Friend」までもがっ! あぁ、これがアレサ・フランクリンの凄さですし、真正ゴスペルのピアノと語りでサポートするジェームス・クリーヴランド、バックの聖歌隊の存在感も強い印象を残します。
そしてもちろん真っ当なゴスペルソングの名曲群も素晴らしいパフォーマンで、やはり彼女がピアノの弾き語りでグイグイとリードしていく「What A Friend We Have In Jesus」、その場の一体感が見事な「Precious Memories」、コーラス隊の素晴らしい実力が冴える「Precious Lord, Take My Hand」と「You've Got A Friend」のメドレー、軽快なゴスペルロック仕立ての「How I Got Over」、楽しげに高揚していく「Climbing Higher Mountains」と、実に自然体なグルーヴが満喫出来ます。
そして極みつきのとなるのが、アレサ・フランクリンとジェームス・クリーヴランドが魂の掛け合いを堪能させてくれる「Amaging Grace」です。もちろんコーラス隊と観客、バンドの面々も一体となった盛り上がりは、所謂「お約束」なんて言葉が不要の、無垢な感動しかありません。これはキリスト教徒でなくとも、間違いなく感じることの出来る名演だと思います。
さらにこの後に続くクロージングのインスト曲「My Sweet Lord」はジョージ・ハリスンの大ヒットとしてお馴染みのメロディが、最強のバンドによって祭りの後のせつなさで演じられます。あぁ、ここで聞かれるコーネル・デュプリーのギターは私の憧れ♪♪~♪ チャック・レイニーの蠢くベースにズバンズバンのビートが凄いバーナード・パーディ♪♪~♪ 地元のミュージャンだというケン・ラッパーのオルガンも流石の黒人ノリで最高ですよっ♪♪~♪
ちなみにオーラスに入っている「Give Yourself To Jesus」は、アナログ盤LP用に作られた素材で、この教会で録られたカラオケにボーカルとコーラスを後でダビングしたと、ライナーに書いてあるとおり、流石の完成度でジンワリと心が温まります。
☆Disc One / 1972年1月14日金曜日の夜
01 Organ Introduction ~ Opening Remarks
02 On Our Way / 南カリフォルニア・コミニュティー聖歌隊
03 Aretha's Introduction
04 What A Friend We Have In Jesus
05 Wholy Holy
06 Climbing Higher Mountains
07 God Will Take Care Of You
08 Old Landmark
09 Mary, Don't You Weep
10 Never Grow Old
11 Remarks By Reverend C.L. Franklin
12 Precious Memories / アレサ・フランクリン&ジェィムス・クリーヴランド
13 My Sweet Lord (inst.)
こちらのパートも基本的な構成は前日と同じですが、より剥きだしとなったゴスペルフィーリングが強烈な印象です。それは特に後半、前日とは異なる演目が入っている所為かもしれませんが、単純に言えば、ノリがますます良いんです♪♪~♪
じっくりと観客を煽っていく「God Will Take Care Of You」ではバンドの地味な伴奏が逆に凄く、狂騒的な「Old Landmark」の手拍子&足拍子の楽しさ、ジワジワと熱気に満ちていく雰囲気が素晴らしい「Mary, Don't You Weep」を聴いていると、宗教的な意味合いが深く込められた歌詞は完全に分からなくとも、そのハーモニーとボーカルの圧倒的な威力には思わず神に感謝の気持ちを抱くほどです。
生きているって、素晴らしい! それが苦しみの世界であっても!
そしてアレサ・フランクリンは「Never Grow Old」で、15分を超える魂の熱唱を披露するのですが、これはまだ十代だった彼女の公式初リリース曲でもあり、ビッグスタアとなった今でも、その時のピュアな心情を忌憚無く感じさせてしまう凄さがあります。
さらに続くのが、彼女の父親であり、百万ドルの声として説教アルバムを多数出している超有名な伝道師=クレランス・フランクリンのスピーチ! そこでは「アレサの心は、今でも教会を離れていない、どうかそれを信じて、彼女の歌声を」と、ある意味では親バカ系の話をしていますが、ここまでの流れの中では、全くそのとおりの感動が広がります。
そして厳かに熱い「Precious Memories」から終焉のインスト曲「My Sweet Lord」へと続くクライマックスのせつない高揚感は、まさに唯一無二の素晴らしさです。
ということで、実に生々しく溢れ出たソウルがしっかりと記録されています。
ゴスペルという宗教性、そのアクの強さゆえに万人が好む音楽ではないでしょうが、ジャズでもロックでも、とにかく黒人音楽とは切り離せないルーツが、ここに素晴らしすぎるパフォーマンスで残されているのは、それに触れる絶好の機会だと思います。
ちなみに原盤解説によれば、当夜の模様はフィルム撮影も行われたとか!? その発掘も心から願っています。