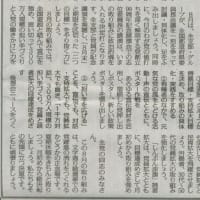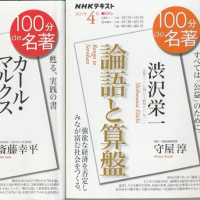日本の農村社会=地方の限界集落化こそ
街中のシャッター通り化こそ
戦後自民党政治の対米従属政治の結末だ!
安倍首相こそ日本の歴史の伝統と文化の破壊者だ!
憲法を押し付けられたなどと吹聴する安倍首相は
歴史の無知を自ら暴露している恥ずべき首相!
高校・大学で日本史を再学習すべきだな?
日本史学習の実態が判るぞ!
9条は幣原首相が提案!憲法は占領軍が押し付けたシロモノではないことが資料で判明!安倍首相真っ青! 2016-08-12 | 安倍式憲法改悪
明治以前の「平和思想」の解明が不足している!
紛争を武力=戦争で解決しない日本の歴史があった!
今、憲法を考える
中日/東京新聞社説 2016/8/29 8:00
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016082902000121.html
マッカーサーの執務室が今も残っている。皇居堀端の第一生命本社ビルの六階。連合国軍総司令部(GHQ)が一九四五年の終戦後、そこに置かれた。執務室は広さ約五十四平方メートル。引き出しのない机と革製の椅子…。背もたれのばねが弱り、今は座ることを許されない。
四六年一月二十四日。当時の首相幣原喜重郎は正午にGHQを訪れた。年末から年始にかけ肺炎で伏せっていたが、米国から新薬のペニシリンをもらい全快した。そのお礼という口実をもって、一人で訪問したのである。
お礼を述べた後、幣原は当惑顔をし、何かをためらっている様子だった。最高司令官のマッカーサーが「意見を述べるのに少しも遠慮する必要はない」と促すと、幣原は口を開いた。
何と「戦争放棄」の条項を新憲法に入れる提案をし始めたのだ。日本が軍隊を持たないということも…。「マッカーサー回想記」の記述だ。こう続く。
<私は腰が抜けるほどおどろいた。(中略)この時ばかりは息もとまらんばかりだった。戦争を国際間の紛争解決には時代遅れの手段として廃止することは、私が長年情熱を傾けてきた夢だった>
二人の会談は三時間に及んだ。マッカーサーは後に米国議会上院でも同じ趣旨の証言をした。
また五七年につくられた憲法調査会会長の高柳賢三がマッカーサーに書簡を出したことがある。戦争放棄はどちら側から出た考えなのかと−。
五八年十二月に返信があった。その書簡でもマッカーサーはやはり幣原による提案だと書いていた。今年になって、堀尾輝久東大名誉教授が見つけた新史料である。こう綴(つづ)られている。
<提案に驚きましたが、心から賛成であると言うと、首相は、明らかに安どの表情を示され、わたくしを感動させました>
幣原側にも史料がある。五一年に亡くなる十日ほど前に秘書官だった元岐阜県知事平野三郎に東京・世田谷の自宅で語った文書である。その「平野文書」が国会図書館憲政資料室に残る。
<風邪をひいて寝込んだ。僕が決心をしたのはその時である。それに僕には天皇制を維持するという重大な使命があった><天皇の人間化と戦争放棄を同時に提案することを僕は考えた>
オーストラリアなどは日本の再軍備を恐れるのであって、天皇制を問題にしているのではない、という幣原の計算があった。戦争放棄をすれば、天皇制を存続できると考えたのだ。この二つは密接に絡み合っていた。そして、マッカーサーと三時間かけて語り合ったのである。
<第九条の永久的な規定ということには彼も驚いていたようであった。(中略)賢明な元帥は最後には非常に理解して感激した面持ちで僕に握手した程であった><憲法は押しつけられたという形をとった訳であるが、当時の実情としてそういう形でなかったら実際に出来(でき)ることではなかった>
「平野文書」は九条誕生のいきさつを生々しく書き取っている。
むろん、この幣原提案説を否定する見方もある。GHQに示した当初の政府の改正案には「戦争放棄」などひと言もなかったからだ。大日本帝国憲法をわずかに手直しした程度の内容だった。かつ、二人の会談は録音がないから、明白な証拠は存在しない。ただ、会談から十日後に示されたマッカーサー・ノートと呼ばれる憲法改正の三原則には、戦争放棄が入っている。
ドイツの哲学者カントは十八世紀末に「永遠平和のために」で常備軍の全廃を説いた。
第一次大戦後の二八年にはパリで戦争放棄をうたう不戦条約が結ばれた。
実は大正から昭和初期は平和思想の世界的ブームでもあった。軍縮や対英米協調外交をすすめた幣原もまた平和主義者だった。
憲法公布七十年を迎える今年、永田町では「改憲」の言葉が公然と飛び交う。だが、戦争はもうごめんだという国民の気持ちが、この憲法を支え続けたのだ。多くの戦争犠牲者の願いでもあろう。行く末が危ういとき、この憲法はいつでも平和への道しるべとなる。
私たちは憲法精神を守る言論に立つ。戦後の平和な社会は、この高い理想があってこそ築かれたからだ。一度、失えば平和憲法は二度と国民の手に戻らない。
読者のみなさんとともに、今、あらためて憲法を考えたい。(引用ここまで)
山室信一「憲法9条の思想水脈」 2007-06-28
http://loisir-space.hatenablog.com/entry/20070628/p2
この本で山室信一京都大学教授は、欧州におけるサン・ピエール、ルソー、カント、そして、国内でも幕末・明治を生きた横井小楠、植木枝盛などまで遡って、9条の源流を見出そうとされていますが、極めて画期的な試みといえます。
それは、9条そのものの源流というよりも、むしろ「非戦思想」の足跡をたどったものという感じです。もちろん、そうした「非戦思想」が9条の成立に直ちに結びつくというわけではありませんが、他方で、9条が終戦直後の短時間において全くの偶然によって出来上がったものではなく、そこまで辿り着くためには、長い思想水脈が横たわっており、それが9条とは全く無関係ではないのだということもこの本から理解することができます。こうした「非戦思想」と9条との結びつきを論証しようとする山室教授の熱意には全く脱帽です。
[書籍] 山室信一『憲法9条の思想水脈』(朝日新聞社、2007年)
http://d.hatena.ne.jp/mahounofuefuki/20080506/1210074077
刊行以来早く読まねばと思いつつ放置してしまい、憲法記念日に合わせてようやく読んだ。書題の通り日本国憲法第9条の思想的源流を探った本。明示してはいないが、現憲法を戦勝国による一方的武装解除の下での「おしつけ」であるという見方への批判になっている。山室の著作にはその知性に裏打ちされた実証性と視野の広い複眼的思考にいつも感服するが、この本も例外でない。
本書は憲法9条の基軸を次の5点に整理する。1)戦争放棄・軍備撤廃、2)国際協調、3)国民主権、4)平和的生存権、5)非戦。これらの基軸はいずれも唐突に現れたものではなく、長い歴史的前提があることを明らかにしている。
第1に、前近代ヨーロッパの平和構想。サン=ピエール、ルソー、カントの平和論に着目。これらが道義的正戦論や無差別戦争論や勢力均衡論を克服していった。
第2に、幕末・明治維新期の平和論。横井小楠(儒教思想に基づく反省的戦争廃止論)、小野梓(世界政府構想)、中村正直(国際法の強化による世界平和論)、植木枝盛(「無上政法論」)、中江兆民(常備軍撤廃論)。これらはヨーロッパの平和論の影響を受けつつ、当時の国際環境の現実を批判的に分析した上で、平和主義実現の道を模索した。特に植木→鈴木安蔵→憲法研究会→GHQ案の系譜は重要。
第3に、日清・日露戦争期の非戦論・反戦論。トルストイの影響の大きさを強調する。北村透谷→日本平和会。社会民主党(日本最初の社会主義政党)の軍備撤廃綱領。丸山幹治(「武装平和」批判)。田中正造(「無戦主義」)。幸徳秋水、堺利彦、安部磯雄、内村鑑三らの非戦論と小国主義。日露戦争以前はある程度の社会的支持基盤があった。
第4に、第1次世界大戦後の戦争違法化運動・体制。大戦前のハーグ平和会議が先駆。国際連盟と不戦条約。特に不戦条約は、アメリカのレヴィンソンやデューイらによる戦争非合法化運動による世論の盛り上がりが引き金になったこと、後の日本占領に関わる人々がこの動きを体験したことの意味を重視している。
第5に、大正デモクラシー後の国際協調論と非戦論の復活。外交官や法学者らの国際連盟協会。アンリ・バルビュスのクラルテ運動→小牧近江→『種蒔く人』→初期プロレタリア文学の系譜。婦人参政権運動の平和論(特に野見山不二子の軍備縮小・撤廃論)。水野広徳や鹽津誠作の軍備撤廃論(特に鹽津は憲法改正による軍備撤廃を提唱)は9条の直接の源流となる。
以上のような潮流が戦後の日本国憲法を用意した。また占領下における憲法改正作業において占領軍は自由裁量を持っていたわけでなく、その占領自体がハーグ陸戦法規(占領地の既成法令の尊重義務)とポツダム宣言の制約を受けていたこと、あくまで「日本国民」が自発的に憲法を選び取ったという体裁に配慮したこと(憲法制定議会を特設せず帝国議会が審議し、GHQ案=政府案が議会で修正され、明治憲法の改正手続に従った)も指摘している。
最後に9条2項のいわゆる「芦田修正」については、芦田の日記や議会の速記録から「虚構」であると推定、少なくとも憲法制定時には自衛のための戦力保持を認めるという意思は読み取れないとする。
日本国憲法9条は恒久平和実現を模索した長年の営為の結晶であり、近代日本の歴史には終始平和主義が伏流として存在したことがよくわかる良書である。注釈では日本国憲法より古い外国の憲法における戦争制限条項もいくつか紹介されており、日本国憲法の戦力放棄条項が決して突拍子もないものではないこともわかる。9条についての基本的入門書の役割も果たしており、憲法を論じるにあたって必読の書と言えよう。(引用ここまで)