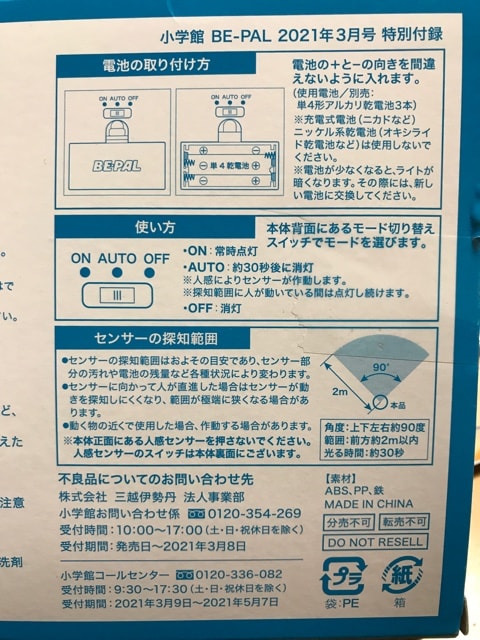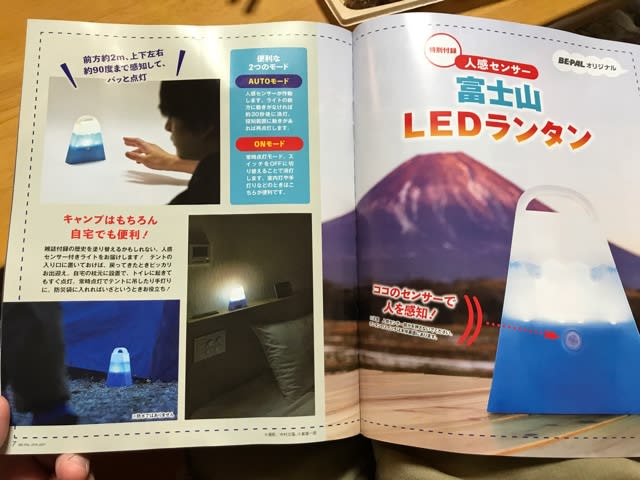補装具の新しい基準についての意見募集が始まりました。
こうした手続きを経て、補装具の支給基準は決まっていきます。
変えていくには、地道に当事者や当事者家族が声を上げていくしかありません。
どうか、みなさま。
幼児、小児について、
走るための補装具、水中歩行のための補装具が、子ども園から小中学校にかけて必要になることを、意見として出していただけたら。
チリも積もれば山となります。
どうか、力を貸してください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000214463
3月11日必着までが締め切り
以下、ホームページより
補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の 一部を改正する件(案)の御意見の募集について
令和3年2月10日 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部
補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の一部を改正す る件(案)について、下記のとおり、御意見を求めます。
1.御意見募集期間 令和3年2月10日(水)~令和3年3月11日(木)(必着)
2.御意見募集対象
補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の一部を改
正する件(案)について(概要)
3.御意見の提出方法 御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してくださ
い(様式は自由)。その際、件名に「補装具の種目、購入等に要する費用の
額の算定等に関する基準の一部を改正する件(案)に関する意見」と明記し
て御提出ください。電話での受付はできませんので御了承ください。
(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合 「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の意見提出フォームへ のボタンをクリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提
出を行ってください。 (2) 郵送する場合
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部企画課自立支援振興室宛て (3) FAXの場合
FAX番号:03-3503-1237
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部企画課自立支援振興室宛て
4.御意見の提出上の注意 提出していただく御意見は日本語に限ります。また、個人の場合は、氏名・
住所等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地を記入してください(御意 見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために使用します。)。お寄 せいただいた御意見について、個別の回答はいたしかねます。また、氏名及び 住所その他の連絡先を除き、公表させていただくことがありますので、あらか じめ御了承願います。
<概要>
補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の一部を改正
する件(案)について(概要)
1.改正の趣旨
補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 528 号)について、補装具の製作に必要な素材等の一 般市価の動向等に対応するため、基準額の改定を行うとともに、現状の実 態に合わせた型式の追加その他所要の改正を行う。
2.改正の概要
(1)基準額の改定
・補装具費の基準額に係る実態調査の結果を踏まえ、所要の改定を行う。
(2)型式の追加 ・購入及び修理基準の殻構造義肢(義手)に「電動式」を追加する。 ・購入及び修理基準の殻・骨格構造義肢の下腿義足に「TSB 式」を追加する。
(3)用語の整理
・JIS T 9267(福祉用具-歩行補助具-多脚つえ)が制定されたことに伴
い、歩行補助つえの「多点杖」を「多脚つえ」に改称する。
(4)その他
・所要の改正を行う。
※詳細な改正内容は別添のとおり。
3.根拠規定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)第5条第 25 項及び第 76 条第2項
4.適用期日等
告 示 日 令和3年3月下旬(予定) 適用期日 令和3年4月1日



ドライフルーツにチョコバナナキューブをトッピングにしたら、激うま。



山間部、それも過疎地の除雪問題が深刻化している。
対策について、各所で検討されてはいるが、なかなかうまくいかない。
なぜだろうか。
ちょっと聞かれたこともあり、考えてみた。
まず、除雪に関しては、雪が降る前から準備する必要がある。だからして、準備していたが雪があまり降らなかったと言う場合にも、かかった費用は払う必要がある。
雪が降りそうだなと言うときに、自律的に動いて、雪が降り始める前に除雪車を分散配置して待機するためには、実務を誰かに任せて、出来形払いをする仕組みが有効だ。通常の役場の発注では、降るかどうかもわからない雪のために、空振りでいいから頼むと言うことはできない。
また、長さに応じた台数の除雪車の保有、メンテナンス、点検、更新費用も、雪がたとえ数年降らなくても必要経費として割り切らなければならない。
除雪作業をする人材の確保も大切。
その人にも生活がある。ゆきがたまたま全く降らなかったからといって、その人が暮らしていけなければ、人材はそこには根付かない。安定的に一定の仕事があるような組み合わせで仕事を頼む工夫も必要だろう。
除雪にかかる費用の積算についても、問題だ。国が定めた積算基準をそのまま使い、補正だけして積算しても、見合わない。もちろん空振りにはお金は払えない。
それでは赤字になるに決まっている。
過疎地のそんな仕事、一体誰がやってくれるだろうか。
一つの案を提示してみる。
除雪車を購入して、点検しメンテナンスして、更新することを考えると、年刻みでやるは人が変わるのは都合が悪い。せっかく買った除雪車が無駄になる。でも、役場では除雪車を財産にはしたく無い。
そうなると、出てくるのが複数年契約という考え方だ。
例えば15年契約とかを考えてみる。
加えて、準備に要した経費は場合分けをして、事後申告で支払えるように単価を細かく設定し、出来形払いとする。除雪車を分散して待機するための仮設事務所や土地の確保も考慮に入れる。
また、雪が降らなくても、準備自体がなくても、年間の最低支払額を決める。
あまりに何もしなくて支払うのが問題なら、草刈りやパトロール、修繕なんかを単価設定して組み合わせて、年間最低支払額まで毎年仕事を頼むような契約にすればいいかもしれない。
仕組み的には協定の方が馴染みやすいかもしれない。どうだろうか。
15年間契約してもらえるなら、機械を買っても無駄にはならない。
安定して生活できるだけのお金がもらえるなら、過疎地に住んででもやってくれる人はいると思う。
あとはね。
協定の内容の吟味と、単価設定をいかに実情に合わせていくか。その相手の決定プロセスも大切かな。
そうしたことを、過疎地における役場単位で自律的に仕組みづくりから始めるのは無理がありすぎる。
だからして国がそうした研究会を立ち上げて、メンテナンス会議なるものを開催し始めているが、まだ形になるのは少し先になりそうだ。
やはり、村役場にもそうしたことを考えられる土木技術者が必要なのではないか。
つまり、やはりそこにいきつくわけで。
ないがしろにされまくっている土木職公務員。役場では事務職や他の技術職より、なぜか格下であるのが当たり前の土木職公務員。小さな役場では不要とされて、雇われてもいない土木職公務員。
そんな待遇では、そりゃ解決策もでないよね。
なんて、愚痴でしかないな。(^^)
追伸
わかりにくければ、
過疎地にお医者さんを呼ぶときの話を考えてみましょう。
住むところ込みで診療所も用意して、もちろん生活も保証して、長い間いてもらうためになんとかして環境を整えて、誰か来てくれませんか となりますよね。
道路の管理も一緒かなと。
道路のお医者さんを招く発想。
これがまあ、多分必要なのでは無いかなと。
ついでに言うと、過疎手当も医師にはあったりしますよね。(^ ^)