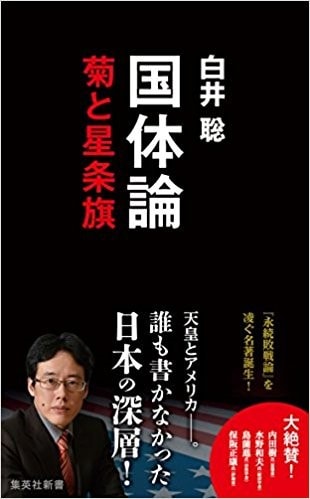しばらく前に(正月明けの頃だった)房総半島の館山に行った。東京から館山までは、以前はJR内房線で行ったが、今ではバスが主流になっている。わたしもバスで行った。なんの変哲もない一泊旅行だったが、心に残っていることがあるので、簡単に旅行記を。
バスが東京湾アクアラインを通って千葉県に入ると、のどかな山里風景の中を走るようになる。しばらくすると鋸南町に入った。屋根にブルーシートをかぶせた民家が目立つ。昨年の台風15号と19号の被害だろう。復旧が遅れていることは新聞等で報道されているが、それを目の当たりにすると、「あれから何か月もたつのに‥」と胸が痛む。気のせいか、ブルーシートをかぶせた民家は、ポツンポツンと点在するのではなく、ある場所に固まっているように見える。そんな場所が何か所もある。地形とか風向きとか、何か原因があるのだろうか。
宿に着いてフロントの人に「去年は大変でしたね」と話しかけると、「そうなんです。うちもガラスが何枚か割れました。でも、それ以上に停電が続いたのが大変でした」と。わたしも当時その宿のホームページで休業が続いているのを見ていた。停電が原因だった。営業再開になったら早く行こうと思っていたが、体調を崩したので、今頃になった。今はお客さんも戻っているようでホッとした。
その日は東京も暖かい天気だったが、館山は東京よりも2度くらい暖かく、海岸を歩くと気持ちがよかった。高校生くらいの男の子が3人堤防の上で話していた。見渡す限りの海の中で、時間を忘れて話す様子が好ましかった。その男の子たちは日没までいた。写真(↑)はわたしの部屋から夕暮れの海を撮ったもの。写真には写っていないが、男の子たちはまだ堤防にいた。
夕食を終えて部屋に戻ると、東京湾をはさんで三浦半島の灯台がよく見えた。灯台は3基あり、観音崎の灯台、久里浜の灯台、剣崎の灯台だった。それらの灯台が等間隔に並び、暗い海に光を放っていた。船舶の航行を守るその光が力強く、また暖かかった。
翌朝もよく晴れた。窓を開けて潮風を入れた。波の音に癒された。人間が波の音に癒されるのは、何かわけがあるのだろうか。わたしの義父は亡くなる前に「波の音が聞きたい」といった。わたしは波の音のCDを買ってきて聞かせた。義父はその数日後に亡くなった。自宅で亡くなったのでできたことかもしれない。病院だったらできただろうか。
人間も自然界の一部なので、体の奥底に自然のリズムが宿っているのかもしれない。そう思うくらい波の音が体に響いた。
バスが東京湾アクアラインを通って千葉県に入ると、のどかな山里風景の中を走るようになる。しばらくすると鋸南町に入った。屋根にブルーシートをかぶせた民家が目立つ。昨年の台風15号と19号の被害だろう。復旧が遅れていることは新聞等で報道されているが、それを目の当たりにすると、「あれから何か月もたつのに‥」と胸が痛む。気のせいか、ブルーシートをかぶせた民家は、ポツンポツンと点在するのではなく、ある場所に固まっているように見える。そんな場所が何か所もある。地形とか風向きとか、何か原因があるのだろうか。
宿に着いてフロントの人に「去年は大変でしたね」と話しかけると、「そうなんです。うちもガラスが何枚か割れました。でも、それ以上に停電が続いたのが大変でした」と。わたしも当時その宿のホームページで休業が続いているのを見ていた。停電が原因だった。営業再開になったら早く行こうと思っていたが、体調を崩したので、今頃になった。今はお客さんも戻っているようでホッとした。
その日は東京も暖かい天気だったが、館山は東京よりも2度くらい暖かく、海岸を歩くと気持ちがよかった。高校生くらいの男の子が3人堤防の上で話していた。見渡す限りの海の中で、時間を忘れて話す様子が好ましかった。その男の子たちは日没までいた。写真(↑)はわたしの部屋から夕暮れの海を撮ったもの。写真には写っていないが、男の子たちはまだ堤防にいた。
夕食を終えて部屋に戻ると、東京湾をはさんで三浦半島の灯台がよく見えた。灯台は3基あり、観音崎の灯台、久里浜の灯台、剣崎の灯台だった。それらの灯台が等間隔に並び、暗い海に光を放っていた。船舶の航行を守るその光が力強く、また暖かかった。
翌朝もよく晴れた。窓を開けて潮風を入れた。波の音に癒された。人間が波の音に癒されるのは、何かわけがあるのだろうか。わたしの義父は亡くなる前に「波の音が聞きたい」といった。わたしは波の音のCDを買ってきて聞かせた。義父はその数日後に亡くなった。自宅で亡くなったのでできたことかもしれない。病院だったらできただろうか。
人間も自然界の一部なので、体の奥底に自然のリズムが宿っているのかもしれない。そう思うくらい波の音が体に響いた。