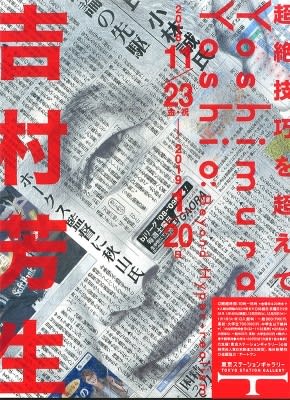高橋悠治(1938‐)の1960年代の作品を中心とした演奏会。今回が第1回で、第2回は2019年10月29日に予定されている。今回は15:30開演と19:00開演の2公演があった。年末なので家にいたかったが、がんばって2公演とも聴いた。聴いてよかったと思う。初めて聴く曲ばかりなので、1回目は音を捉えるだけで精一杯、2回目でやっと音の流れを追うことができた。
プログラムの前半は「クロマモルフⅠ」(1964)、「オペレーション・オイラー」(1968)、「あえかな光」(2018 世界初演)。
その中では「オペレーション・オイラー」がおもしろかった。オーボエ2本の曲。都響の首席奏者・鷹栖美恵子と東響の首席奏者・荒木奏美の演奏。2人は舞台の上手と下手に向かい合って立つ。その位置が1回目と2回目とで入替っていた。線の太い音の鷹栖と細い音の荒木とでは個性のちがいがあり、それが曲の印象を変えた。わたしは2回目のほうがおもしろかった。
「あえかな光」では木管(Fl.Cl)、金管(Tr.Tb)、打楽器(Vib)、弦(Cb)が舞台の前面に並び(各1人)、ヴァイオリン(4人)とチェロ(4人)が後方に並ぶ。前面の奏者が音楽を主導し、後方の奏者は微かな背景を構成する。通常のオーケストラを逆転した作品。
プログラム後半は「6つの要素」(1964)、「さ」(1999)、「歌垣」(1971)。
「6つの要素」と「さ」は、1回目のときにもっとも惹かれた曲だ。「6つの要素」は4人のヴァイオリン奏者のための曲で、ミニマル・ミュージックの発想を取り入れているかもしれない。周防亮介と伊藤亜美の強い個性が光った。
「さ」はホルンの独奏曲。ホルン奏者はまず舞台の下手の奥の椅子に腰かけて演奏し、次に中央に移動して立奏し、次に上手に置かれたピアノの前に移動して演奏する。ピアノの蓋は開いていて、ホルンの音で振動する。ホルン独奏はN響の首席奏者・福川伸陽。たいへんなヴィルトゥオーソだ。ヴィルトゥオジティに背を向けたように見える近年の高橋悠治だが、本作は例外かもしれない。
「歌垣」はピアノと30人の奏者のための曲。管理された偶然性の音楽なのだろう、1回目と2回目とでは曲の出だしがちがった。ピアノ・パートはトリルが中心の音楽で、そのトリルが狂おしく駆け巡り、また沈静する。ピアノは黒田亜樹、指揮は杉山洋一。演奏会全体の企画・主催も杉山洋一。
(2018.12.29.東京オペラシティリサイタルホール)
プログラムの前半は「クロマモルフⅠ」(1964)、「オペレーション・オイラー」(1968)、「あえかな光」(2018 世界初演)。
その中では「オペレーション・オイラー」がおもしろかった。オーボエ2本の曲。都響の首席奏者・鷹栖美恵子と東響の首席奏者・荒木奏美の演奏。2人は舞台の上手と下手に向かい合って立つ。その位置が1回目と2回目とで入替っていた。線の太い音の鷹栖と細い音の荒木とでは個性のちがいがあり、それが曲の印象を変えた。わたしは2回目のほうがおもしろかった。
「あえかな光」では木管(Fl.Cl)、金管(Tr.Tb)、打楽器(Vib)、弦(Cb)が舞台の前面に並び(各1人)、ヴァイオリン(4人)とチェロ(4人)が後方に並ぶ。前面の奏者が音楽を主導し、後方の奏者は微かな背景を構成する。通常のオーケストラを逆転した作品。
プログラム後半は「6つの要素」(1964)、「さ」(1999)、「歌垣」(1971)。
「6つの要素」と「さ」は、1回目のときにもっとも惹かれた曲だ。「6つの要素」は4人のヴァイオリン奏者のための曲で、ミニマル・ミュージックの発想を取り入れているかもしれない。周防亮介と伊藤亜美の強い個性が光った。
「さ」はホルンの独奏曲。ホルン奏者はまず舞台の下手の奥の椅子に腰かけて演奏し、次に中央に移動して立奏し、次に上手に置かれたピアノの前に移動して演奏する。ピアノの蓋は開いていて、ホルンの音で振動する。ホルン独奏はN響の首席奏者・福川伸陽。たいへんなヴィルトゥオーソだ。ヴィルトゥオジティに背を向けたように見える近年の高橋悠治だが、本作は例外かもしれない。
「歌垣」はピアノと30人の奏者のための曲。管理された偶然性の音楽なのだろう、1回目と2回目とでは曲の出だしがちがった。ピアノ・パートはトリルが中心の音楽で、そのトリルが狂おしく駆け巡り、また沈静する。ピアノは黒田亜樹、指揮は杉山洋一。演奏会全体の企画・主催も杉山洋一。
(2018.12.29.東京オペラシティリサイタルホール)