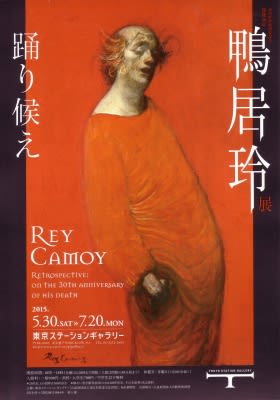鈴木雅明率いるバッハ・コレギウム・ジャパンのバッハの「ミサ曲ロ短調」。これはもう聴く前からハイレベルの演奏が期待されるわけだが、その期待がきちんとクリアーされる、その光景を見守るような演奏会だった。
冒頭、キリエの合唱は、音が軋むような、硬く緊張したハーモニーで開始された。その後、大河のように続く対位法の流れは沈痛だが、淀みがない。クリステ・エレイソンに入ると、ソプラノ2重唱の第2ソプラノが引っこみ気味に聴こえた。キリエ・エレイソンに戻ると、合唱が一段と確信をもったハーモニーを響かせた。
と、そんな具合に、演奏の流れに乗って、この演奏の――そしてこの音楽の――すべてを受け止めようと耳を傾けた。もちろん‘すべてを受け止める’ことなどできないが、あたうかぎり虚心に耳を傾けた。
グロリアに入って、第7曲グラティアスの合唱――全曲の最後に再び登場する音楽だ――、そのハーモニーの透明さ、静けさ、‘塵一つない’清澄さに胸をうたれた。合唱の各声部がどこまでも果てしなく広がっていくようだった。
グロリアを締めくくる第12曲クム・サンクト・スピリトの華やかさに胸がおどった。3本のトランペットが鳴り響き、喜びがあふれた。すべてが解き放たれ、なんの束縛もない。音楽にのみ可能な解放感だ。
休憩後、ニケーア信経(クレド)が始まると、ダイナミックレンジが一段と広がり、音にはかっちりした芯を感じるようになった。第16曲エト・インカルナトスでの暗いハーモニーへの転換、続く第17曲クルチフィクスでの悲痛なハーモニー、ともに適確な表現だった。
最後の一連の流れ――サンクトゥス、オザンナ、ベネディクトゥス、オザンナ、アニュス・デイ、ドナ・ノビス・パーチェムと続く部分――は、わたしの大好きなところだ。どこをとっても申し分のない演奏で、深く満たされた。
全体に透明な、そして繊細な演奏だった。絹のような感触の演奏。わたしたちはその音の空間で楽々と呼吸できる。快い微風が吹いているようだ。どこかに日本的な感性が感じられた。世界的に通用し、高い評価を受けている団体だが、それとは矛盾せずに、日本的なホスピタリティが同居している。今回とくにそれを感じた。
独唱陣ではカウンターテナーのロビン・ブレイズの美しい高音と、テノールの櫻田亮のしっかりした歌唱が印象に残った。
(2015.7.28.サントリーホール)
冒頭、キリエの合唱は、音が軋むような、硬く緊張したハーモニーで開始された。その後、大河のように続く対位法の流れは沈痛だが、淀みがない。クリステ・エレイソンに入ると、ソプラノ2重唱の第2ソプラノが引っこみ気味に聴こえた。キリエ・エレイソンに戻ると、合唱が一段と確信をもったハーモニーを響かせた。
と、そんな具合に、演奏の流れに乗って、この演奏の――そしてこの音楽の――すべてを受け止めようと耳を傾けた。もちろん‘すべてを受け止める’ことなどできないが、あたうかぎり虚心に耳を傾けた。
グロリアに入って、第7曲グラティアスの合唱――全曲の最後に再び登場する音楽だ――、そのハーモニーの透明さ、静けさ、‘塵一つない’清澄さに胸をうたれた。合唱の各声部がどこまでも果てしなく広がっていくようだった。
グロリアを締めくくる第12曲クム・サンクト・スピリトの華やかさに胸がおどった。3本のトランペットが鳴り響き、喜びがあふれた。すべてが解き放たれ、なんの束縛もない。音楽にのみ可能な解放感だ。
休憩後、ニケーア信経(クレド)が始まると、ダイナミックレンジが一段と広がり、音にはかっちりした芯を感じるようになった。第16曲エト・インカルナトスでの暗いハーモニーへの転換、続く第17曲クルチフィクスでの悲痛なハーモニー、ともに適確な表現だった。
最後の一連の流れ――サンクトゥス、オザンナ、ベネディクトゥス、オザンナ、アニュス・デイ、ドナ・ノビス・パーチェムと続く部分――は、わたしの大好きなところだ。どこをとっても申し分のない演奏で、深く満たされた。
全体に透明な、そして繊細な演奏だった。絹のような感触の演奏。わたしたちはその音の空間で楽々と呼吸できる。快い微風が吹いているようだ。どこかに日本的な感性が感じられた。世界的に通用し、高い評価を受けている団体だが、それとは矛盾せずに、日本的なホスピタリティが同居している。今回とくにそれを感じた。
独唱陣ではカウンターテナーのロビン・ブレイズの美しい高音と、テノールの櫻田亮のしっかりした歌唱が印象に残った。
(2015.7.28.サントリーホール)