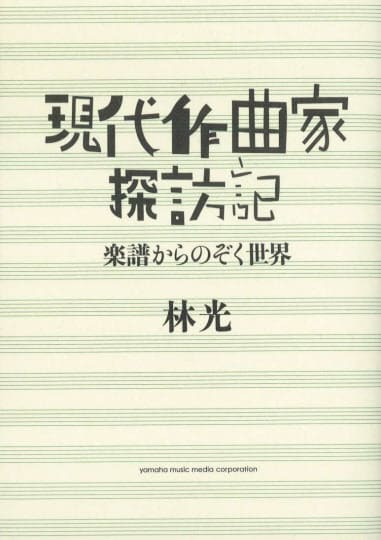今年11月に上演されるアリベルト・ライマン(1936‐)のオペラ「リア」に先立って、細川俊夫、長木誠司の両氏によるトークセッションが開催された。標題は「現代オペラの挑戦~シェイクスピア戯曲『リア王』のオペラ化をめぐって~」。司会は高島勲。
去年はライマンのオペラ「メデア」が上演された。そのときもシンポジウムが開かれた。長木誠司、下野竜也、片山杜秀、高橋宣也、野平一郎、高島勲という賑やかな顔ぶれだった。なにが飛び出すかわからない面白さがあった。今回はきちんと下準備がされていたので、その意味ではスリルがなかった。
約2時間にわたるトークセッションの全貌を伝える力はないが、印象に残った点をメモしておきたい(ただし、わたしが理解した範囲で表現を置き換えている場合がある。文責はすべてわたしに。)。
1)「リア王」のオペラ化は、20世紀ではライマン、細川俊夫(鈴木忠志の脚色による)以外に、アレクサンダー・ゲール(1932‐)とアウリス・サリネン(1935‐)がやっている。
2)ヴェルディも「リア王」のオペラ化を念願していたが、果たせなかった(草稿がどこかに眠っているはずだ。)。女声3人の登場(ゴネリル、リーガン、コーディリア)が異例だったからでもあるが、もう一つは、嵐の場面を書けなかったからでもあるだろう。ヴェルディにとって自然は外にあった。一方、自分(細川俊夫)の場合は能の伝統があり、内面の世界が外在化することは普通だ。また、ライマンの場合は、自然の心理的な表現ができる時代になっていた。
3)キース・ウォーナーがフランクフルト歌劇場でこの作品を演出したとき、プログラムにこう書いていた、「『リア王』は演劇史上初めて神が出てこない作品だ」と。
4)ライマンの「リア」ではオーケストラの間奏曲に重要な役割がある。それはドビュッシーの「ペレアスとメリザンド」~ベルクの「ヴォツェック」につながるものだ。
5)今回エドガーを歌うのは藤木大地という有望なカウンターテナーだ。カストラートの最後の一人が20世紀初めまで生きていたが、その後途絶えた。1950年代からカウンターテナーが出てきた。
なお、会場では、本年4月にこの作品がスェーデンのマルメで上演された際に、ヨーロッパにいた下野竜也がライマンを訪れて、助言を受けている様子が放映された。演奏家の努力はすごい。
(2013.5.25.日生劇場大会議室)
去年はライマンのオペラ「メデア」が上演された。そのときもシンポジウムが開かれた。長木誠司、下野竜也、片山杜秀、高橋宣也、野平一郎、高島勲という賑やかな顔ぶれだった。なにが飛び出すかわからない面白さがあった。今回はきちんと下準備がされていたので、その意味ではスリルがなかった。
約2時間にわたるトークセッションの全貌を伝える力はないが、印象に残った点をメモしておきたい(ただし、わたしが理解した範囲で表現を置き換えている場合がある。文責はすべてわたしに。)。
1)「リア王」のオペラ化は、20世紀ではライマン、細川俊夫(鈴木忠志の脚色による)以外に、アレクサンダー・ゲール(1932‐)とアウリス・サリネン(1935‐)がやっている。
2)ヴェルディも「リア王」のオペラ化を念願していたが、果たせなかった(草稿がどこかに眠っているはずだ。)。女声3人の登場(ゴネリル、リーガン、コーディリア)が異例だったからでもあるが、もう一つは、嵐の場面を書けなかったからでもあるだろう。ヴェルディにとって自然は外にあった。一方、自分(細川俊夫)の場合は能の伝統があり、内面の世界が外在化することは普通だ。また、ライマンの場合は、自然の心理的な表現ができる時代になっていた。
3)キース・ウォーナーがフランクフルト歌劇場でこの作品を演出したとき、プログラムにこう書いていた、「『リア王』は演劇史上初めて神が出てこない作品だ」と。
4)ライマンの「リア」ではオーケストラの間奏曲に重要な役割がある。それはドビュッシーの「ペレアスとメリザンド」~ベルクの「ヴォツェック」につながるものだ。
5)今回エドガーを歌うのは藤木大地という有望なカウンターテナーだ。カストラートの最後の一人が20世紀初めまで生きていたが、その後途絶えた。1950年代からカウンターテナーが出てきた。
なお、会場では、本年4月にこの作品がスェーデンのマルメで上演された際に、ヨーロッパにいた下野竜也がライマンを訪れて、助言を受けている様子が放映された。演奏家の努力はすごい。
(2013.5.25.日生劇場大会議室)