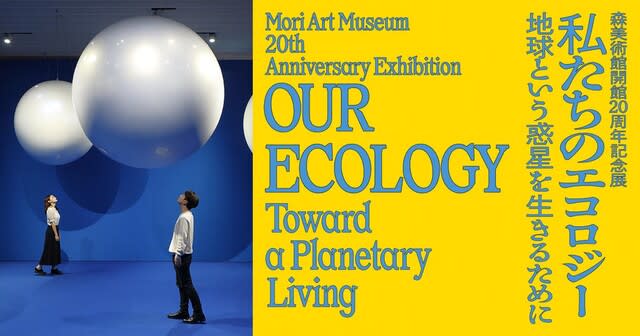東京ステーションギャラリーで「空想旅行案内人 ジャン=ミッシェル・フォロン」展が開かれている。チラシ(↑)に惹かれて行ってみた。
チラシに使われた作品は「月世界旅行」(1981 水彩)だ。カバンが三日月なのがユーモラスだ。帽子をかぶった男はリトル・ハット・マン。フォロンの作品になくてはならないキャラクターだ。多くの作品に登場する。フォロンの分身だ。本展の表題にある「空想旅行案内人」とはフォロンの名刺にあった言葉だそうだ。フォロンの自己イメージであるとともに、リトル・ハット・マンのことでもあるだろう。
「月世界旅行」は色彩の淡さと透明感が印象的だ。それがフォロンの特徴だ。加えて、全体にただようユーモア。押しつけがましさは一切ない。飄々として軽妙だ。鑑賞者は身構えることなくスッと作品に入って行ける。
だが、たんにそれだけのアーティストかというと、そうではない。たとえば「もっと、もっと」(1983 墨、カラーインク、水彩、色鉛筆、コラージュ)は、大きなガラス製の水槽を描く。中にいるのは魚ではなくて、ミサイルだ。水槽の左右から手が伸びる。左からはアメリカの手が、右からソ連の手が。それぞれの手は水槽の中に餌を入れる。もっと、もっとミサイルが増えるようにと。
そのような問題意識があったからだろう、フォロンはアムネスティ・インターナショナルの依頼に応じて、「世界人権宣言」に挿絵を描いた(1988 水彩)。第二次世界大戦の反省に立ち、人権を高らかに謳い上げた「世界人権宣言」だが、フォロンの描いた挿絵は、理想の表現だけではなく、理想とは裏腹の現実を描いたものもあった。たとえば第3条「すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。」につけた挿絵は、3本の絞首台が並び、3人の人間が首を吊られる光景だ。そこに一羽の白い鳥が飛ぶ。
「世界人権宣言」は序文と30の条文からなる。フォロンが挿絵を描いたのは、序文と18の条文だけだ。残りの12の条文には挿絵をつけなかった。なぜだろう。もともと30の条文すべてに挿絵をつけるつもりはなかったのか。それとも理想と現実とのギャップに行き詰まったのか。
フォロンは1934年にベルギーで生まれ、長らくパリの近郊に住み、2005年にモナコで亡くなった。挿絵、ポスターなどの多方面で活躍した。わたしは本展では1980年代以降の水彩画に惹かれた。たとえば「ひとり」(1987 水彩)という作品。蜃気楼のように浮かぶ山や高層ビルを前にリトル・ハット・マンが佇む。淡く透明な美しさに言葉を失う。
(2024.8.8.東京ステーションギャラリー)
チラシに使われた作品は「月世界旅行」(1981 水彩)だ。カバンが三日月なのがユーモラスだ。帽子をかぶった男はリトル・ハット・マン。フォロンの作品になくてはならないキャラクターだ。多くの作品に登場する。フォロンの分身だ。本展の表題にある「空想旅行案内人」とはフォロンの名刺にあった言葉だそうだ。フォロンの自己イメージであるとともに、リトル・ハット・マンのことでもあるだろう。
「月世界旅行」は色彩の淡さと透明感が印象的だ。それがフォロンの特徴だ。加えて、全体にただようユーモア。押しつけがましさは一切ない。飄々として軽妙だ。鑑賞者は身構えることなくスッと作品に入って行ける。
だが、たんにそれだけのアーティストかというと、そうではない。たとえば「もっと、もっと」(1983 墨、カラーインク、水彩、色鉛筆、コラージュ)は、大きなガラス製の水槽を描く。中にいるのは魚ではなくて、ミサイルだ。水槽の左右から手が伸びる。左からはアメリカの手が、右からソ連の手が。それぞれの手は水槽の中に餌を入れる。もっと、もっとミサイルが増えるようにと。
そのような問題意識があったからだろう、フォロンはアムネスティ・インターナショナルの依頼に応じて、「世界人権宣言」に挿絵を描いた(1988 水彩)。第二次世界大戦の反省に立ち、人権を高らかに謳い上げた「世界人権宣言」だが、フォロンの描いた挿絵は、理想の表現だけではなく、理想とは裏腹の現実を描いたものもあった。たとえば第3条「すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。」につけた挿絵は、3本の絞首台が並び、3人の人間が首を吊られる光景だ。そこに一羽の白い鳥が飛ぶ。
「世界人権宣言」は序文と30の条文からなる。フォロンが挿絵を描いたのは、序文と18の条文だけだ。残りの12の条文には挿絵をつけなかった。なぜだろう。もともと30の条文すべてに挿絵をつけるつもりはなかったのか。それとも理想と現実とのギャップに行き詰まったのか。
フォロンは1934年にベルギーで生まれ、長らくパリの近郊に住み、2005年にモナコで亡くなった。挿絵、ポスターなどの多方面で活躍した。わたしは本展では1980年代以降の水彩画に惹かれた。たとえば「ひとり」(1987 水彩)という作品。蜃気楼のように浮かぶ山や高層ビルを前にリトル・ハット・マンが佇む。淡く透明な美しさに言葉を失う。
(2024.8.8.東京ステーションギャラリー)