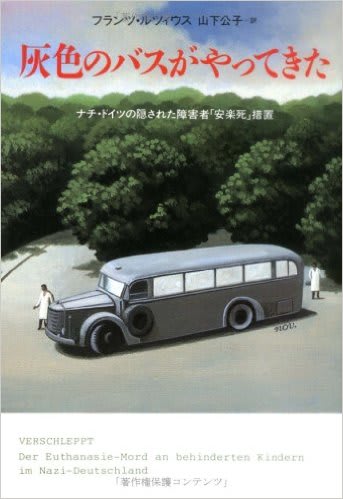今年のMUSIC TOMORROWは手応え十分だった。演奏は下野竜也指揮のN響。
1曲目は権代敦彦(1965‐)の「Vice Versa―逆も真なり―」(2015)。オーケストラ・アンサンブル金沢の委嘱。音楽監督の井上道義から詳細な「注文書」が付されたそうだ。どんな内容だったか、プレトークで作曲者が読んで聞かせてくれた。微に入り細に入り、詳細を極め、しつこく、しかも奇抜なアイディアを含んでいる。「却下」したアイディアもあったが、基本的には井上道義の注文(挑発といった方がよいかもしれない)に応えたとのこと。
痛みを伴うような音楽、自らの傷口に指を突っ込むような音楽、言い換えれば、安穏とした世界に身を置くことを潔しとしない音楽、そんなふうに聴こえた。
2曲目は大胡恵(だいご・けい)(1979‐)の「何を育てているの?」「白いヒヤシンス」(2016)という曲。N響の委嘱。未知の作曲家で、予備知識もなかったが、大変面白かった。今年のMUSIC TOMORROWの大きな収穫だ。
シリアの悲惨な状況が念頭にあったそうだ。日本にいて作曲に打ち込んでいる自分になにができるだろうかと自問自答し、「砂埃の中で瓦礫に触れるように、楽器を通して音に触れ、そこから私なりの前向きな創造をすること」に辿りついた。
不思議な光に満ちた曲。幾筋もの光が多方面から射して、プリズムのように乱反射している曲。たまたま東京ではドキュメンタリー映画「シリア・モナムール」が公開中だが、そこで描かれているシリアの過酷な現実の、その上空ではこういう光の世界があるのだろうか、命を失った人々の魂は、このような光の中を通って天に昇るのだろうか、などと考えた。
わたしは1951年生まれなので、大胡恵は息子の世代だ。もし大胡恵がわたしの息子だったら、異星人を見るような思いがするだろう。わたしがその中で生きてきた音楽とはまったく違う音楽をやっている。でも、その音楽に惹かれる自分を見出すだろう。
3曲目のエイノ・タンベルク(1930‐2010)の「トランペット協奏曲第1番」(1972)では名手セルゲイ・ナカリャコフの演奏を楽しんだ。4曲目の北爪道夫(1948‐)の「地の風景」(2000)でまた‘世代’を考えた。北爪道夫はわたしと同世代。オーケストラの鳴らし方が堂に入っている。滑らかな口調で雄弁だ。
(2016.6.28.東京オペラシティ)
1曲目は権代敦彦(1965‐)の「Vice Versa―逆も真なり―」(2015)。オーケストラ・アンサンブル金沢の委嘱。音楽監督の井上道義から詳細な「注文書」が付されたそうだ。どんな内容だったか、プレトークで作曲者が読んで聞かせてくれた。微に入り細に入り、詳細を極め、しつこく、しかも奇抜なアイディアを含んでいる。「却下」したアイディアもあったが、基本的には井上道義の注文(挑発といった方がよいかもしれない)に応えたとのこと。
痛みを伴うような音楽、自らの傷口に指を突っ込むような音楽、言い換えれば、安穏とした世界に身を置くことを潔しとしない音楽、そんなふうに聴こえた。
2曲目は大胡恵(だいご・けい)(1979‐)の「何を育てているの?」「白いヒヤシンス」(2016)という曲。N響の委嘱。未知の作曲家で、予備知識もなかったが、大変面白かった。今年のMUSIC TOMORROWの大きな収穫だ。
シリアの悲惨な状況が念頭にあったそうだ。日本にいて作曲に打ち込んでいる自分になにができるだろうかと自問自答し、「砂埃の中で瓦礫に触れるように、楽器を通して音に触れ、そこから私なりの前向きな創造をすること」に辿りついた。
不思議な光に満ちた曲。幾筋もの光が多方面から射して、プリズムのように乱反射している曲。たまたま東京ではドキュメンタリー映画「シリア・モナムール」が公開中だが、そこで描かれているシリアの過酷な現実の、その上空ではこういう光の世界があるのだろうか、命を失った人々の魂は、このような光の中を通って天に昇るのだろうか、などと考えた。
わたしは1951年生まれなので、大胡恵は息子の世代だ。もし大胡恵がわたしの息子だったら、異星人を見るような思いがするだろう。わたしがその中で生きてきた音楽とはまったく違う音楽をやっている。でも、その音楽に惹かれる自分を見出すだろう。
3曲目のエイノ・タンベルク(1930‐2010)の「トランペット協奏曲第1番」(1972)では名手セルゲイ・ナカリャコフの演奏を楽しんだ。4曲目の北爪道夫(1948‐)の「地の風景」(2000)でまた‘世代’を考えた。北爪道夫はわたしと同世代。オーケストラの鳴らし方が堂に入っている。滑らかな口調で雄弁だ。
(2016.6.28.東京オペラシティ)