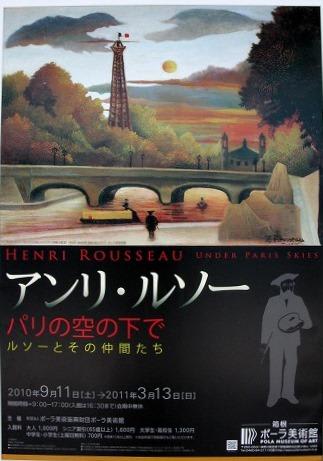日本フィルの1月定期でスティーヴ・ライヒの「管楽器、弦楽器とキーボードのためのヴァリエーション」が演奏された。指揮はシズオ・Z・クワハラさん。同氏は2008年6月の横浜定期に客演したおりには、ジョン・アダムズの「高速機械で早乗りShort Ride in a Fast Machine」を披露してくれた。
演奏会にむけた取り組みがすばらしかった。まずホームページに前島秀国さんの解説を事前公開した。馴染みのない曲に関心をよぶには効果的だ。前島さんはサウンド&ヴィジュアル・ライター。この曲の解説者としては最適の人だ。
次に「公演担当者と一緒に、オーケストラを聴こう 第3弾 ライヒの巻」を掲載した。事務所で何人かが公演担当者とアメリカ音楽をきく様子が書かれていた。あれこれCDをかけながら、ボソボソと交わされる感想が、意外に臨場感があった。
こうして周到に準備された演奏会。土曜日の公演では前島秀国さんのプレトークがあった。いくつかのCDをかけながら、ライヒの音楽を語るもの。ライヒが自分の音楽に影響を与えたと語っているペロタン(12世紀末~13世紀初め、ノートルダム楽派の作曲家)の音楽は、モアレ現象(規則正しい繰返しを重ね合わせたときに生じるズレ)に似た効果が、ライヒをふくむミニマルミュージックのようだった。
またライヒの「三つの物語Three Tales」も面白かった。金床(かなとこ)を叩く一定のリズムが繰り返されるうちに、少しずつ音が加わっていく。ワーグナーの「ラインの黄金」で、ヴォータンが地下のニーベルハイムに下りていく音楽みたいだなと思っていたら、ほんとうにそうだった。この部分は「ニーベルング・ツェッペリンNibelung Zeppelin」というそうだ。笑ってしまった。
さて、いよいよ演奏。CDではきき馴れた曲だが、生できくのは初めて。こうしてコンサートホールできくと、たしかにこれはコンサートホールで通常演奏される音楽とは、全然ちがう原理でできていると感じられた。また指揮のしかたにも注目した。同じ音型が繰り返され、そこに微妙な変化が生じる約21分もの長い間、きちょうめんに拍をとっていた。たしかに、そうしないと、演奏者はどこをやっているのかわからなくなる可能性があるだろう。
この曲の前にはウィリアム・シューマンの「アメリカ祝典序曲」が、後にはストラヴィンスキーの「春の祭典」が演奏された。ともに張りのある豪快な演奏。今のアメリカの価値観の一端にふれる思いだった。
(2011.1.29.サントリーホール)
演奏会にむけた取り組みがすばらしかった。まずホームページに前島秀国さんの解説を事前公開した。馴染みのない曲に関心をよぶには効果的だ。前島さんはサウンド&ヴィジュアル・ライター。この曲の解説者としては最適の人だ。
次に「公演担当者と一緒に、オーケストラを聴こう 第3弾 ライヒの巻」を掲載した。事務所で何人かが公演担当者とアメリカ音楽をきく様子が書かれていた。あれこれCDをかけながら、ボソボソと交わされる感想が、意外に臨場感があった。
こうして周到に準備された演奏会。土曜日の公演では前島秀国さんのプレトークがあった。いくつかのCDをかけながら、ライヒの音楽を語るもの。ライヒが自分の音楽に影響を与えたと語っているペロタン(12世紀末~13世紀初め、ノートルダム楽派の作曲家)の音楽は、モアレ現象(規則正しい繰返しを重ね合わせたときに生じるズレ)に似た効果が、ライヒをふくむミニマルミュージックのようだった。
またライヒの「三つの物語Three Tales」も面白かった。金床(かなとこ)を叩く一定のリズムが繰り返されるうちに、少しずつ音が加わっていく。ワーグナーの「ラインの黄金」で、ヴォータンが地下のニーベルハイムに下りていく音楽みたいだなと思っていたら、ほんとうにそうだった。この部分は「ニーベルング・ツェッペリンNibelung Zeppelin」というそうだ。笑ってしまった。
さて、いよいよ演奏。CDではきき馴れた曲だが、生できくのは初めて。こうしてコンサートホールできくと、たしかにこれはコンサートホールで通常演奏される音楽とは、全然ちがう原理でできていると感じられた。また指揮のしかたにも注目した。同じ音型が繰り返され、そこに微妙な変化が生じる約21分もの長い間、きちょうめんに拍をとっていた。たしかに、そうしないと、演奏者はどこをやっているのかわからなくなる可能性があるだろう。
この曲の前にはウィリアム・シューマンの「アメリカ祝典序曲」が、後にはストラヴィンスキーの「春の祭典」が演奏された。ともに張りのある豪快な演奏。今のアメリカの価値観の一端にふれる思いだった。
(2011.1.29.サントリーホール)