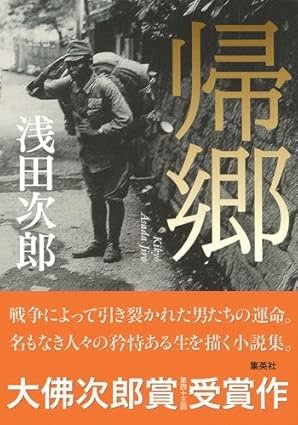サントリーホールサマーフェスティバル2024の最終日。アルディッティ弦楽四重奏団のオーケストラ・プログラム。オーケストラはブラッド・ラブマン指揮の都響。
1曲目は細川俊夫の「フルス(河)~私はあなたに流れ込む河になる~」。音の粒子がすさまじい勢いで飛び交う嵐のような曲だ。弦楽四重奏とオーケストラの境目は相互に侵食し合い、不分明な磁場のような音場を形成する。アルディッティ弦楽四重奏団の演奏と都響の演奏がシャープですばらしかったのはいうまでもないが、指揮のラブマンがこの曲を表面的にではなく、深く理解していることが感じられた。ラブマンは8月23日のマヌリのオーケストラ・ポートレートでも鮮烈な演奏を聴かせた(オーケストラは東響)。大変な実力の持ち主ではないだろうか。
2曲目はクセナキスの「トゥオラケムス」。クセナキスが武満徹の60歳を祝うコンサートのために書いた曲。ファンファーレのような短い曲だ。弦楽器は16型、木管・金管は4管編成と大編成だ(総勢90人が指定されている)。濁りのない明るい音色が印象的だ。
3曲目はクセナキスの「ドクス・オーク」。ヴァイオリン協奏曲だ。ヴァイオリン独奏はアーヴィン・アルディッティ。面白いことに、この曲は「トゥオラケムス」のハープを独奏ヴァイオリンに置き換えただけで、ほとんど同じ編成だ。だがオーケストラから出てくる音はだいぶ違う。不機嫌なダミ声のような音が鳴る。ギリシャ悲劇のコロスのように独奏ヴァイオリンを威嚇する。一方、独奏ヴァイオリンは微分音を交えたグリッサンドを連続する。弱々しくコロスに哀願するかのようだ。
4曲目はマヌリの「メランコリア・フィグーレン」。1曲目の「フルス(河)」と同様に弦楽四重奏とオーケストラのための曲だ。元々はマヌリの「メランコリア:デューラーによせて」という弦楽四重奏曲があり、それを基に作られた曲だそうだ(須藤まりな氏のプログラム・ノートより)。全体は7つの小曲からなり、どの曲もスマートで洗練されている。ドビュッシー~ブーレーズ~マヌリと続く音楽の系譜を思う。
余談だが、デューラーの銅版画「メランコリア」は国立西洋美術館も所蔵している。多くの形態(フィグーレン)が複雑に構成された作品だ。マヌリのこの曲はその細部の音によるイメージ化とも思える。
終演後、マヌリが舞台に上がり、アルディッティ弦楽四重奏団とハグを交わした。今年のサントリーホールサマーフェスティバルは例年にも増して充実していた。テーマ作曲家のマヌリとプロデューサーのアルディッティがうまく絡み合い、車の両輪のように機能した。
(2024.8.29.サントリーホール)
1曲目は細川俊夫の「フルス(河)~私はあなたに流れ込む河になる~」。音の粒子がすさまじい勢いで飛び交う嵐のような曲だ。弦楽四重奏とオーケストラの境目は相互に侵食し合い、不分明な磁場のような音場を形成する。アルディッティ弦楽四重奏団の演奏と都響の演奏がシャープですばらしかったのはいうまでもないが、指揮のラブマンがこの曲を表面的にではなく、深く理解していることが感じられた。ラブマンは8月23日のマヌリのオーケストラ・ポートレートでも鮮烈な演奏を聴かせた(オーケストラは東響)。大変な実力の持ち主ではないだろうか。
2曲目はクセナキスの「トゥオラケムス」。クセナキスが武満徹の60歳を祝うコンサートのために書いた曲。ファンファーレのような短い曲だ。弦楽器は16型、木管・金管は4管編成と大編成だ(総勢90人が指定されている)。濁りのない明るい音色が印象的だ。
3曲目はクセナキスの「ドクス・オーク」。ヴァイオリン協奏曲だ。ヴァイオリン独奏はアーヴィン・アルディッティ。面白いことに、この曲は「トゥオラケムス」のハープを独奏ヴァイオリンに置き換えただけで、ほとんど同じ編成だ。だがオーケストラから出てくる音はだいぶ違う。不機嫌なダミ声のような音が鳴る。ギリシャ悲劇のコロスのように独奏ヴァイオリンを威嚇する。一方、独奏ヴァイオリンは微分音を交えたグリッサンドを連続する。弱々しくコロスに哀願するかのようだ。
4曲目はマヌリの「メランコリア・フィグーレン」。1曲目の「フルス(河)」と同様に弦楽四重奏とオーケストラのための曲だ。元々はマヌリの「メランコリア:デューラーによせて」という弦楽四重奏曲があり、それを基に作られた曲だそうだ(須藤まりな氏のプログラム・ノートより)。全体は7つの小曲からなり、どの曲もスマートで洗練されている。ドビュッシー~ブーレーズ~マヌリと続く音楽の系譜を思う。
余談だが、デューラーの銅版画「メランコリア」は国立西洋美術館も所蔵している。多くの形態(フィグーレン)が複雑に構成された作品だ。マヌリのこの曲はその細部の音によるイメージ化とも思える。
終演後、マヌリが舞台に上がり、アルディッティ弦楽四重奏団とハグを交わした。今年のサントリーホールサマーフェスティバルは例年にも増して充実していた。テーマ作曲家のマヌリとプロデューサーのアルディッティがうまく絡み合い、車の両輪のように機能した。
(2024.8.29.サントリーホール)