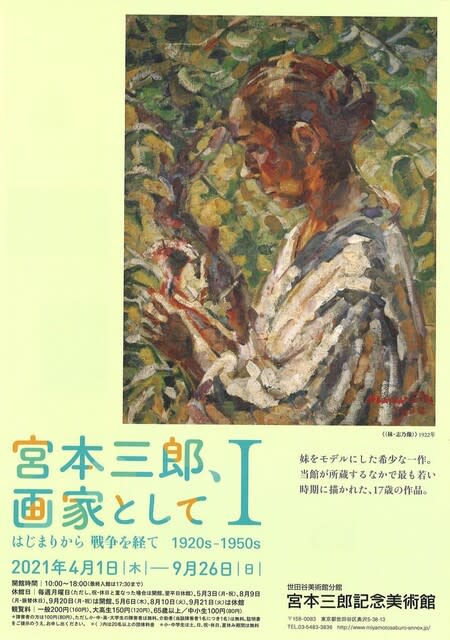サントリーホール・サマーフェスティバルの今年のテーマ作曲、マティアス・ピンチャー(1971‐)の管弦楽作品演奏会。オーケストラは東京交響楽団。
わたしはドイツで2度ピンチャーの指揮するオーケストラ演奏会を聴いたことがある。一度目は2010年にカールスルーエでバーデン州立歌劇場のオーケストラを振った演奏会。二度目は2013年にフランクフルトでhr交響楽団を振った演奏会。とくに二度目は曲がB.A.ツィンマーマンの巨大な作品「ある若い詩人のためのレクイエム」だったので、強烈な印象を受けた。
三度目になる今回は、舞台に登場するピンチャーのタキシード姿を見て(過去2回がどんな服装だったか覚えていないが)、恰幅がよく貫禄が付いたその姿に、見違えるような思いがした。いまではすっかり欧米の音楽界でエスタブリッシュメントの地位を築いた風格が漂っていた。
1曲目はピンチャーが将来を嘱望する若手としてジュリアード音楽院での弟子のマシュー・シュルタイス(1997‐)の「コロンビア、年老いて」(2020)が演奏された。コロンビアとはアメリカ合衆国の雅称だそうだ(プログラム・ノートより)。だからだろうか、冒頭の音型は大航海時代を彷彿とさせる視覚的なイメージを感じさせた。全体に明るい音色で聴きやすい曲だ。
2曲目はピンチャーのチェロとオーケストラのための「目覚め(ウン・デスペルタール)」(2016)。チェロ独奏は岡本侑也。ゆったりした時間の持続は、今フェスティバルで演奏された大アンサンブルのための「初めに(ベレシート)」(2013)やチェロとピアノのための「光の諸相」(2012~15)と共通する。「目覚め」の場合は、チェロの旋律の渋さに対して、オーケストラが意外に色彩的なことに注目した。
3曲目はピンチャーのオーケストラ曲「河(ネハロート)」(2020)の世界初演。委嘱者はサントリーホールの他に、ドレスデンのザクセン州立歌劇場、ロサンゼルス・フィル、パリのフェスティバル・ドートンヌ、ラジオ・フランスと錚々たる名前が並んでいる。曲は「目覚め」とは異なり、劇的緊張に満ち、明暗のコントラストが鮮やかだ。倍音の解析・合成にもとづくスペクトル楽派を消化した世代の傑作ではないかと思った。
4曲目はピンチャーが影響を受けた作曲家としてラヴェルの「スペイン狂詩曲」が演奏された。オーケストラの統率力は、冒頭で書いた2度の経験に照らしても、格段に上がっている。隠れた音型の発見もあった。
(2021.8.27.サントリーホール)
わたしはドイツで2度ピンチャーの指揮するオーケストラ演奏会を聴いたことがある。一度目は2010年にカールスルーエでバーデン州立歌劇場のオーケストラを振った演奏会。二度目は2013年にフランクフルトでhr交響楽団を振った演奏会。とくに二度目は曲がB.A.ツィンマーマンの巨大な作品「ある若い詩人のためのレクイエム」だったので、強烈な印象を受けた。
三度目になる今回は、舞台に登場するピンチャーのタキシード姿を見て(過去2回がどんな服装だったか覚えていないが)、恰幅がよく貫禄が付いたその姿に、見違えるような思いがした。いまではすっかり欧米の音楽界でエスタブリッシュメントの地位を築いた風格が漂っていた。
1曲目はピンチャーが将来を嘱望する若手としてジュリアード音楽院での弟子のマシュー・シュルタイス(1997‐)の「コロンビア、年老いて」(2020)が演奏された。コロンビアとはアメリカ合衆国の雅称だそうだ(プログラム・ノートより)。だからだろうか、冒頭の音型は大航海時代を彷彿とさせる視覚的なイメージを感じさせた。全体に明るい音色で聴きやすい曲だ。
2曲目はピンチャーのチェロとオーケストラのための「目覚め(ウン・デスペルタール)」(2016)。チェロ独奏は岡本侑也。ゆったりした時間の持続は、今フェスティバルで演奏された大アンサンブルのための「初めに(ベレシート)」(2013)やチェロとピアノのための「光の諸相」(2012~15)と共通する。「目覚め」の場合は、チェロの旋律の渋さに対して、オーケストラが意外に色彩的なことに注目した。
3曲目はピンチャーのオーケストラ曲「河(ネハロート)」(2020)の世界初演。委嘱者はサントリーホールの他に、ドレスデンのザクセン州立歌劇場、ロサンゼルス・フィル、パリのフェスティバル・ドートンヌ、ラジオ・フランスと錚々たる名前が並んでいる。曲は「目覚め」とは異なり、劇的緊張に満ち、明暗のコントラストが鮮やかだ。倍音の解析・合成にもとづくスペクトル楽派を消化した世代の傑作ではないかと思った。
4曲目はピンチャーが影響を受けた作曲家としてラヴェルの「スペイン狂詩曲」が演奏された。オーケストラの統率力は、冒頭で書いた2度の経験に照らしても、格段に上がっている。隠れた音型の発見もあった。
(2021.8.27.サントリーホール)