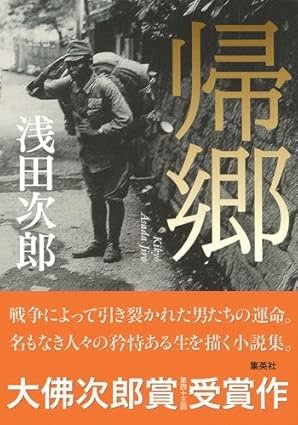能登半島地震から1年たった。現地では倒壊した家屋がそのまま残っていたり、水道がまだ通っていない地域があったりすると報じられている。それらの復旧の遅れはどうしてなのか。そもそも能登半島地震への対応は初動からおかしかった。ヴォランティアに行くなと号令がかかった。また岸田首相(当時)や馳県知事の現地入りが遅かった。その延長線上に今がある。
半村良の「能登怪異譚」は能登にまつわる怪談を9篇収めた短編集だ。どの話も能登弁で書かれている。間延びしてユーモラスだ。だが内容はゾッとする。たとえば「箪笥」は主人公・市助の子どもが夜になると箪笥の上に座る話だ。なぜ箪笥の上に座るのかは分からない。ともかく箪笥の上で夜を過ごす。朝になると普通の生活に戻る。市助には子どもが8人いる。最初は一番下の子どもがそうなる。だんだん増えて、ついには8人全員がそうなる。妻や祖父や祖母もそうなる。市助は気味が悪くなって家出をする。
市助の家は古民家だ。電気をつけても暗い。おまけに部屋数が多い。葬式でもなければ3か月も半年も入らない部屋がある。もしわたしがそんな家に泊まり、がらんとした部屋に一人で寝たら、どんな気持ちになるだろう。部屋には古い箪笥がある。箪笥の上は暗い。そこに何かの気配がしないか。「箪笥」はそんな気配から生まれた話かもしれない。
「箪笥」は一種の寓話かもしれない。市助は一家のあるじだが、市助を除く家族全員の結束が固い。市助は疎外感を味わう。市助は家出をする。そんな話は実際にありそうだ。「箪笥」では市助は最後に家に戻る。だがハッピーエンドだろうか。家に戻ることは、家族に屈服し、家族の仲間に入れてもらうことを意味するかもしれない。市助は一人でいたほうが自由で幸せだったのではないだろうか、という解釈も成り立つ。
ネタばれは避けるが、「箪笥」は最後にオチがつく。そのオチが怖い。さすがに半村良は小説がうまいと舌を巻く。
「箪笥」が箪笥の上の暗い空間から生まれた(かもしれない)話だとすれば、「蛞蝓」(なめくじ)は土蔵の中に大量の蛞蝓が発生したことから生まれた話かもしれない(あるいは、夜釣りをしているときに、海に浮かぶクラゲを見て生まれた話かもしれない)。両者は一対をなす。また「雀谷」(すずめだに)と「蟹婆」(かにばあば)は推理小説的な手法で一対をなす。同様に「仁助と甚八」と「夫婦喧嘩」はコミカルな点で対をなす。「夢たまご」と「終の岩屋」は人生の寓意という点で一対だ。
ただ「縺れ糸」(もつれいと)は対になる作品が見当たらない。その話だけ孤立している。現代への警句が読み取れる話だ。
半村良の「能登怪異譚」は能登にまつわる怪談を9篇収めた短編集だ。どの話も能登弁で書かれている。間延びしてユーモラスだ。だが内容はゾッとする。たとえば「箪笥」は主人公・市助の子どもが夜になると箪笥の上に座る話だ。なぜ箪笥の上に座るのかは分からない。ともかく箪笥の上で夜を過ごす。朝になると普通の生活に戻る。市助には子どもが8人いる。最初は一番下の子どもがそうなる。だんだん増えて、ついには8人全員がそうなる。妻や祖父や祖母もそうなる。市助は気味が悪くなって家出をする。
市助の家は古民家だ。電気をつけても暗い。おまけに部屋数が多い。葬式でもなければ3か月も半年も入らない部屋がある。もしわたしがそんな家に泊まり、がらんとした部屋に一人で寝たら、どんな気持ちになるだろう。部屋には古い箪笥がある。箪笥の上は暗い。そこに何かの気配がしないか。「箪笥」はそんな気配から生まれた話かもしれない。
「箪笥」は一種の寓話かもしれない。市助は一家のあるじだが、市助を除く家族全員の結束が固い。市助は疎外感を味わう。市助は家出をする。そんな話は実際にありそうだ。「箪笥」では市助は最後に家に戻る。だがハッピーエンドだろうか。家に戻ることは、家族に屈服し、家族の仲間に入れてもらうことを意味するかもしれない。市助は一人でいたほうが自由で幸せだったのではないだろうか、という解釈も成り立つ。
ネタばれは避けるが、「箪笥」は最後にオチがつく。そのオチが怖い。さすがに半村良は小説がうまいと舌を巻く。
「箪笥」が箪笥の上の暗い空間から生まれた(かもしれない)話だとすれば、「蛞蝓」(なめくじ)は土蔵の中に大量の蛞蝓が発生したことから生まれた話かもしれない(あるいは、夜釣りをしているときに、海に浮かぶクラゲを見て生まれた話かもしれない)。両者は一対をなす。また「雀谷」(すずめだに)と「蟹婆」(かにばあば)は推理小説的な手法で一対をなす。同様に「仁助と甚八」と「夫婦喧嘩」はコミカルな点で対をなす。「夢たまご」と「終の岩屋」は人生の寓意という点で一対だ。
ただ「縺れ糸」(もつれいと)は対になる作品が見当たらない。その話だけ孤立している。現代への警句が読み取れる話だ。