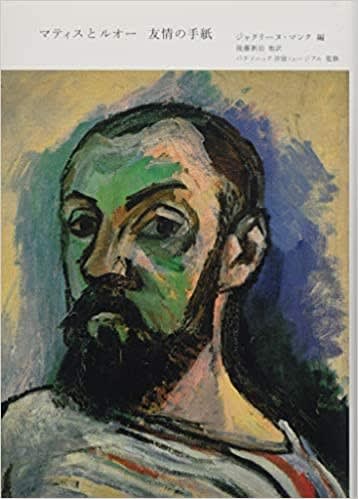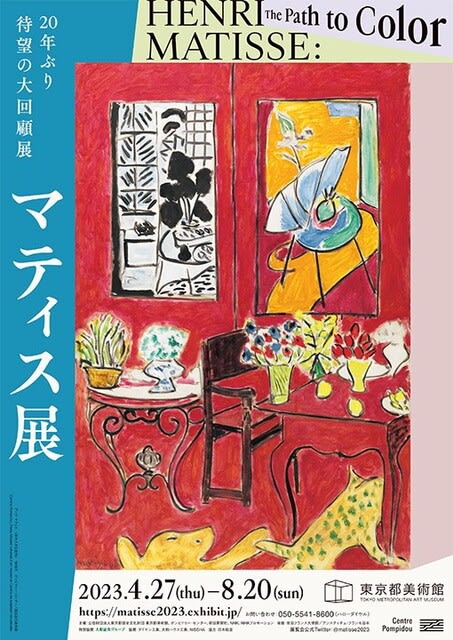東京都江東区の夢の島公園にある「第五福竜丸展示館」を訪れた。第五福竜丸を保存・展示する施設だ。第五福竜丸を見るのは初めて。なんでもそうだが、現地を訪れ、または現物を見ると、感じることが必ずある。第五福竜丸の意外に大きな船体を見ると、この船がたどった数奇な運命が実感される。
今の世の中では、第五福竜丸といわれても、わからない人も多いかもしれない。わたしは1951年生まれなので、第五福竜丸のことを知っている世代だが、その第五福竜丸が都内に保存されているらしいとは知っていても、それがどこなのかは知らなかった。ただ、ずっと気になっていたので、先日、場所を調べたら、夢の島公園だとわかったので、重い腰を上げて行ってみた次第だ。
第五福竜丸はマグロ漁船だった。1954年3月1日にマーシャル諸島で漁をしているときに、アメリカがビキニ環礁で行った水爆実験に遭遇し、大量の死の灰をかぶった。焼津港に戻ったのは2週間後の3月14日。乗組員23人全員に高度の放射能反応があり、「急性放射能症」で入院した。9月23日には無線長の久保山愛吉さんが亡くなった。「原水爆の犠牲者は私を最後にしてほしい」と言い残した。
第五福竜丸事件は当時の社会に大きなショックを与えた。反核運動が盛り上がった。日米両政府は躍起になって抑えようとした。久保山愛吉さんの死についても、放射能との関連を否定する言説を流布した(それは今も続いている)。
第五福竜丸はその後除染され、改造されて、東京水産大学の練習船として使われた。そして老朽化の末、夢の島のゴミの中に放置された。やがて埋め立てに使われる運命にあった。ところが1968年3月10日の朝日新聞に当時26歳の会社員の投書が掲載され、第五福竜丸の運命を変えた。
「第五福竜丸。それは私たち日本人にとって忘れることのできない船。決して忘れてはいけないあかし。知らない人には、心から告げよう。忘れかけている人には、そっと思い起こさせよう。いまから14年前の3月1日。太平洋のビキニ環礁。そこで何が起きたのかを。そして沈痛な気持ちで告げよう。/いま、このあかしがどこにあるかを。/東京湾にあるゴミ捨て場。人呼んで「夢の島」に、このあかしはある。それは白一色に塗りつぶされ船名も変えられ、廃船としての運命にたえている。(以下略)」
投書は大きな反響を呼び、保存運動が起こった。紆余曲折があったが(それ自体がひとつのドラマだ)、保存が決まり、保存施設の建設にむけて動き出した。施設は1976年6月10日にオープンした。それが現在の展示館だ。もし今だったら保存できただろうか。
今の世の中では、第五福竜丸といわれても、わからない人も多いかもしれない。わたしは1951年生まれなので、第五福竜丸のことを知っている世代だが、その第五福竜丸が都内に保存されているらしいとは知っていても、それがどこなのかは知らなかった。ただ、ずっと気になっていたので、先日、場所を調べたら、夢の島公園だとわかったので、重い腰を上げて行ってみた次第だ。
第五福竜丸はマグロ漁船だった。1954年3月1日にマーシャル諸島で漁をしているときに、アメリカがビキニ環礁で行った水爆実験に遭遇し、大量の死の灰をかぶった。焼津港に戻ったのは2週間後の3月14日。乗組員23人全員に高度の放射能反応があり、「急性放射能症」で入院した。9月23日には無線長の久保山愛吉さんが亡くなった。「原水爆の犠牲者は私を最後にしてほしい」と言い残した。
第五福竜丸事件は当時の社会に大きなショックを与えた。反核運動が盛り上がった。日米両政府は躍起になって抑えようとした。久保山愛吉さんの死についても、放射能との関連を否定する言説を流布した(それは今も続いている)。
第五福竜丸はその後除染され、改造されて、東京水産大学の練習船として使われた。そして老朽化の末、夢の島のゴミの中に放置された。やがて埋め立てに使われる運命にあった。ところが1968年3月10日の朝日新聞に当時26歳の会社員の投書が掲載され、第五福竜丸の運命を変えた。
「第五福竜丸。それは私たち日本人にとって忘れることのできない船。決して忘れてはいけないあかし。知らない人には、心から告げよう。忘れかけている人には、そっと思い起こさせよう。いまから14年前の3月1日。太平洋のビキニ環礁。そこで何が起きたのかを。そして沈痛な気持ちで告げよう。/いま、このあかしがどこにあるかを。/東京湾にあるゴミ捨て場。人呼んで「夢の島」に、このあかしはある。それは白一色に塗りつぶされ船名も変えられ、廃船としての運命にたえている。(以下略)」
投書は大きな反響を呼び、保存運動が起こった。紆余曲折があったが(それ自体がひとつのドラマだ)、保存が決まり、保存施設の建設にむけて動き出した。施設は1976年6月10日にオープンした。それが現在の展示館だ。もし今だったら保存できただろうか。