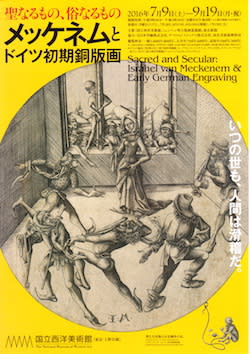サントリーホール国際作曲委嘱シリーズの今年のテーマ作曲家、カイヤ・サーリアホ(1952‐)の新作演奏会。指揮はエルネスト・マルティネス=イスキエルド(昨年サーリアホのオペラ「遥かなる愛」を指揮した人)、オーケストラは東京交響楽団。
1曲目はシベリウスの交響曲第7番。サーリアホが「影響を受けた作品」として選んだ曲だ。2014年のテーマ作曲家パスカル・デュサパンはシベリウスの交響詩「タピオラ」を選んだ。偶然の一致かもしれないが、シベリウスの最後のスタイルを評価する作曲家が一定数いるのかもしれない。
演奏は、指揮者はあまり関与していなかったが、オーケストラから出てくる音楽は、わたしのシベリウスのイメージと合っていて、日本のオーケストラにはシベリウス演奏の伝統があることを感じた。
2曲目はサーリアホの新作「トランス」。3楽章形式のハープ協奏曲(ハープ独奏はグザヴィエ・ドゥ・メストレ)。冒頭、ハープが短いフレーズを奏し、その最後の音を木管が引き延ばす。そうすることによってハープの余韻が補強され、音の層が生まれる。それが(楽器を変えながら)繰り返される。
第2楽章ではハープ奏者が左の手の平でハープの弦を叩く音が何度も出てくる。バスドラムがその音を補強する。音楽が美しく流れることを阻止して、立ち止まって考えさせるような効果がある。なにを? この楽章のタイトル「ヴァニテ」(人生の虚しさ)を、か。
サーリアホは今や、どんな曲を書いても、自分の音が鳴るようになった。この曲はその証しだと思う。透明な結晶のような音。少し聴いただけでサーリアホだと分かる音。
会場では日本のハープ奏者の第一人者と目されている方の姿を見かけた。メストレの演奏もいいが、できればその方にこの曲を演奏してもらえないかと思った。作曲者も女性、その方も女性、同性なので分かりあえる繊細さ、あるいは柔軟さがあるのではないだろうか。
3曲目はサーリアホが「注目している若手の作品」、ゾーシャ・ディ・カストリ(1985‐)の「系譜」。音の鮮度がいい。わたしも注目した。4曲目はサーリアホの「オリオン」。2曲目の「トランス」はハープ協奏曲なので、オーケストラは小編成だったが、「オリオン」は大オーケストラのための曲。雄弁な語り口は大家のそれだ。3曲目と4曲目では、イスキエルドの指揮も積極的だった。
(2016.8.30.サントリーホール)
1曲目はシベリウスの交響曲第7番。サーリアホが「影響を受けた作品」として選んだ曲だ。2014年のテーマ作曲家パスカル・デュサパンはシベリウスの交響詩「タピオラ」を選んだ。偶然の一致かもしれないが、シベリウスの最後のスタイルを評価する作曲家が一定数いるのかもしれない。
演奏は、指揮者はあまり関与していなかったが、オーケストラから出てくる音楽は、わたしのシベリウスのイメージと合っていて、日本のオーケストラにはシベリウス演奏の伝統があることを感じた。
2曲目はサーリアホの新作「トランス」。3楽章形式のハープ協奏曲(ハープ独奏はグザヴィエ・ドゥ・メストレ)。冒頭、ハープが短いフレーズを奏し、その最後の音を木管が引き延ばす。そうすることによってハープの余韻が補強され、音の層が生まれる。それが(楽器を変えながら)繰り返される。
第2楽章ではハープ奏者が左の手の平でハープの弦を叩く音が何度も出てくる。バスドラムがその音を補強する。音楽が美しく流れることを阻止して、立ち止まって考えさせるような効果がある。なにを? この楽章のタイトル「ヴァニテ」(人生の虚しさ)を、か。
サーリアホは今や、どんな曲を書いても、自分の音が鳴るようになった。この曲はその証しだと思う。透明な結晶のような音。少し聴いただけでサーリアホだと分かる音。
会場では日本のハープ奏者の第一人者と目されている方の姿を見かけた。メストレの演奏もいいが、できればその方にこの曲を演奏してもらえないかと思った。作曲者も女性、その方も女性、同性なので分かりあえる繊細さ、あるいは柔軟さがあるのではないだろうか。
3曲目はサーリアホが「注目している若手の作品」、ゾーシャ・ディ・カストリ(1985‐)の「系譜」。音の鮮度がいい。わたしも注目した。4曲目はサーリアホの「オリオン」。2曲目の「トランス」はハープ協奏曲なので、オーケストラは小編成だったが、「オリオン」は大オーケストラのための曲。雄弁な語り口は大家のそれだ。3曲目と4曲目では、イスキエルドの指揮も積極的だった。
(2016.8.30.サントリーホール)