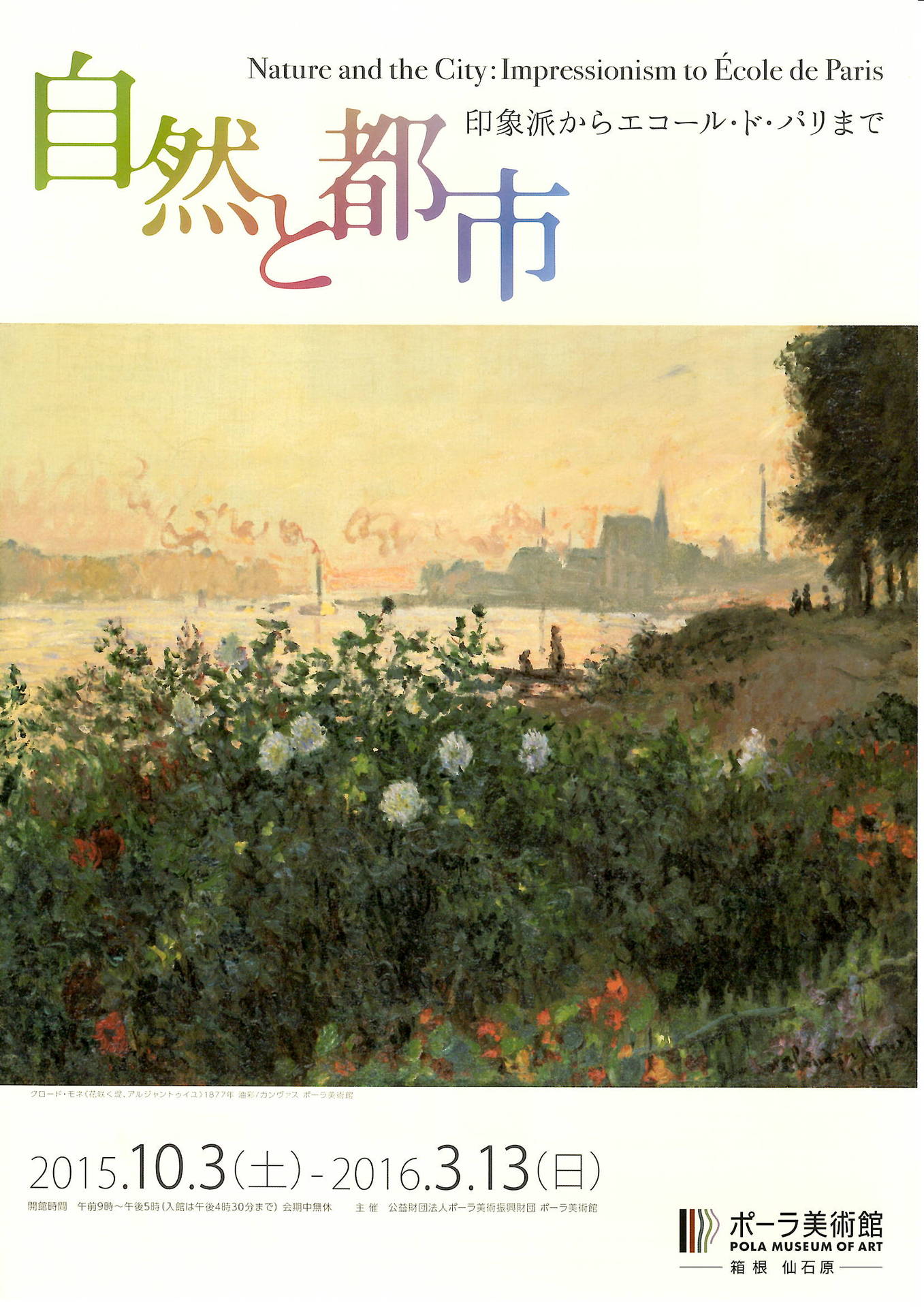戦後70年だった今年。わたしもそれなりに想いを巡らしながら過ごしたので、この一年を振り返っておきたい。
わたしにとっては、東京藝大が開催した信時潔の「海道東征」の演奏会が、戦後70年のビッグイヴェントだった。皇紀2600年(1940年)の祝賀曲の一つだ。軍国主義がピークに達した時期を象徴する曲。当時の演奏がSPに録音され、今ではCDに復刻されている。そのCDを持っているので、何度か聴いたことがある。異常な興奮が渦巻く演奏だ。聴いていると息苦しくなる。その曲がいま演奏されると、どう聴こえるか。
結果的には、驚くほど平明な曲だと思った。拍子抜けするほどだ。こういう曲だったのかと思った。では、初演当時のあの興奮はなんだったのか――。時代が違うと、同じ曲でもこんなに変わるものか。
そう感じたのは、演奏がよかったからでもあるだろう。湯浅卓雄指揮の東京藝大シンフォニーの演奏、独唱陣は甲斐栄次郎、福島明也など錚々たる顔ぶれ、合唱は藝大の学生さんたち。その合唱が透明感あふれるハーモニーを聴かせた。前述の初演当時の合唱との違いが曲の印象を一変したと思う。
でも、「海道東征」を歴史的な文脈から切り離して、純粋に音楽として評価すべきかとなると、まだそこまでは言い切れない気がする。この曲のありのままの姿が示された。それで十分だと思う。
戦後70年を離れて、この一年を思い起こすと、まっさきに目に浮かぶのは、今年2月にパーヴォ・ヤルヴィがN響を振ったマーラーの交響曲第1番「巨人」だ。いつもは沈着冷静なN響が、あのときは我を忘れて、夢中になって演奏していた。異様な熱気を放つ演奏。あのときは、プログラムの記載とは異なり、コンサートマスターにロイヤル・コンセルトへボウ管のエシュケナージが入っていた。その影響も大きかったのではないだろうか。
サントリー芸術財団のサマーフェスティヴァルで演奏されたシュトックハウゼンの「シュティムング」とツィンマーマンの「ある若き詩人のためのレクィエム」は注目の的だった。前者では倍音唱法の美しさに惹きこまれ、また後者では「ついにこの曲が日本でも鳴り響いた」という感慨があった。
でも、いま思い返すと、大野和士/都響による後者の演奏は、あまりにも整然としすぎていなかったろうか。音響のコントロールは見事だったが、その一方で20世紀の歴史への怒りや絶望はあまり感じられなかった。
わたしにとっては、東京藝大が開催した信時潔の「海道東征」の演奏会が、戦後70年のビッグイヴェントだった。皇紀2600年(1940年)の祝賀曲の一つだ。軍国主義がピークに達した時期を象徴する曲。当時の演奏がSPに録音され、今ではCDに復刻されている。そのCDを持っているので、何度か聴いたことがある。異常な興奮が渦巻く演奏だ。聴いていると息苦しくなる。その曲がいま演奏されると、どう聴こえるか。
結果的には、驚くほど平明な曲だと思った。拍子抜けするほどだ。こういう曲だったのかと思った。では、初演当時のあの興奮はなんだったのか――。時代が違うと、同じ曲でもこんなに変わるものか。
そう感じたのは、演奏がよかったからでもあるだろう。湯浅卓雄指揮の東京藝大シンフォニーの演奏、独唱陣は甲斐栄次郎、福島明也など錚々たる顔ぶれ、合唱は藝大の学生さんたち。その合唱が透明感あふれるハーモニーを聴かせた。前述の初演当時の合唱との違いが曲の印象を一変したと思う。
でも、「海道東征」を歴史的な文脈から切り離して、純粋に音楽として評価すべきかとなると、まだそこまでは言い切れない気がする。この曲のありのままの姿が示された。それで十分だと思う。
戦後70年を離れて、この一年を思い起こすと、まっさきに目に浮かぶのは、今年2月にパーヴォ・ヤルヴィがN響を振ったマーラーの交響曲第1番「巨人」だ。いつもは沈着冷静なN響が、あのときは我を忘れて、夢中になって演奏していた。異様な熱気を放つ演奏。あのときは、プログラムの記載とは異なり、コンサートマスターにロイヤル・コンセルトへボウ管のエシュケナージが入っていた。その影響も大きかったのではないだろうか。
サントリー芸術財団のサマーフェスティヴァルで演奏されたシュトックハウゼンの「シュティムング」とツィンマーマンの「ある若き詩人のためのレクィエム」は注目の的だった。前者では倍音唱法の美しさに惹きこまれ、また後者では「ついにこの曲が日本でも鳴り響いた」という感慨があった。
でも、いま思い返すと、大野和士/都響による後者の演奏は、あまりにも整然としすぎていなかったろうか。音響のコントロールは見事だったが、その一方で20世紀の歴史への怒りや絶望はあまり感じられなかった。