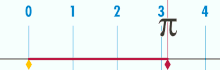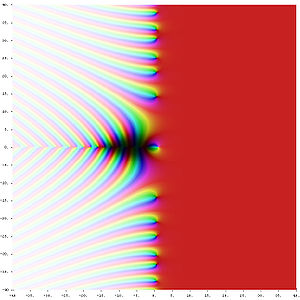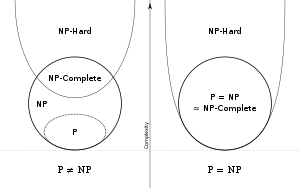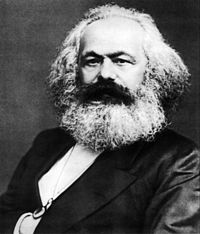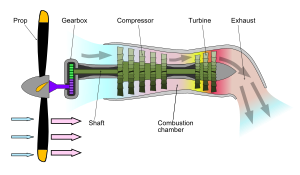雨上がり 綱引き消えて 秋空に 紅白の玉 舞う五十年
【高所恐怖症】
高所恐怖症の現れ方には色々なタイ
プがあるが、その原因は高い所から
落ちて死んでしまったらどうしよう
という「死の恐怖原因説」があるが
そうりによると、高所恐怖症は強迫
神経症の症状であり不安神経症(パ
ニック障害)の要素も含まれている
症状だと言うが本当にそうなのか?
この間の白山登山の経験から「苦手」
の、「弱点」の克服を実践しようと
と考えネット検索する(『山岳信仰
と教会堂』)。

※崖の上や足場の不安定な場所で怖
いと思うのは、本来、身を守る大切
な反応。
高所恐怖症の人は、単なる高さにお
びえるというよりも、下に空間があ
るということをイメージさせる状況
を怖がる場合が多いとも指摘する。
理性が働かなくなる理由がある。
心理学の世界で「抑制の逆説効果」
などと呼ばれる現象があり、感情や
思考を抑制しようとすると、かえっ
て増幅させてしまうことがあるとい
う。
「シロクマ実験」
高いところめぐりツアーの被験者に
「怖くない!大丈夫!」というおま
じないを唱えさせる。
「恐怖が増幅する理由」
「怖い」という感情がふくらむと、
足がすくんだり、鼓動が高まったり
という身体反応が出る。それらが脳
にフィードバックされ「やっぱり怖
いんだ」と怖さが増幅されてしまう。
さらにもう1つ、頭の中には、過去
の経験に基づいた行動や反応に対す
る予測図が固定化している。その予
測図に基づいて行動する(=フィー
ドフォワード)。
高所恐怖症の人は、間違った予測図
を思い描いてしまう。「恐怖が高ま
って最後はどうにかなってしまう」
と考える。ありもしない恐怖をどん
どん予想し、事実とはかけ離れた結
末を思い描いてしまったため、その
場に立っていられなくなったと述べ
ている。
専門家に聞くと「怖いままで逃げ出
してしまうと、ますます悪化してし
まうこともある」という。
ヘビ恐怖症も治った!?
ヘビの写真を見続けると、恐怖の度
合いを示す発汗量はいったん上がっ
たものの、約10分で正常並みになる。
ヘビの写真を10分見ていただけで、
なぜか恐怖の度合いが下がったので
す。実は、恐怖はいつまでも続くの
ではなく、ある一定の時間を過ぎる
と下がり始めるという。その場に居
続ければ、いずれその状況でも大丈
夫だという体験ができるからだと。
これをNHKの‘ためしてガッテン’
では「OK体験」と名づけた。専門
家によると、もともと「恐怖」は緊
急事態に対する反応なので、エネル
ギーがそう長くは続かないとする。
本当に危険な場合であれば、いつま
でも怖がっていられるが、遅くとも
15分くらいで恐怖の反応は下がり始
めると指摘する。
つり橋に挑戦し。10歩も進めなか
った人々が画板に2分ごとに何かを
記入すると、あっという間に「OK
体験」することができたという事例
を報告している。被験者たちが行っ
たのは、実際の医療現場でも行われ
ている「エクスポージャー(恐怖の
対象などにさらすという意味)」と
いう方法を、専門家のアドバイスに
よってアレンジした方法を応用した。
エクスポージャーは、医療現場でも
効果があると認められているという。
まずはおよそ30メートルのつり橋で
我慢できるところまで進んだら、そ
の場で止まってもらい、画板上の画
用紙に2分ごとに恐怖の度合いを書
き込み「もう我慢できない!」とい
う恐怖の度合いを百として、その時
点での恐怖の度合いを点数化し、恐
怖の度合いがゼロになった(OK体験)
ところで、いったん戻るというもの。
これを繰り返す。一度「OK体験」
すると自信がつくのか、1回目より
も先まで進むことができるという。
【「OK体験」のポイント】
心を閉じない:
怖くないと言い聞かせたり、他のこ
とに熱中したりしていると「OK体
験」は訪れない。実際に恐怖を体験
することがとても大切。
恐怖にのみこまれない:
頭の中が恐怖でいっぱいになってし
まっても「OK体験」は訪れない。
ある程度の冷静さを保てるレベルの
高さや場所を選ぶ。
※「OK体験」は吊り橋でなくても、
ビルや、タワー、歩道橋などでも可
能(ただし、場所は問いませんが、
とにかく安全が第一。崖や足場の不
安定な所など、危険な場所では決し
て行わない)。10分間たっても怖さ
がなくならない場合は、もっと低い
ところで試すなど、簡単なものから
段階的に挑戦する。
実際に行う場合の注意点
例えば、つかんでいる手の感覚など、
その時の感覚に目を向けると、恐怖
にのみこまれにくくなり、恐怖心が
下がるのが早くなり、家族や友人な
ど、誰かと一緒に行くと、冷静さを
保ちやすくなる。
というレシピだが「チャレンジし、馴れろ」
ということに尽きる。近々実行に移すこ
とに。

※「こうしたフィードフォワード制
御は、単に小脳のみを介した機械的
な動きに便われているだけではなく、
大脳連合野からの指令によって随意
運動が遂行される場合にも利用され
ていると思われる。連合野が随意運
動の指令を発するとき、指令信号は
運動野を経て小脳に送られる一方、
小脳からの出力が大脳運動野に接続
する錐体路のニューロンに投射され
るようになり、結果的に運動が実行
される以前に小脳と大脳の間でルー
プが形成される。この過程で小脳が
果たしている機能についてはいまな
お不明な点が多いが、小脳が運動を
制御する“コンビュータ”であるこ
とを考慮すれば、おそらく、運動を
(部分的に)シミュレートしながら
必要な筋張力の値を計算し、これを
もとにそれぞれの筋肉を支配する大
脳運動野の各部位に適切な“準備”
をさせていると推測される。ここで
言う“準備”とは、生理学的には、
運動に数百ミリ秒ほど先だって大脳
運動野に運動準備電位を誘起する過
程を指し、これが小脳からの情報に
基づいていることは、小脳を除去し
たサルで準備電位が著しく減少する
という実験結果から確かめられる。
準備電位が誘起された状態では、筋
張力それ自体は変化していないが、
これから行おうとしている運動で収
縮する筋では、伸張に対する脊髄反
射が増幅し、逆に弛緩する筋の反射
は減少することが判明しており、ま
さに運動の“準備”が整えられてい
ると言って良い。このように、運動
の実行以前にその状況を予測してし
かるべき目標を設定するというフォ
ーマットは、フィードフォワード制
御の典型である」(『小脳のフィー
ドフォワード制御』)。
本当に久しぶりで、今年で50年を
迎えた市民運動会に自治会の裏方で
参加するが、やはり消すことのでき
ないイベントであることを確認。競
技内容も時代とともに「不易流行」
のコントラが鮮やかだと、雨天中止
も危ぶまれたが無事終わったと詠う。