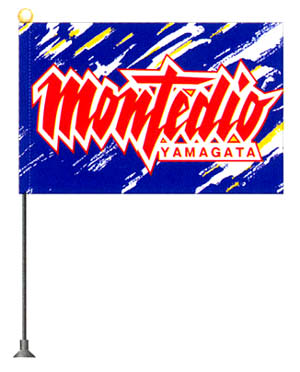 PART3はこちら。
PART3はこちら。
‘84年、NECの同好会から発したサッカークラブは、これが意外なほど強かった。べにばな国体のどさくさまぎれの(あの頃はなんでもありだった)強化と相まって、東北社会人リーグ4年連続優勝。その背景に、コンピュータ業界の発展があったことは間違いない。
ちょうどその頃、NEC鶴岡で働いていた人間にいろいろときいてみた。
「その頃って、あそこで何作ってたんだよ。」
「半導体。とにかぐ作れば売れる時代でやー。三交代でフル操業だったんや。給料もけっこういいけし。」
日電の業界におけるシェアが揺るぎない頃。ビル・ゲイツがまだまだ低姿勢だったあたりか。
企業内スポーツが、その業界の消長に左右されるのは、プロ野球における横浜ベイスターズや近鉄バッファローズの例を引くまでもない。Jリーグが、何はともあれ発足できたのは、地獄の構造不況が本格化する前の、バブルの名残りがあったからだろう。わたしは一種の奇跡だとすら思う。
で、モンテディオ。NECが丸抱えできる時代はとうに過ぎ(山形工場はもう閉鎖)、本来であればJ2にいることすらおぼつかないはずの経営状況を、社団法人化、というアクロバットで乗り切ったこのチーム(背に腹はかえられないから機構側も承認せざるをえなかった)は、2年前に“あぶないところで”J1に昇格しそうなぐらい強くなってしまったのである。コンパクトなサッカーをめざした監督柱谷(兄)が、あんな形でチームを去ったのは寂しいかぎりだが……
Jリーグの隆盛が社会体育の充実、ひいては部活動の社会体育への移行にそのままつながると今は単純に考えているわけではない。ジュニアユースと中体連の関係など、整理しなければならない問題は山積している。しかし、くり返すが現在が「過渡期」であることに疑問の余地はない。その認識をもとに「部活動」を、教職員自身がもう一度考え直す時期にきている。だいたい「本務であるかどうか」が、いまだに論議のネタになっている状況が、健康であるはずがないではないか。
【サッカーくじの裏側に・終了】
状況は今も変わっていない。部活動も、モンテディオも。しかし今回の改名騒ぎには驚かされた。利権だの何だのと言われているが、そんなものが存在しうるレベルにすらないことの方が重要ではないか。がんばれモンテ。










 PART2は
PART2は
 モンテディオ山形
モンテディオ山形 “みずから地雷を踏みに行くような”という表現は、わたしの知るかぎり
“みずから地雷を踏みに行くような”という表現は、わたしの知るかぎり





