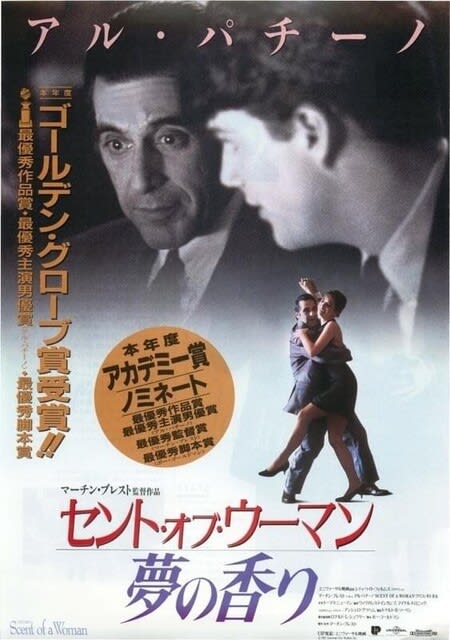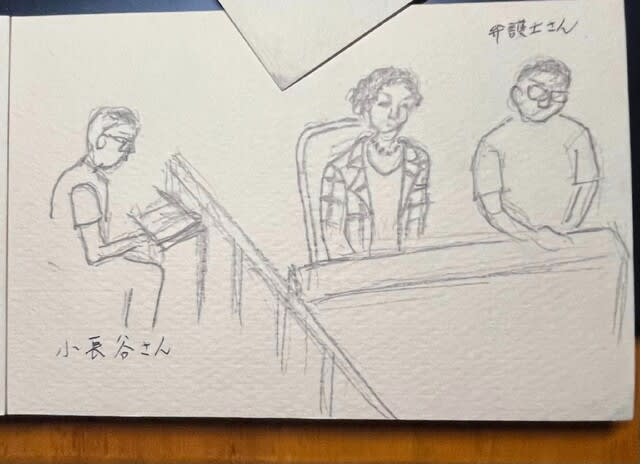~~~~~~~~~~~~~~~~~~
キリスト教の洗礼について(その-1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
いま85歳の私が中学2年生で洗礼を受けたとき、担任のクノール神父さんは私に一本の灯のともったろうそくを手渡して、「ともれる灯(ともしび)を受けなさい。主イエス・キリストが来られるとき、喜んで主を迎えることが出来るように、いつも光の子として歩みなさい。」という意味の言葉を言われたことになっている。ことになっている、とはずいぶん無責任に聞こえるかもしれないが、10人ほどの同級生に流れ作業で繰り返される言葉の深い意味をその場でしっかり悟れるはずはなかった。
洗礼そのものがただの儀式に過ぎなかった。受洗後は、日曜日のミサの時に赤く長いスカートをはき、白いケープを着て赤い幅広のカラーをつけたピエロのようなスタイルで祭壇に奉仕し、ウイーン少年合唱団よろしくラテン語の合唱などもやったが、それ以外は、洗礼の前にも、後にも、自分の生活はまわりの生徒たちと何も違わなかった。
中・高はミッションスクールの男子校だからまわりに女子学生はいなかったが、思春期の色欲は健全にもすこぶる旺盛だった。上智大学でイエズス会の志願者だった間は猫をかぶっていたが、会を飛び出した後は、解き放たれた若駒のように全力で疾走し、ほとんどの学生が就職活動でおとなしくなる大学の4年に学生会の議長選挙に立候補して、当選後は上智大全学生の頂点に君臨し、書記と称してきれいな女子学生の大根足を壇上に並べたりもした。議長の立場を武器にせっかくナンパに成功しそうになっても、「僕はいつか神父になるかもしれないので結婚はしない」とポロリと本音を吐くと、彼女らはみな身をひるがえして去っていき、間もなく「お見合いして結婚することになりました。」と言って東大や慶応のお坊ちゃまを紹介された。女性とは薄情な現実主義者だ、という確信がそのとき植え付けられた。中には、それなら私も、とばかりにシスターになったのもいないわけではなかったが、要するに私は振られ上手だったと言える。
話を元に戻せば、私は神父さんから額(ひたい)にチョロリと水を注がれた洗礼の前も後も、意識も生活態度も全く変わらないごく普通の多感な若者にすぎなかった。洗礼は主観的には私の本質を何も変えなかった。洗礼が人間の生き方の根底を覆すほど重大なことだということは、ずっと後になってやっと気が付いた。

手に入る画像の中でイエスの全身がヨルダン川の水に沈むのを比較的忠実に再現しているのはこれだろうか
本当は洗礼者ヨハネも左の岸辺にではなく、イエスと一緒に水に入っているはずだが・・・
そもそも、洗礼式の本来の形が、全身水に沈む「浸しの洗礼」であることに注意が向いたのも、1965年前後、カトリック教会の歴史上2度しか起きなかった180度の大転換点に当たる第2バチカン公会議の後だった。
聖書によれば、確かにナザレのイエスはヨルダン川に入り、全身頭までしっかり水に沈んで、洗礼者聖ヨハネから「罪の許しを得させる悔い改めの洗礼」を受けたとある。それは、私が受けた教会の建物の中で額にチョロリと水を流してもらう「注ぎの洗礼」とは、形も意味も全く別ものであることを知らなかった。また、その洗礼の本質が回心に伴う「罪の赦し」であることも意識していなかった。そもそも、洗礼を受けたときの私は、自分が赦しを受けなければならない罪人であるという自覚すらほとんどなかった。洗礼はただ、キリスト教会への入信式にすぎず、それ以後は信者として未信者と区別されるだけのことだった。

イエスの洗礼
洗礼が額にチョロリと水を注ぐだけのものとしてイメージされるようになったのは、おそらく4世紀頃からではなかったか
話をがらりと変えよう。魚は鰓(えら)で水中の酸素をとって生きている。だから水から揚げるとすぐ死んでしまう。反対に、猿や人間は肺呼吸して空気中の酸素を吸って生きているから、水に15分も沈められれば溺れて死んでしまう。
その意味で、人が水に沈むことは昔から「死」を象徴している。つまり、洗礼で頭まで水に沈むと言うことは、「お前は溺死した」ということを意味していた。何に死んだのか。古い人間-闇に生きる罪人-に死に、古い人間の屍(しかばね)とともにすべての罪を水中に残して、キリストの復活の命を身にまとった新しい光の子に生まれ変わって水から立ち上がり、聖なる人として信仰の光の中で新たな命を生き始めることを象徴しているのだった。
だから、肉体の目には満員電車の中のサラリーマンは皆同じビジネススーツに身を包んだ同じ人間に見えるが、霊的な目で透視すればクリスチャンとノングリスチャンとの間には人間とチンパンジーほどの違いがあるはずなのだ。
知れば愕然とするほど大きなこの霊的変化を、洗礼は人間にもたらしたはずだった。頭まで水に沈む「浸しの洗礼」を受けた人なら、その宗教儀式が象徴する重大な意味、即ち、人は洗礼とともにキリストの死と復活に与るという事実を説明してもらったかもしれないが、「注ぎの洗礼」を受けた人も、授けた人も、その重大な信仰の神秘をほとんど意識していなかったのではないか、と今にしてわたしは疑う。
少なくとも、中学二年生の私はもちろんのこと、恐らく私に洗礼を授けたクノール神父さんもそんなこと深く考えてはいなかったのではないか。洗礼の前と後で何も変わらなかったのはそのためだった。そして、日本でカトリックの洗礼を受けた人達も、みなほとんどは同じだったに違いない。
つまり、洗礼を受ける前の私は神道や仏教を信じていた自然宗教の人たちと同じだったし、洗礼を受けた後も自然宗教の信者たちと変わらないレベルの宗教心を生きていたにすぎない。それはただ自然宗教の仏教バージョンや神道バージョンから、同じ自然宗教のキリスト教バージョンに外面的な装いが変わっただけだった。バージョンは違っても自然宗教はあくまで自然宗教だ。煎じ詰めればどれもこれも「ご利益宗教」であることに変わりはない。
ところで、マタイの福音書には10人の乙女たちのたとえ話がある(25.1-13)。賢い五人は灯火(ともしび)と一緒に油を入れた壺に持っていた。愚かな五人は灯火はもっていたが、油を用意していなかった。
この話が洗礼を受けたとき私が持たされた火の灯ったローソクと関係があることに、私は長い間気が付かなかった。それはそうだろう、2000年前のともし火と現代のローソクは、目的は同じでも全くの別物だからだ。
キリストの時代のともし火は油の入った陶器のランプが普通で、一度燈心の火を消してしまったら、もう一度火をつけるのは容易ではなかった。シュッ!と擦れば簡単に火が付くマッチは19世紀以降のものだから、キリストの時代には火の点ったランプを用意したら、実際に使う本番までずっと点したままにするしかない。だから、万一それを必要とするタイミングが遅れる場合に備えて、別の壺に予備の油を用意しておく必要があったのだ。
聖書のともし火の話を、現代の注ぎの洗礼の時のように、安価なパラフィンのローソクにガスライターで火をつけたり消したり自在にできる現代の感覚で読んだら、意味を取り違えることになる。
洗礼のとき、水に沈んで罪にまみれた古い人間の屍を水中に残し、キリストの復活にあずかる新しい人間として水から立ち上がった受洗者は、真新しい白衣を着せられる。それは、受洗者がすべての罪を赦されて新しい人間に生まれ変わり、聖なるものとなったことを象徴する。端的に言えば、人は洗礼を受けた時、みな罪を知らぬ聖人になったことになる。そして、この白い衣服は復活後に天国の宴に連なるときに着る晴れ着を意味する。だから、洗礼を受けたすぐ後に死ねば、人はみな聖人として天国に直行すること疑いなしだった。
ところが、普通は洗礼後もしばらくこの世で生きていかなければならない。この浮世の生活を生きるということは、いやでも日々罪にまみれることになる。嘘をつかない人はいないだろう。性欲にまみれ、淫らな思いにふけり異性に近づくこともあるだろう。傲慢や嫉妬や憎悪に駆られ、物欲に溺れ、金銭に執着しその奴隷にもなるだろう。だから、人はみな日々初心に帰り回心の業に励まなければならない。そのためにカトリック教には「懺悔」とか「告解」とか「赦しの秘跡」などという便利なものがある。神父のところに行って自分の罪を正直に告白すれば全て許され、洗礼の時にいただいた白い衣は、罪によごれて汚くなっても再び元の純白に戻ることが出来る。懺悔は第二、第三・・・の洗礼のようなものだ。人はこうして死ぬまで絶えず「回心」を繰り返しながら天国に入るにふさわしい聖人の境地に近づくことになっている。これこそ超自然宗教であるキリスト教の生きざまであるはずだ。超自然宗教である真のキリスト教は、一切の現世利益(りやく)を売らないことになっているが、その代わりに死からの復活と永遠の命を確約する。
ところが現実はどうか。人はとどまることも後戻りすることもできない回心の旅路を一直線に自分の終末である死に向かって進むことなく、四季がめぐる様に同じ場所でぐるぐる回るマンネリズムの惰眠に落ちていないだろうか。前者が超自然宗教の救済への道で、後者は自然宗教の始めも終わりもない迷妄の中を堂々巡りする道なのだ。
色々脱線したが、今改めて、私たちはキリスト教の洗礼の本当の意味を再発見し、生活を再点検し、回心と深くリンクしたキリスト者本来の生き方を考えなおす必要がありそうだ。回心は洗礼の前に緒についていなければならなかった重大事だが、後、先は構わない。今からでも遅くはない。死が突然襲い掛かってくるまでに、まだ「回心」の油を買いに行くしばしの暇はあるのだから。今ならまだ間に合う。これを終活と言わないで、何が終活だろうか。
あと一つ寝るとクリスマスイヴ!あなたの今年のクリスマスと去年のクリスマスは同じですか?同じならヤバイ!来年のクリスマスこそは洗礼の回心の実を結ぶクリスマスになりますように!
メリークリスマス!
(つづく)