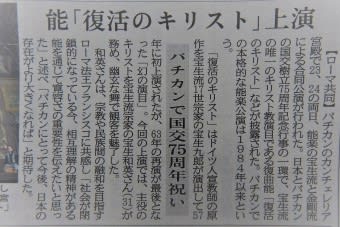~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
聖書から見た「サイレンス」―その(7)
〔 最 終 回 〕
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

スコセッシ監督と俳優たち
聖書の本質的メッセージとは何か?それは「主、キリストは蘇えられた!」の一言に尽きる。こんな強烈なメッセージは「自然宗教」のどこを探しても決して見つかるものではない。
もし、ナザレのイエス、すなわちメシア(救世主)と言われたキリスト、が人間として本当に十字架刑の拷問の末に「死んで」三日目に「蘇えられた」、つまり「復活して生き返った」―「死」を克服し「死」の支配に対して勝利を収めた―のでなかったら、キリスト教ほど馬鹿馬鹿しい、割の合わない宗教はない。
この世で、富も、名誉も、地位も、健康も、長寿も、いいことはなにも約束してくれない、ご利益を積極的に「全否定」するだけでは気が済まないで、「貧しい人は幸い」である(ルカ4章20節)。「悲しむ人々は幸い」である(マタイ5章4節)。「義のために迫害される人は幸い」である(同5節)。「私のためにののしられ、迫害され、身に覚えの無いことであらゆる悪口を浴びせられるときあなた方は幸い」である(同11節)などと言ってはばからない。
まだしつこく続く。「富んでいるあなた方は、不幸である。」「今笑っている人々は不幸である。」「すべての人にほめられるとき、あなた方は不幸である」(ルカ6章24節以下)。つまり、市井の凡俗な我々が希求する価値観の全否定だ。
それでもまだ足りないか、ご丁寧に駄目押しの無理難題が並ぶ。「敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。・・・あなたの頬を打つ者には、もう一方の頬も向けなさい。・・・あなたの持ち物を奪うものから取り返そうとしてはならない。・・・(ルカ6章27節以下)。
そんな無茶苦茶なことを要求した挙句の果てに、ローマ人が考案した最高に残酷な拷問刑―「十字架」―に磔けられて苦しみもだえ、「沈黙」する神に完全に見放され、「エリ、エリ、レマ、サバクタニ!」という絶望の叫びをあげた後に哀れにも息を引き取ったキリストが、何の夢も希望も残さず、あっけなく死んで、「それで一巻の終わり!」なら、キリスト教ほどアホらしい宗教はない。
それでも、キリストの生前の魅力の集団催眠にかかった信者たちが、次々と拷問を甘受し、人が猛獣に喰い殺されるのを見て楽しむ野蛮なローマ人の娯楽ショーの消耗品として殺されていく姿は、ただ哀れとしか言いようがないではないか。
「自然宗教」的メンタリティーから言えば、要するに、これ以上にアホらしい宗教は絶対に考えられないのだ。
それなのに、なんでキリスト教(カトリック、プロテスタント、その他もろもろの宗派を合わせて)は世界人口の1/3、22.5億人もいるのか?
やはり、もしかして、キリストは本当に復活したのでは・・・?(そうとでも考えなければ、この数字は全く辻褄が合わないではないか?)それとも紀元313年にコンスタンチン大帝に手籠めにされて帝国の「囲われ女」に身を持ち崩したキリストの花嫁(教会)が、最も成功した「自然宗教」として勢力を張っている姿なのか?(これは恐ろしい話で、考えたくもないが・・・。とにかく、この体制は325年以降1965年まで、いや今日まで基本的に変わっていない。)
何はともあれ、そのキリスト教は今年も4月16日の日曜日に「復活祭」を祝った。厳密に言うと、15日の日没から16日の明け方まで、徹夜して復活祭を祝うことになっていた、というのが正しいのだが・・・。
だからどうした?何か起こったか?世界は何も変わらなかったではないか?
一見するところ確かにそうだ。私も全く同感だ。何も変わったようには見受けられない。
では、本当のところはどうなのか?本当に何も変わらなかったのか。変わる兆しもないのか?
10年前から45万人を切って、毎年平均1000人単位で信者が減少している日本のカトリック教会で、もし500人の信者が本当にキリストの復活を心から信じたとしたらどうだろう?彼らが本気で聖書の教えを信じて実践しようと努めたらどうなるか?
キリストは彼らに向かって「あなた方は地の塩である」「あなた方は世の光である」(マタイ5章13節以下参照)と言われた。圧倒的少数者の彼らではあるが、世間を腐敗から守り、社会に味をつけ、世の闇を照らすだろうと言う予言だ。
神が天地創造の最初に人類に命じられたこと「産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。」(創世記1章28節)という命令を忠実に守り、若い夫婦が一斉にピルも含め一切の避妊行為をやめて愛し合えば、どうなるだろう。避妊を完全に意識から排除した愛し合う夫婦の交わりの心身を溶かす絶頂の至福の一体感・陶酔感と、避妊の成功を前提に行われるセックスによる肉体的性欲の利己的・動物的満足感(孤独なマスターベーションと大差ない)との間に月とすっぽんほどの違いのあることは、経験したものにしかわからないだろう。(1968年、時の教皇パウロ6世はカトリック信者の人工的産児制限を禁止する回勅「フマネ・ヴィテ」を発表したが、全世界の教会指導者たちは、教皇の言うことは実践不可能として無視し、葬ってしまった。しかし、その後任の聖教皇ヨハネ・パウロ2世はそれが真面目に受け取られることを望み、そのために腐心された、という経緯がある。)
結果は、多い家族は10人以上の子宝に満ち、平均でも5人ぐらいにはなるだろう。そして、親が自分の持っているものの中で最高のもの、「命よりも大切な宝」を子供たちに受け渡すために最善を尽くすなら、つまり、命より大切な「信仰」を確実に子供たちに伝えていくことに成功すれば、それだけで一世代、30年以内にカトリック人口の減少傾向は止まり、やがて際立った増加に転じるだろう。また、復活したイエスが弟子たちに現れて、「全世界に行って、すべての造られたものに福音を宣べ伝えなさい。」(マルコ16章15節)と言われた命令を、彼らが忠実に守って、「物見の塔」の信者さんや「エホバの証人」の信者さんたち顔負けの熱意で、宣教活動のために街頭に打って出るならば、キリスト教を信じる人の数は飛躍的に増えていくに違いない。
しかし、このような信仰の生き方は、他方では「自然宗教」の仲良しクラブの中では付き合いにくい異分子として摩擦の種になるだろう。そんな時、イエスは言う。「世があなたがたを憎むなら、あなたがたを憎む前にわたしを憎んでいたことを覚えなさい。」(ヨハネ15章18節)さらに、「『僕は主人にまさりはしない』と、わたしが言った言葉を思い出しなさい。人々がわたしを迫害したのであれば、あなたがたをも迫害するだろう。」(ヨハネ15章20節)
彼らには迫害に対する心の準備がある。「悪人に手向かってはならない」(マタイ5章39節)と聖書にあるから、迫害者と対決することはないが、逃げても、隠れても追い詰められて囚われれば開き直る。拷問や殉教が恐ろしくない人間などどこにもいないが、彼らは容易に転ぶこともしないだろう。「沈黙」はそこで、「殉教者は強者」で「転ぶものは弱者」、神は弱いものにこそ憐れみをかける、というような理屈を展開するかもしれないが、それは聖書的ではない。人間的に見て、殉教するものがころぶものより強いとは言えない。復活の確信、天国への希望は確かに支えになり、強めてもくれるだろうが、それは彼ら自身が強い人間であるという意味ではない。それは人間の力ではなく、上から注がれる信仰の恵みなのだ。信仰の恵みによらなければ誰一人として殉教などできるものではない。この神からの恵みは、苦しみを和らげ、耐えきれるものに変えて下さるだろう。さもなければ誰も最後まで耐えられるものではない。ころぶ人は、信仰の恵みと神からの助けを信じない。神の助けと力添えを期待もしない人間が、人間的プライドの強さにだけ頼り、その限界に達したときに転ぶのだ。その意味で、強い人こそ転ぶといえる。キリストにあやかり、キリストに似たものとなること、つまりキリストのように死ぬこと、を光栄としない者、無上の喜びとしない者にとって、神の恵みも助けも役に立たないということか。
私はキリストの「復活」を本当に信じる人々の小さな共同体に希望をつなぎたい。自分自身「キリストが復活したこと」を信じ、自分も「死」に打ち勝って復活することを希求し、その希望にすべてを賭ける人生を送りたい。
私は日本に帰ったら ―早く帰りたい!-20人、30人の同じ信仰を共有できる仲間と共に「キリストの復活の証し人」の共同体を作ることができれば、それで満足だ。
私は世界中にその萌芽をすでに見ている。教皇フランシスコのおひざ元のローマでも小さいながら始まっている。ひょっとして日本でもすでに?
生きているうちにその「希望」の証しを見たいものだと思う。
(このシリーズ終わります)