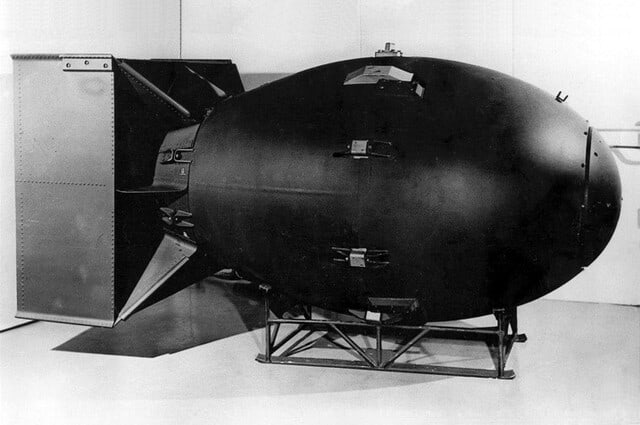~~~~~~~~~~~~~~~
インドの旅から
第3信 香港の夜と国境の村
~~~~~~~~~~~~~~~
私は、連載中の「インドの旅から」をしばらく脇に置いて、時間の隙間を見つける毎に、若松英輔著「霧の彼方 須賀敦子」と言う470ページ余りの評伝を、憑きものにつかれたように読みふけり、今しがたやっと読み終わったばかりで、まだいささか興奮している。

須 賀 敦 子
50年以上前に、私の「インドの旅から」が「聖心の使徒」と言うカトリックの布教雑誌に連載されていたことは既にふれた。そしていま、まるで秋の夜空に突然まばゆい光を放って現れ、あっという間に闇の中に消えていった超新星のように、たった7年だけ日本の文壇に輝いて、惜しくも世を去っていった須賀敦子が、同じころ同じ月刊誌に様々な記事を寄稿していたことは、浅からぬ因縁に思えた。
当時、私は25歳の大学院生。須賀敦子は私より10才年上で、イタリア人のペッピーノと結婚してミラノに住んでいた。私は以前からこの雑誌の発行者であるチースリック神父に勧められて毎月の「布教の意向」という小さな記事を連載していたから、神父やその秘書の須山緑女史とは昵懇にしていたが、二人から須賀さんの話を聞くことはなく、一緒に〔目次〕に名を連ねている須賀さんの存在に、私の側から関心を寄せることもなかった。まだ私が未熟だったせいか、まだ機が熟していなかったのか、多分その両方だったのだろう。
しかし、いま、彼女の全集をむさぼり読み、若松英輔の書いた評伝を一気に読み終わって、私が知らずして須賀敦子の足取りを自分の人生で辿り、生きる信条を同じくしていたことを知って、限りない親近感を覚えている。共通点は、彼女の言葉を借りて言えば「カトリック左派」ということだろうか。
須賀敦子と遠藤周作はパリで、また日本で、互いに接点があったようだが、遠藤は代表作「沈黙」で「棄教者、背教者」をテーマに描いて、教会の内外に深刻な影響を残したのに対して、もし須賀がキリシタン時代を描いていたら、きっと「殉教者」をこそテーマに選び、真反対の世界を展開していたに違いないと思われる点でも、思考の同質性を覚える。そして、須賀の魂の指向性と、未熟の極みながらも私の「インドの旅」の通奏低音が、須賀がパリに、ミラノに見出したものと、どこかで響きあっているように思えて、不思議な縁を感じながら、いま「第3信」を書こうとしている。
2021年は東京オリンピックだが、1964年も第1回東京オリンピックの年、北京条約で九龍半島南部の市街地があらたにイギリスに割譲されてから4年目、世界はベトナム戦争のさ中にあった。

インドの旅から
第3信 香港の夜と国境の村
O君、ぼくの恋人「ラオス号」は、今しがた香港を後にしました。生々しい思い出をいっぱい積み込んで。
まず順を追って話しましょう。
香港の第一日目は、朝、船が着くとすぐ飛び出して、町の隅から隅まで、そして田舎の漁港の小舟の溜まりの中までも足を伸ばして見て歩きました。それこそ、この視力2.0の両眼に、ありとあらゆるものを吸い取って、ぼくの去った後には何も残っていなかったと言えるほどに。
そしてその夜、名高い香港の夜景を、六甲山から見た神戸のそれと比べるために、あの一風変わったケーブルカーに乗って、一人ゴトゴトピークへ上がってみました。
都会の夜が美しく見えるなんて、人間の視覚も案外いい加減なものだと思いながら、ケーブルの駅にもどってビックリ、ポケットにお金が無い。正確に言うと、ポケットに香港ドルが残っていなかった。駅で米ドルを替えてくれの、レートが安すぎるのと、スッタモンダやっている所へ、アメリカの水兵さんが二人やってきた。
二人が「そんなの俺たちに任せてついておいで」、と言うので、ケーブルで下りて、車で海軍のクラブまで行き、それから誘われるままに一緒に飲み歩くことにした。水兵を二人も護衛につけていれば、まず間違いはなかろうと思ったわけだ。バーやナイトクラブをはしご飲みして、自分もほんのり良い気持ちになった。どこもかしこも乱痴気騒ぎの水兵でいっぱいだったが、この二人はジャズに浮かれて踊り出すでもなく、ビールをかたむけながら淡々と話し続ける。
総員わずか28人の老朽潜水艦のクルーになってからは、岡に上がってもこうして飲み歩くことのほか、何も思いつかなくなったと言う。生活は乱れがちだし、勉強を長く離れているので、兵役が終わっても学校に入り直すのはむずかしい。かといって就職もなかなか思うに任せない。ついずるずると職業軍人になってしまう。その点、日本の学生はうらやましい、と言った。
悲しいことだと思った。年を聞いたら僕より二つも若かった。どう見ても三つ四つは年上に見えるのに。身分証明書の間から、若い母親と可愛い妹さんの写真をひっぱり出して見せてくれた。代理戦争(ベトナム戦争)のヒーローのこのアメリカ青年も、幸せではないんだな、と思った。
真夜中を過ぎたので別れを告げて、一人人力車に乗って船にもどった。肩で息をしながら引いてくれた車夫の、はだしの足の細かったことと言ったら・・・。もう人力車には乗るまい、と思った。
x x x
香港の二日目、歴史の現実を見るために国境へ向かった。九龍(クオンロン)駅からディーゼル機関車に引かれてシナ大陸へ。
トンネルを抜けると、入江の青と山の緑が目にしみる。サングラスをとると美しい田園と貧しい漁村の長閑で平和な景色が広がる。干し魚の臭いとアヒルの声が風に乗ってくる。車内は、生きたニワトリをぶら下げたおばさんや、子供たち、セーラー服の女学生らで 混んでいる。
昨日の香港の夜の強烈さにくらべて、今日はまるで小学生の遠足のような楽しさだ。
ファンリン(粉嶺)駅を過ぎるころから乗客が減りはじめ、ほとんどの客シェンシェイ(仙水)駅で降りてしまった。
車内のざわめきが消え、がらんとした中に一人残されると、急に引き締まった気分になる。
足音がして、ブリティッシュ・ホンコンのポリスが険しい顔で近付いてくる。
「許可証はあるか?」
「許可証?」
仙水からこちらは、たとえそこに住んでいる人間であっても、ライセンスなしには出入り出来ぬと言う。いつの間にか国境の両側に設けられたクローズド・エリアに入ってしまったらしい。ひと悶着の末、即刻引き返すことで話がついた。
国境の駅、ローフースタに着いた。駅全体がすっぽり金網で囲まれている。プラットホームの向こう五十メートルの上を、半円の赤い屋根が覆っていて、その両側にはブリティッシュ・ホンコンの旗と中共の旗がニラメッコしている。駅に詰めている白人や黒人のポリスメンを見たとき、「これは深入りし過ぎたかな?」と思った。
写真を撮ろうとしたのが見咎められて、またひと悶着、しかし、天の助け、フイと現れた日中旅行社のKと称する人の計らいで、調べも受けず、カメラも取り上げられずに事なきを得た。
K氏は急ぐからと言って消えたが、この騒ぎのお陰でポリスたちと仲良くなり、汽車が折り返すまでの間、彼らと詰め所でいろんな話が出来た。
「お前のような怖いもの知らずののんき者は見たことがない」と言う。知らないということは実に有難いことだ。おかげでみんなの見ないものを見た。
「今でも時々トラブルがあるのか。」と聞いたら、「そんなこと言わせる奴があるか。」と目をむいた。
ようするに、ここが国境の村そのものずばり。ここだけが中共へ汽車を乗り入れられる最も緊迫した拠点だということだけは確からしい。両側の丘の上には監視所があり、軍用道路が四通八達し、人の動きもどことなく違う。
英国人のポリスがそっと耳打ちして、「ここは警戒がきびしいので自由に見ることは出来ないが、もっと見たければ、仙水駅から車で国境に近づくことが出来る。」と教えてくれた。
仙水までとって返す。そこのポリスに「ボーダーはどこか。」と聞いたら、首を振って手で帰れと合図する。話しても無駄だと思って歩きはじめると、思ったとおり、「ヘイ、ミスター、トゥエンティーファイブ・ダラー」と声がかかった。18ドルまで値切ってその男の車に乗る。
立派な道を飛ばしていくと、両側に兵隊の家族の家、将校の家。ジープの溜まりなどがある。道が二つに分かれて、五メートル先に踏切の遮断機のようなものが行く手をさえぎる。英語とカントン語で威嚇的なことばが並んでいる。クローズド・エリアの入り口だ。そこを右に折れて丘の上に出ると、急に視界が開けた。
足下の浅い流れに沿って、鉄条網の白く光るフェンスが果てしなく続く。そのこちら側には、藁ぶきの掘立小屋が並んでいて、アヒルが群れ、のどかな感じだ。しかし、人気の無いのが気にかかる。向こう側には同じ造りの農家が一軒ポツンとあるきりで、はるか向こうの丘までは、水田と浅い池のほかは何もない。
昔は向こうにも農家がたくさんあったのだが、赤軍が全部取り払って、残る一軒も実は中共兵の詰所だと言う。二、三年前までは日に何度か銃声を聞いたものだそうだ。
向こうの丘には低いアパートがポツポツと見える。これは中共がデモンストレーションのために建てたもので、香港で四日に一個の割合で建てられている二十数階建てのアパートや、九日に一個出来上がる学校に比べれば物の数ではない。香港はそれでも難民を収容しきれないでいる。
中国人の女がいたので写真を撮ろうとしたが、モデル料一ドル聞いて興ざめしてやめた。クローズド・エリアの境まで引き返したところで、遮断機の向こうから女の子が水桶を下げてやってきたのでレンズを向けたら、子鹿のように干し草の陰に隠れてしまった。
悲しい気持ちになった。
仙水からの帰りはバスにした。バスの中で考えた。
実際と言うものは、話に聞いて想像しているものとは大分違う。本で読み、人に聞いた話は大概色が付いている。だからそれを鵜呑みにする前に、本当にそうなのかどうかを実際に当たって調べてみる必要があるのではないか、ということだ。
別にみんな香港へ来い、ベトナムに行けといっているのではない。それはもっと身近な話だ。
「あいつは、あのクラブは、あの種の本は赤だ」と片付ける前に、そこで叫ばれている暖かいヒューマニズムに肌で触れていくべきだ。「私はプロテスタンティズムについてこう教えられた。」と言う前に、彼らは今、何を訴えているのかを見るべきだ。「あの神父はぼくの思いを理解せず、ぼくの言葉に理屈で反応したから」と言って、それだけで全てを片付けてしまうのはあまりにも残念だ。
ぼくたちが、観念や、主義や、教説にではなく、この物質的な世の中の実際と、言葉のかげに人が伝えようとした生きた心に愛を込めて寄り添えるようになったら、新しい一致を生み出すことも不可能とは言えなくなるのではないだろうか。
やっと一つの考えに辿り着いたから、今回はこの辺で終わろう。
次の便りは多分ベトナムからだ。船中のことも伝えよう。
みんなによろしく。サヨウナラ

あれから半世紀余りが過ぎた。香港は今、反逃亡犯条例修訂デモに象徴される大きな転機を迎えている。こんなこと、半世紀前に誰が予想しただろう。

ウイキペディアから借用
昨年は、教皇フランシスコが来日してその設立を祝福するはずだった「教皇庁立アジアのためのレデンプトーリス・マーテル神学院」、またしても日本の司教団の反対で、タッチアンドゴーよろしく空に舞い上がり、その後マカオに着陸した。
その新しいマカオの神学校も、今は、新型コロナウイルスに追われて、台湾に避難している。香港の次にやられるのは台湾か、マカオか。中国の覇権主義のあおりを受けて、アジアの福音宣教は、まだまだ苦難の道を歩むことになるだろう。

東京ドームで教皇フランシスコ
少子高齢化の波に呑まれ、カトリック教会の信者は年々確実に高齢化し数をへらしている。子供たちに信仰は受け継がれず、新たに教会の門を叩き入信する人も稀な状態だ。教会の自然死に向かう衰退は加速の度を強めている。だが、これは何も日本に限ったことではない。先進国と言われた国々はどこも50歩100歩に状態にあえいでいる。
しかし、ペトロの船と呼ばれる教会は、貧しい無学な田舎漁師に委ねられながらも、2000年余りの歴史の暴風に耐えて、絶えず刷新を繰り返しながら、今日に至った。この罪人の集団である貧しい船は、それにも拘らず、聖霊に守られ導かれて、何億年先の世の終わりまで、宇宙の果てまで、必ず航海をつづけるに違いない。これが私たちの信仰だ。