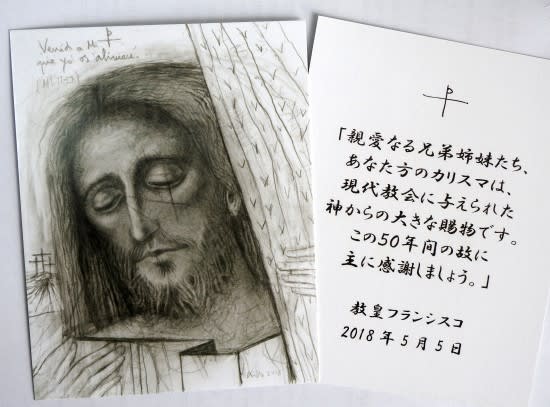~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
アジアのための「レデンプトーリス・マーテル」神学院
の「誤解」を解く(そのー1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

私がかつて表題のブログをアップしたら、まもなくローマから「お前のブログには重大な問題が含まれているという嫌疑が掛けられているが、いったいどうなっているのか」と言うような、全く身に覚えのないお咎めが届きました。日本から何らかの告発がローマにまで届いたのでしょう。それもかなり高いレベルから高いレベルへ。
さて、それからが大変でした。私のブログが過去にさかのぼってローマの意向を体した日本語のわかる検察官みたいな人達によって、徹底的な取り調べが始まったのです。どんなお咎め、処分が来るかと超緊張し観念しました。ちょっと大げさですが、中世の異端審問か魔女狩りにあった気分でした。ところが、それから3か月余り、何のお咎めも届きませんでした。
そればかりか、「心配するな、お前の書いたことは当たり前のこと、何も問題はなかった」というねぎらいの声さえも届きました。それまで、生きた心地がしなくて、身を縮めていましので、ホッとしました。
日本の常識は世界の非常識、世界の常識は日本の非常識、と言う古い言いまわしがふと心をよぎりました。
心晴れて、いったん削除したブログをほぼ文字どおり再現して、あらためてアップしたいと思います。

わたしは、「アジアのためにレデンプトーリス・マーテル神学院」の目的は、「新求道期間の道の信徒を、アジアにおける福音宣教のための司祭として準備することにある。」という言葉の解釈には、多くの場合、微妙な誤解と誤りが含まれていることに気付きました。
「誤解」というのは、「・・・だから、この神学院は《新求道期間の道の司祭》を養成する神学院である」と結論づける声のことです。そもそも、《新求道期間の道の司祭》と言うものは有り得るのでしょうか?
元来、司祭には大きく分けて「教区司祭」と「修道司祭」の2種類しかありません。東京教区司祭、長崎教区司祭とかが前者で、イエズス会司祭、フランシスコ会司祭、サレジオ会司祭、などが後者です。この分類は教会法上の司祭の帰属(Incardination=司祭籍)に関するものですが、上記の「アジアのための神学院」から生まれる司祭も、「教区司祭」か「修道会司祭」のどちらかしかあり得ないのです。
「新求道期間の道」は「司教区」や「修道会」のような組織または団体としての性格を持たず、それはあくまでも「道」であり、「道」であるかぎり、人々が通り過ぎていく両端の開いた細長い通路のような性格のもので、教会法上は固定メンバーを持った輪郭のある閉じられた団体として位置付けられていないからです。
組織でも団体でもなく、法人格もない「道」と呼ばれるバーチャルな存在に司祭が帰属する(籍を持つ)ことは教会法上あり得ません。ですから、たとえ召命は「道」を歩む子沢山の家庭から生まれるとしても、彼らが「教区司祭」や「修道会司祭」と並列される意味での「新求道共同体の司祭」になると言うことは原理的にあり得ません。
また、「新求道期間の道」は、新しい大阪の補佐司教になられた酒井神父様が所属するオプス・デイのような「属人区」でもありません。「新求道期間の道」は、カトリック信者が「成人のための信仰教育」を受ける過程、信仰を深めるための方法論、つまり幾つも有り得る「道」=信仰教育課程=の一例にしか過ぎないのです。
例えば、私はれっきとした教区司祭です。そして私の教会法上の帰属先(籍)は依然として高松教区と言う堅固な存在であって、決して「新求道期間の道」と呼ばれる輪郭の無い雲のような存在の司祭ではありません。
1990年に深堀敏司教が聖教皇ヨハネパウロ2世に励まされて高松教区に教区立の神学校を設立されて以来、30人余りの司祭が生まれましたが、全員深堀司教様から司祭叙階を受けて「高松教区」に入籍したれっきとした「教区司祭」です。従って、彼らを「新求道期間の道の司祭」と呼ぶのは明白な誤りです。
この高松教区立の神学校が教皇ベネディクト16世の手でローマに移植されたとき、名前は「日本のためのレデンプトーリス・マーテル神学院」と変わりましたが、それ以後、高松から移り住んだ神学生たちはローマで勉強し、司祭になるときはローマ教皇の手で叙階され、多くは「ローマ教区司祭」として入籍しました。入籍後は原則3年間ローマ教区で奉仕しますが、その期間が過ぎれば、宣教地(例えば日本やアジアの他の国々)に「ローマ教区司祭」の身分のまま派遣されることができます。このようにして養成された日本のための司祭の数は、高松時代を加えるとすでに40名を超えています。
しかし、最近では、ローマ教区でも司祭不足が深刻化して、「日本のためのレデンプトーリス・マーテル神学院」の出身であっても、一旦「ローマ教区司祭」として入籍してしまうと、ローマ教区に縛り付けられて、なかなか日本やその他の宣教地に出してもらえない現実が顕在化しました。
そのため、養成が終わるとローマ教区への入籍を避けて、それぞれの出身国、出身地の司教様にお願いして、一旦は故郷の教区に教区司祭として入籍し、叙階後直ちに宣教師として日本などの宣教地に派遣してもらう道が開かれました。
この度、「アジアのためのレデンプトーリス・マーテル神学院」が予定通り東京に設置されれば、神学生の司祭職への養成が終わると、教皇庁の福音宣教省はその責任においてその神学生を叙階して一旦は自分の教区の教区司祭籍に受け入れ、叙階後は日本などアジアの宣教地に宣教師として派遣してくれる世界各地の理解ある司教様に司祭叙階をゆだねることになるはずです。
もし日本のどこかの司教様が、ある神学生に目をとめ、彼を自分の教区の司祭として迎えたいと望まれるなら、教皇庁と話し合ってその新司祭をその司教様の教区に入籍することも可能だろうと思います。教皇庁は日本の教会や他の宣教地の司祭不足、司祭の高齢化、召命の枯渇などの緊急の課題に対応する特効薬として、この神学院の設立を決断されたのでしょう。
フランシスコ教皇の心には、約40万人の日本人カトリック信者の司牧をどうするかという内向きの心配だけではなく、60万人以上とも言われる在日外国人カトリック信者のケアーや、1億2700万人の神をまだ知らない日本人への福音宣教をどうすべきかと言う大きな課題が視野にあるのだと思います。目的は、内向きに現有信者を司牧することに専念する司祭ではなく、外に向けて打って出る宣教精神に燃えた「教区司祭」の養成であると考えられます。
一方では、世俗主義に犯された少子高齢化社会において、一般のクリスチャンホームからはそのような司祭職への志願者がほとんど育っていないという厳しい状況があります。他方では、子沢山の家庭からなる「新求道期間の道」が豊かな召命を生み出しているほとんど唯一の源泉だと言うのも現実です。
新求道期間の道の信徒たちは、その道を歩む過程で次第に福音的に目覚め、「回心」し、夫婦が和解してあらためて愛し合い、夫婦生活の営みが神からの新しい生命の恵みに対して寛大に、おおらかに開かれようになり、4人、5人は当たり前、8人も10人も13人もの子供を産み育てることも決して例外でない状態に導かれていくのです。そのような新しい福音的家庭に対する神様の祝福と恵みとして、司祭職への豊かな召命が芽生えるのです。
フランシスコ教皇が東京に設置することを考えられた「教皇庁立の神学校」で行おうとしているのは、日本とアジアの福音宣教の熱意に燃えた「教区司祭」を生み出すために、「新求道期間の道で育まれた若い青年たちの豊かな召命」をこのレデンプトーリス・マーテル神学院に受け入れ、「教区司祭として」養成しようと言うものと理解すべきだろうと思います。
箱ものとして神学院を設立することは簡単ですが、それを宣教の熱意に燃えた若い神学生で満たすことはほとんど不可能に近いのが今の世界の実情です。第二バチカン公会議の決定を信仰生活の原点として受け入れかねて、古い信仰生活にとどまっている家庭の子供の数は、一家庭当たり平均1.4人と言われます。だから一家に男の子が一人いたら「神に感謝」の実情です。その子を生涯独身で通す司祭として神様に捧げようと言う発想はその親にはありません。親の遺産は自分のもの、そのかわり親の老後を看る者も自分しかいない、と言うマインドセットが幼い頃から刷り込まれている若者に、福音的勧告を受け入れて、「親も家も捨てて生涯独身の司祭としてわが身を神に捧げる」などという発想は全く湧いてこないのです。
冗談のようですが・・・長兄は東大を出て官僚になった。次男は医者になった。三男はオペラ歌手になると言う。うーん、四男の僕は何になって存在をアピールしようか?そうだ!神父になろう!神様に身を捧げて宣教者になろう!!と言う「乗りの良さ」が、子沢山の家庭の豊かさをよく表しています。
聖教皇ヨハネパウロ2世がレデンプトーリス・マーテルの神学院の第1号を原型として「ローマ教区立」として設立して以来、この30年余りの間に世界中に展開された120以上の姉妹校が、情熱にあふれる若い神学生たちで満ちている現実は、この「新求道期間の道」と言う肥沃な召命の苗床なしには考えられません。
その名誉ある第7番目の姉妹校として1990年に設立されたのが、「高松教区立レデンプトーリス・マーテル国際宣教神学院」でした。聖教皇ヨハネパウロ2世の励ましを受けて日本最小の教区の深堀司教が慄きながらそれを設立する姿を私は自分の目で見ました。この神学院が危機に瀕したとき、この神学院の消滅を望まれなかったベネディクト16世教皇が、それをご自分のものとしてローマに移されました。そして、フランシスコ教皇はそれを「アジアのためのレデンプトーリス・マーテル神学院」として日本とアジア全体のために東京に返そうとされたのです。
思い返せば、高松の神学校の初代の院長ミゲル・スアレス神父はスペイン人の「イエズス会士」(修道会司祭)でした。今、実質上の院長職を担っているアンヘル・ロメロ神父はスペイン人の「ローマ教区司祭」です。いずれも身分としては「新求道期間の道の神父」ではありません。
つまり、「新求道期間の道の神父」と言うものは教会法上存在し得ないのです。
お分かりになられたでしょうか?
誤解は少しは解消されたでしょうか?
いま、諸般の事情で同神学校の東京設立が「保留」になっていますが、この秋のフランシスコ教皇訪日を控えて、その成り行きから目が離せません。

(つづく)