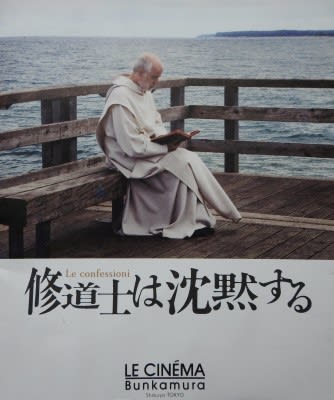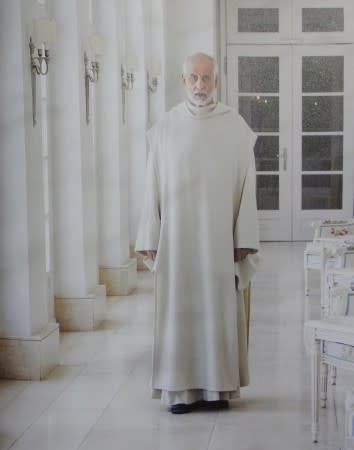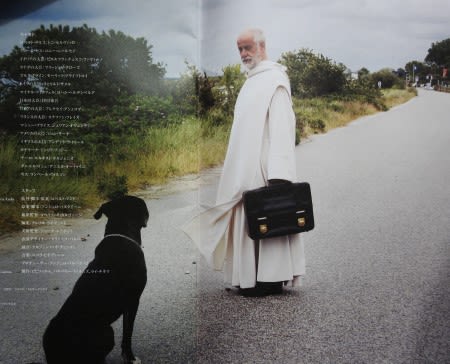~~~~~~~~~~~~~~~~
【映画】ペンタゴン・ペーパーズ
—最高機密文書―
~~~~~~~~~~~~~~~~
(鑑賞後に手にしたプログラムから自由に要約引用しながら感想を展開しよう)
【監督】
スティーヴン・スピルバーグ

【主演】
メリル・ストリープ

トム・ハンクス

アメリカ合衆国憲法修正第1条は、
「連邦議会は、国教の樹立、あるいは宗教上の自由な活動を禁じる法律、言論、または報道の自由を制限する法律、並びに人々が平穏に集会する権利、および苦痛の救済のために政府に請願する権利を制限する法律を制定してはならない。」と規定している。

ニクソン政権は、ベトナム戦争に関する最高機密文書「ペンタゴン・ペーパーズ」の掲載差し止め求めて、ニューヨーク・タイムズを訴えたが、判決は以下の通りだった。
ニューヨーク・タイムズ対アメリカ合衆国の裁判403 U.S. 713
ヒューゴ・ブラック判事による判決の抜粋
合衆国建国の父は、憲法修正第1条をもって民主主義に必要不可欠である報道の自由を守った。報道機関は国民につかえるものである、政権や政治家に仕えるものではない。報道機関に対する政府の検閲は撤廃されており、それゆえ報道機関が政府を批判する権利は永久に存続するものである。報道の自由が守られているため、政府の機密事項を保有し国民に公開することは可能である。制限を受けない自由な報道のみが、政府の偽りを効果的に暴くことができる。そして、報道の自由の義務を負う者は、政府の国民に対する欺きによって多くの若者もが遠い外国へと派遣され、病気や戦闘で命を落とすと言う悲劇を避けるためには責務を全うすべきである。私の考えでは、ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポスト、そしてその他の新聞社が行った勇気ある報道は決して有罪判決に値するものではなく、むしろ建国の父が明確に掲げた目的に報いる行為として称賛されるべきである。この国をベトナム戦争参戦へと導いた政府の行為を明るみにすることで、前述の新聞社は建国者たちがこの国に望んだことを立派に実行したのである。

ニューヨーク・タイムズによって暴露され、その存在が世界中の知るところとなった政府の最高の機密文書「ペンタゴン・ペーパーズ」。
その機密文書の報道は、政府が負け戦だと理解していたベトナム戦争に身を投じた大勢の兵士を含む、アメリカ国民の未来がかかっていた。危機的状況の中、ワシントン・ポストの発行人キャサリン・グラハム(メリル・ストリープ)は、これまで家族で築いてきた財産と、ジャーナリストとしての精神とを秤にかけることになる。一方、ワシントン・ポストの編集主幹、ベン・ブラッドリー(トム・ハンクス)は、国家に対する反逆罪に問われる危険性を理解した上で、真実の追及を社のメンバーに課していた。そうして2人は勝ち目がないと思われた政府との戦いの中で、民主主義国家として報道の自由を掲げる憲法を守るために団結していく。

1966年、ベトナム視察からアメリカへ戻る国防長官ロバート・マクナマラは、メディアから勝利への展望を聞かれると、状況は「飛躍的に進展している」と答える。
それを見て、自らマクナマラに泥沼化するベトナム戦争の現実を報告した男(ダニエル・エルズバーグ)は自らアナリストを務めるランド研究所から機密文書をコピーしてニューヨーク・タイムズ社にリークする。その中には歴代4人の大統領がベトナム軍事行動について何度も国民に虚偽の報告をし、暗殺、ジュネーブ協定違反、連邦議会に対する嘘と言った闇の歴史の証拠が記されていた。ベトナム介入から撤退まで、58,220人のアメリカ青年が戦死し、100万人以上の人命が犠牲となる直接の原因を作った。ペンタゴン・ペーパーズによってその原因となった政府の嘘が暴かれたのだ。
ニクソン政権は国家の安全保障を脅かすとして、ニューヨーク・タイムズに対して記事の掲載の差し止め命令を連邦裁判所に要求した。同紙が差し止め命令を受けた中、今度はワシントン・ポストがペンタゴン・ペーパーズを掲載した。今度は、連符裁判所はニクソン政権の恒久差し止めの訴えを却下した。判決は最初に紹介した通りだが、ワシントン・ポストの女性社主キャサリン・グラハムが起訴され、受ける恐れのあった有罪判決は合計115年の刑期だった。しかし、政府による深刻な不正行為があったとして、エルズバーグの裁判は審理無効となった。エルズバーグが密かに手にしたのは7000ページに及ぶ合衆国の最高機密だった。

ニクソン相手の裁判でキャサリンが有罪になる可能性は現実にあった。夫が自殺するまでただの主婦だったキャサリンが、ワシントン・ポスト社に経営者になって直面したこの重大な局面で、編集主幹のベン・ブラッドリーとの緊密な連携を通して、たくましく成長していく。ワシントン・ポスト社内の慎重論を抑えて掲載に踏み切った彼女の信念は「報道の自由を守るのは報道しかない。」であった。
幸いにも裁判は6対3票で報道の良心の側に組した。キャサリンは投獄と、破産と、ワシントン・ポストの消滅との危機を回避しただけではなく、それを2流の地方紙の座から、全米有力紙の地位に押し上ることになった。
*********
有名なスチーブン・スピルバーグ監督が通常では考えられないスピードでこの作品の制作を進めた背景には、トランプ政権下の合衆国で、ニクソン時代を思わせる「嘘」がまかり通っている現実に対する危機感があったと思われる。私が一刻も早くこのブログを完成したいと思ったのは、森友・加計問題、15,000ページのイラク日報問題、アメリカのシリア攻撃など、内外の情勢が急迫していることによる。
日本の政治がこれほどまでに嘘にまみれている事実を、もはや国民は座視できない。日本の新聞は、テレビは何と鈍感で生ぬるいことか。一強独裁者を恐れ、報復に怯え、率先して忖度(そんたく)を重ねているとしか思えない。まごまごしているうちに、政権は都合の悪い放送法を改悪しようとさえしているではないか。アメリカは、こと言論の自由に関しては、日本よりはるかに進んでいる。
今朝の福田淳一財務相事務次官のセクハラ辞任の件も、自社の女性記者の問題を自社の責任で報道できなかったあたりに、日本の報道機関の信念の無さが露呈している。ワシントンポストの女性社主の裁判に負ければ投獄されるリスクを取ってでも政府と戦うという、社運をかけた賭けに出る報道人魂がテレビ朝日にはなかった。
最初に紹介したアメリカの合衆国憲法修正第1条と対比できる日本の平和憲法の最も価値ある条項は国際紛争の解決手段としての「戦争放棄」の一文だと言っても過言ではない。これは、第3次世界大戦の未曽有の悲惨のあと、世界の国々が進んで採用することになる未来の憲法の常識を予言的に先取りしたものだ。アメリカの押し付けでも何でもない。日本人が広島・長崎の教訓として納得して選び取ったものではなかったのか。トランプのような狂人と、日本の政府のような嘘にまみれた指導者のもとでは、中近東であれ、朝鮮半島であれ、明日にも世界規模の戦争の危険が差し迫っていることに対する危機感を研ぎ澄まさなければならない。そして、日本の主権者である市民が底辺から声を上げなければならない。それも、急いで!

私は、1970年ごろ、ベトナムの前線で壊れた戦車が相模原の工廠で修理され、再び戦場に送られるのを阻止するため、横須賀に向かう戦車の前に上半身裸になって熱いアスファルトの上に寝転がったことがあった。パリに亡命していたベトナム人のグエン・ディン・ティ神父と仏教の尼僧をパリから招いて、裁判もなく不当に長期拘留されていた大勢の政治囚の釈放を訴えての全国講演旅行に、ボディーガードと通訳を兼ねて同伴したことがあった。反戦の活動に身を投じたベトナム人留学生たちの支援をして、彼らと熱い友情を結んだりもした。今はすべて懐かしい青春の思い出となっている。
その後、私が現役だったリーマンブラザーズの当時の会長ピーター・ピーターソン博士は、ニクソン政権の商務長官、後のソニーの社外重役だ。リーマンのシニア―パートナー、重役のジェイムス・シュレッシンジャーはペンタゴン(国防総省)の国防長官だった。私は、彼らをピート、ジム、とそれぞれ呼び捨てにして、親しく言葉を交わす機会を持った。ホワイトハウスとペンタゴンとウオールストリートは、地上の世俗社会における最強、最悪の三位一体だと言っても過言ではない。
しかし、真の三位一体は、キリスト教の神にのみ当てはまる神聖な属性であることを忘れてはならない。
(終わり)