地方志向の若い世代 島根県の中山間地域・識者に聞く④ 農村の役割を重視して
地方再生のために必要なのは、農村の役割や機能を発揮することだと、島根大学の保母武彦(ほぼ・たけひご)名誉教授(地方自治論)は語ります。
島根大学名誉教授 保母武彦さん
地方再生を考えるうえで重要なことは、地方分権を中心に据えることです。ところが、安倍晋三政権は「地方創生」を唱えながら、地方分権と自治の原則をないがしろにしたやり方で進めようとしています。
政府は、中山間地域や離島の小さな自治体は「消滅」すると脅して、地方に人口20万規模の「地方中核拠点都市」をつくり、財政と施策を集中させ、東京に行かなくてもいいように、仕事の場をつくるといいます。
しかし、そうなると、政府は、農村部に回すべきお金を引き揚げて、その中枢都市に集中することになります。活性化どころか、農村部の疲弊をさらに促進させる政策です。
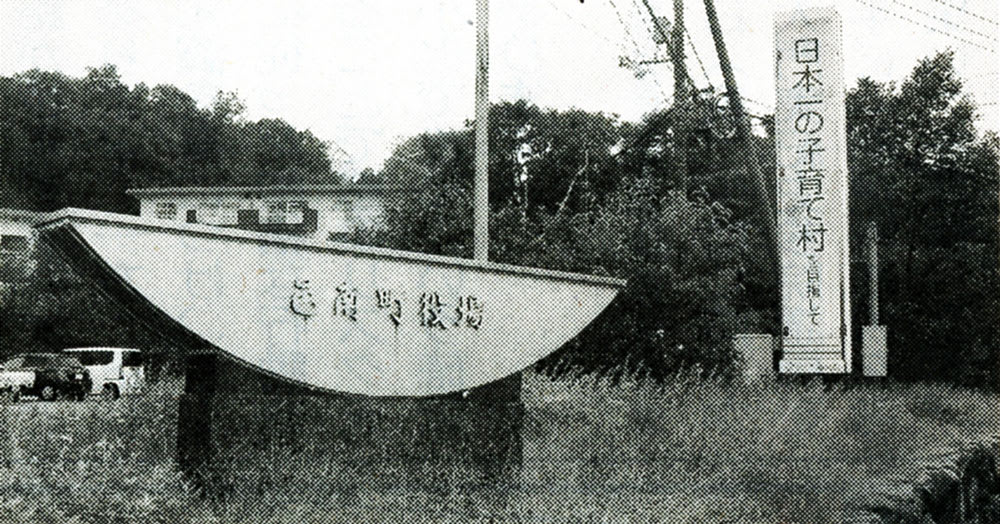
「日本一の子育て村」の看板を掲げる邑南町役場
豊富な資源提供
農村部の人口減少問題の根本にあるのは、農業を自由競争の原理に引き戻した自民党政治に突き当たります。しかし、政府にその反省と総括はまったくありません。地方再生をいいながら、農村の役割や機能の発揮を重視していません。
一つは日本の食料問題です。食料は輸入依存を強めています。世界的に飢餓人口が増えるなかで、食料をどう確保をするのか。自給率の引き上げが喫緊の課題になっています。米づくりが農村を支えており、現在の米価暴落への対策は急を要します。
もう一つはエネルギー問題です。原発ゼロを目指して再生可能エネルギーを増やす上で、農山村は豊富な資源を提供してくれます。再生可能エネルギーを増やすことは、貿易収支の改善にもつながり、輸出の拡大と同じ効果が得られます。
例えば、北海道の下川町では、木質バイオマスを中心に再生エネルギーで熱と電力の完全自給体制を確立しつつあります。それにより、町内の雇用を増やし、灯油代、重油代、電気代を町外へ支払うことなく、地域経済の活性化や子育て環境を整えます。
ヒント足もとに
島根県の邑南(おおなん)町では、地域の食材を生かした取り組みや保育医療費の無料化など子育て対策を進めており、飯南(いいなん)町では定住者向けの住宅対策や相談活動などに力を入れています。
地域の核になる公民館の活動も活発に行われています。それができるのは、20万人、30万人の地方中核都市ではなく、自然と人情が豊かな農村部だからです。
人を育てる「人づくり」も大切です。島根県の離島、海士(あま)町は、人口約2300人の町ですが、Iターンが9年間で438人にのぼります。若い人が生きがい、働きがいを求めて集まっています。ソニーやトヨタの正社員だった人もいます。大きな会社では自分が世の中にどう役立つのかがなかなか実感できない、連帯感が持てないなど、働きがいが持ちにくい社会になっていることが背景にあるのだと思います。
地方再生のヒントは地方の足もとにあります。上から目線では成功しません。
(おわり)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2014年10月26日付掲載
住民一人ひとりの顔が見える農村部、一人ひとりが主人公になって生産をを担う。
地方の再生にとって大事な事です。
地方再生のために必要なのは、農村の役割や機能を発揮することだと、島根大学の保母武彦(ほぼ・たけひご)名誉教授(地方自治論)は語ります。
島根大学名誉教授 保母武彦さん
地方再生を考えるうえで重要なことは、地方分権を中心に据えることです。ところが、安倍晋三政権は「地方創生」を唱えながら、地方分権と自治の原則をないがしろにしたやり方で進めようとしています。
政府は、中山間地域や離島の小さな自治体は「消滅」すると脅して、地方に人口20万規模の「地方中核拠点都市」をつくり、財政と施策を集中させ、東京に行かなくてもいいように、仕事の場をつくるといいます。
しかし、そうなると、政府は、農村部に回すべきお金を引き揚げて、その中枢都市に集中することになります。活性化どころか、農村部の疲弊をさらに促進させる政策です。
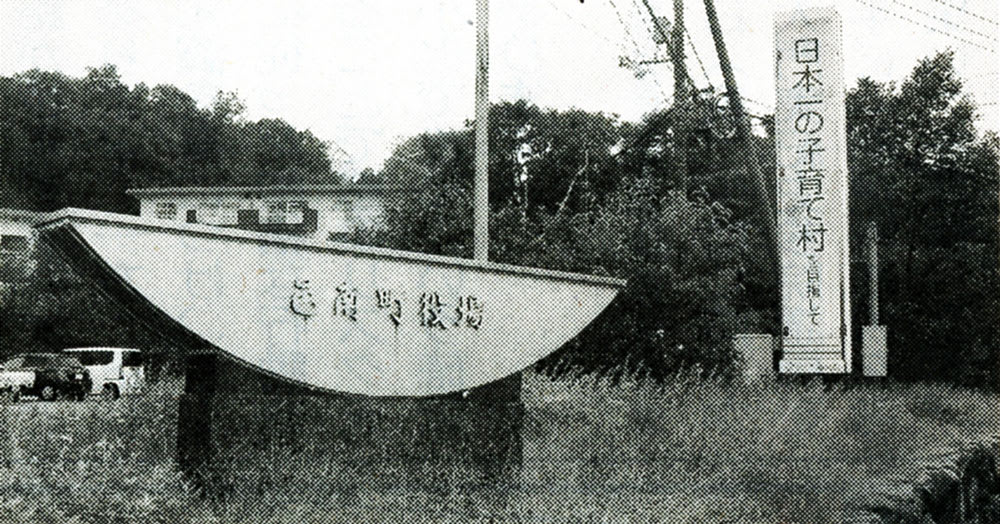
「日本一の子育て村」の看板を掲げる邑南町役場
豊富な資源提供
農村部の人口減少問題の根本にあるのは、農業を自由競争の原理に引き戻した自民党政治に突き当たります。しかし、政府にその反省と総括はまったくありません。地方再生をいいながら、農村の役割や機能の発揮を重視していません。
一つは日本の食料問題です。食料は輸入依存を強めています。世界的に飢餓人口が増えるなかで、食料をどう確保をするのか。自給率の引き上げが喫緊の課題になっています。米づくりが農村を支えており、現在の米価暴落への対策は急を要します。
もう一つはエネルギー問題です。原発ゼロを目指して再生可能エネルギーを増やす上で、農山村は豊富な資源を提供してくれます。再生可能エネルギーを増やすことは、貿易収支の改善にもつながり、輸出の拡大と同じ効果が得られます。
例えば、北海道の下川町では、木質バイオマスを中心に再生エネルギーで熱と電力の完全自給体制を確立しつつあります。それにより、町内の雇用を増やし、灯油代、重油代、電気代を町外へ支払うことなく、地域経済の活性化や子育て環境を整えます。
ヒント足もとに
島根県の邑南(おおなん)町では、地域の食材を生かした取り組みや保育医療費の無料化など子育て対策を進めており、飯南(いいなん)町では定住者向けの住宅対策や相談活動などに力を入れています。
地域の核になる公民館の活動も活発に行われています。それができるのは、20万人、30万人の地方中核都市ではなく、自然と人情が豊かな農村部だからです。
人を育てる「人づくり」も大切です。島根県の離島、海士(あま)町は、人口約2300人の町ですが、Iターンが9年間で438人にのぼります。若い人が生きがい、働きがいを求めて集まっています。ソニーやトヨタの正社員だった人もいます。大きな会社では自分が世の中にどう役立つのかがなかなか実感できない、連帯感が持てないなど、働きがいが持ちにくい社会になっていることが背景にあるのだと思います。
地方再生のヒントは地方の足もとにあります。上から目線では成功しません。
(おわり)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2014年10月26日付掲載
住民一人ひとりの顔が見える農村部、一人ひとりが主人公になって生産をを担う。
地方の再生にとって大事な事です。











