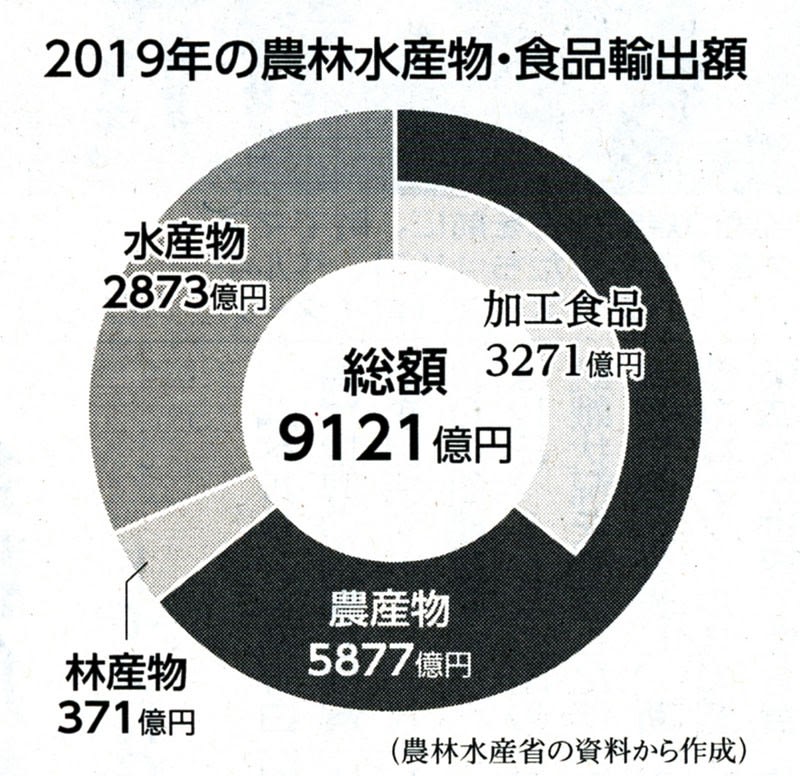2021年概算要求の焦点⑥ 社会保障 「自助」押しつけ強める
厚生労働省の2021年度概算要求は、過去最大の32兆9895億円(一般会計分)です。ただ、新型コロナウイルスの感染状況や影響を踏まえ、対策費用の大半は明示していません。年末までに調整し、要求額を上積みする見通しです。一方、コロナ禍にもかかわらず国民負担増・給付削減は「引き続き着実に実施する」として、「自助」の押し付けを強める構えです。
コロナ対策
コロナ対策では、医療・介護体制の強化に向け、受け入れ病床の確保や、感染を防ぐ陰圧化・個室化の整備支援を計上しますが、関係団体が再三再四求めている、受診・利用控えによる医療機関・介護事業者の収入減少への補てんには踏み込んでいません。現場では「借金漬けだ」と悲鳴が上がっており、経営危機は深刻です。
自治体が行政検査として行うPCR検査の費用の半分を引き続き国が負担するなど、検査体制の支援を盛り込みましたが、残り半分の費用を自治体が負担する問題の解決策は計上していません。全国知事会は、全額国庫負担による検査の戦略的拡大を求めています。
コロナ禍は、医療・保健所・介護などの深刻な人手不足も浮き彫りにしました。しかし、厚労省は医師から看護師への業務移管や、保健師の仕事に就いていない有資格者の「人材バンク」整備の費用を求めるだけで、抜本的な人員増に応じようとしていません。
コロナ対策が不十分すぎるうえ、安倍晋三前政権の社会保障費抑制路線を継承します。前政権は医療費負担増などで、高齢化などに伴う社会保障費の伸び(自然増)を13~20年度に計1兆8300億円も圧縮しました。21年度の自然増はまだ額を示していませんが、削減を継続する方針は変わっていません。自助を第一とする菅政権の危険性は鮮明です。


社会保障充実への政策転換を訴える医療団体などの役員ら=9月10日、厚労省内
負担は増加
介護事業者に支払われる介護報酬の15年度改定の際は、「自然増削減」のために大幅なマイナス改定を行いました。このままでは21年度改定でもマイナス改定が押し付けられる危険性があります。
21年には、75歳以上の医療費窓口負担を引き上げる法案を国会に提出する方針です。
医療体制は「感染症対応」も含めて検討するとしながら、病床削減の手を緩めてはいません。20年度に新設した「病床ダウンサイジング支援」84億円を引き続き要求。批判をかわそうと、名称だけ病床機能再編支援事業(仮称)に変えるなどあの手この手です。
受診時にマイナンバーカードを健康保険証として使えるようにする仕組みは、情報漏えいの不安をよそに、21年3月からの開始に向けて推進費用などを要求しています。
保育所の「待機児童ゼロ」は20年度末の達成を事実上断念。待機児は4月時点で1万2千人超です(厚労省調査)。内閣府は、人員配置基準などを緩和した企業主導型保育事業費を20年度比で上積みする計画です。(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2020年10月20日付掲載
コロナ対策では、コロナ患者を受け入れた医療機関への支援とともに、受診・利用控えによる医療機関・介護事業者の収入減少への補てんが必要です。
高齢化などに伴う社会保障費の伸び(自然増)の抑制も継続するとのこと。
コロナ禍のもと、社会保障に手厚いケアが求められています。
厚生労働省の2021年度概算要求は、過去最大の32兆9895億円(一般会計分)です。ただ、新型コロナウイルスの感染状況や影響を踏まえ、対策費用の大半は明示していません。年末までに調整し、要求額を上積みする見通しです。一方、コロナ禍にもかかわらず国民負担増・給付削減は「引き続き着実に実施する」として、「自助」の押し付けを強める構えです。
コロナ対策
コロナ対策では、医療・介護体制の強化に向け、受け入れ病床の確保や、感染を防ぐ陰圧化・個室化の整備支援を計上しますが、関係団体が再三再四求めている、受診・利用控えによる医療機関・介護事業者の収入減少への補てんには踏み込んでいません。現場では「借金漬けだ」と悲鳴が上がっており、経営危機は深刻です。
自治体が行政検査として行うPCR検査の費用の半分を引き続き国が負担するなど、検査体制の支援を盛り込みましたが、残り半分の費用を自治体が負担する問題の解決策は計上していません。全国知事会は、全額国庫負担による検査の戦略的拡大を求めています。
コロナ禍は、医療・保健所・介護などの深刻な人手不足も浮き彫りにしました。しかし、厚労省は医師から看護師への業務移管や、保健師の仕事に就いていない有資格者の「人材バンク」整備の費用を求めるだけで、抜本的な人員増に応じようとしていません。
コロナ対策が不十分すぎるうえ、安倍晋三前政権の社会保障費抑制路線を継承します。前政権は医療費負担増などで、高齢化などに伴う社会保障費の伸び(自然増)を13~20年度に計1兆8300億円も圧縮しました。21年度の自然増はまだ額を示していませんが、削減を継続する方針は変わっていません。自助を第一とする菅政権の危険性は鮮明です。


社会保障充実への政策転換を訴える医療団体などの役員ら=9月10日、厚労省内
負担は増加
介護事業者に支払われる介護報酬の15年度改定の際は、「自然増削減」のために大幅なマイナス改定を行いました。このままでは21年度改定でもマイナス改定が押し付けられる危険性があります。
21年には、75歳以上の医療費窓口負担を引き上げる法案を国会に提出する方針です。
医療体制は「感染症対応」も含めて検討するとしながら、病床削減の手を緩めてはいません。20年度に新設した「病床ダウンサイジング支援」84億円を引き続き要求。批判をかわそうと、名称だけ病床機能再編支援事業(仮称)に変えるなどあの手この手です。
受診時にマイナンバーカードを健康保険証として使えるようにする仕組みは、情報漏えいの不安をよそに、21年3月からの開始に向けて推進費用などを要求しています。
保育所の「待機児童ゼロ」は20年度末の達成を事実上断念。待機児は4月時点で1万2千人超です(厚労省調査)。内閣府は、人員配置基準などを緩和した企業主導型保育事業費を20年度比で上積みする計画です。(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2020年10月20日付掲載
コロナ対策では、コロナ患者を受け入れた医療機関への支援とともに、受診・利用控えによる医療機関・介護事業者の収入減少への補てんが必要です。
高齢化などに伴う社会保障費の伸び(自然増)の抑制も継続するとのこと。
コロナ禍のもと、社会保障に手厚いケアが求められています。