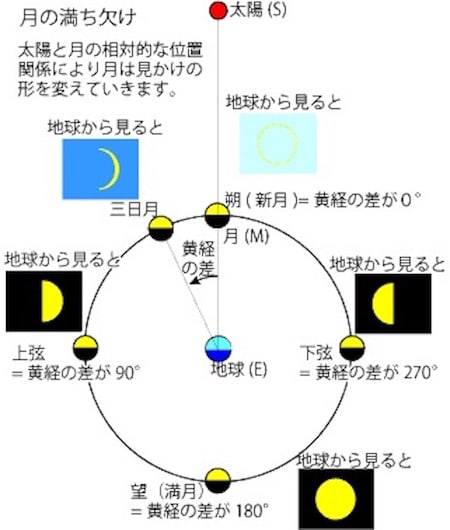今月の満月(望)は12日22時53分であった。プップした画像はその時刻に撮ったものである。真冬での望らしく、その輝きは当方にとって数分間以上直視すると短時間ながらも残像が残るほど眩しかった。同日正午での月齢13.6。月の出(群馬)17時であったが、視点での月の出は18時であった。
真上から太陽光を浴びているので、月面での凹凸(クレーターなど)は目立たない。

ホワイトバランス:オート(雰囲気優先)、ISO感度 200、1/1600秒、絞りF値 9、望遠 320 mm(トリミング)、RAW → JPEG変換
比較のために、望のときから4時間前に撮影した画像を加えた。

ホワイトバランス:オート(雰囲気優先)、ISO感度 200、1/320秒、絞りF値 9、望遠 320 mm(トリミング)、RAW → JPEG変換
*******
望のときは全く雲が浮かんでいない状態であった。しかし、月の出(18時頃)の時間帯において、月が昇る位置は幾つかの雲のかたまり(積雲)で覆われていた。結果として、5時間後に望となる明るさを反映した濃い彩りの月光彩雲が現れた。


先月でのときのように、ムーンピラー(月光柱)が現れることを期待したが....

さすがは満月である。雲に妨げられることなく、その姿をみせた。彩雲に露出を合わせたので、月面に対して露出オーバーとなっている。

今週は連続して月にレンズを向けている。今夜もデフォルメ化されたような月が昇りはじめた。
***
12日、桐生市にて。