今年2018年がちょうど西国三十三所草創1300年の記念の年ということで、2年前から始まっている各種行事の数も増えて、新たな取り組みが行われるようになっている。その一つに「西国観音曼荼羅」というのがある。
今年の初めに送られてきた西国三十三所の先達委員会からのお知らせによると、「掛け軸に替わる納経集印の新しいカタチ」として始めるものとある。専用の八角形、八色の用紙に朱印をいただき、33揃うと曼荼羅用の台紙に貼りつける。これを額に入れると、掛け軸のように床の間でなくても、洋間の壁に掛けることができる。三十三所を普段から身近にというものだ。
実はこれ、現在は先達のみが受けることができる。お知らせに同封されている引換券を持参すれば、33枚の八角形の用紙と台紙をいただくことができる。ただしこれはどこの札所というわけでもなく、地元の葛井寺では配布していない。先達委員会の札所として、紀三井寺、施福寺、岩間寺、革堂、総持寺、圓教寺、成相寺、松尾寺となっている。気のせいか、山の上にあるところが多いように感じるのだが・・。
この中で大阪から近いところとなると総持寺である。納経所が独立した建物になっており、西国関連のものも豊富に揃っている。2巡目としては参拝済みだが、今回は○巡目とカウントしない形で、この用紙をいただきに行くことにする。
総持寺に行こうと思ったのは、3月17日のダイヤ改正にて、新たにJR総持寺駅ができたこともある。新駅訪問も兼ねてちょっとの時間出かけてみる。

 JR総持寺(頭に「JR」がつくのが正式名称)は普通しか停まらないので、快速を手前の茨木で降りる。茨木の駅名標にも隣に「じぇいあーるそうじじ」と書かれている。次の普通に乗り、直線区間を走って次のJR総持寺で下車する。
JR総持寺(頭に「JR」がつくのが正式名称)は普通しか停まらないので、快速を手前の茨木で降りる。茨木の駅名標にも隣に「じぇいあーるそうじじ」と書かれている。次の普通に乗り、直線区間を走って次のJR総持寺で下車する。


 複々線の真ん中のスペースに島式ホームをはめ込み、線路を少し広げたような造りである。直線区間の真ん中ということで、ホームの端には撮り鉄の姿もちらほらと見える。ホームには高槻方面、大阪方面それぞれの列車を待つ人も結構いて、開業してまだ1週間だが自然に町中になじんでいる感じだ。周りは元々住宅やマンションも多く、病院や大学キャンパスもある。新駅の需要は元々あったところのようだ。ホームの両側には可動式のホームドアが設置されており、JRとしても今後ホームドアの設置駅を増やす上でのモデルケースとするそうだ。
複々線の真ん中のスペースに島式ホームをはめ込み、線路を少し広げたような造りである。直線区間の真ん中ということで、ホームの端には撮り鉄の姿もちらほらと見える。ホームには高槻方面、大阪方面それぞれの列車を待つ人も結構いて、開業してまだ1週間だが自然に町中になじんでいる感じだ。周りは元々住宅やマンションも多く、病院や大学キャンパスもある。新駅の需要は元々あったところのようだ。ホームの両側には可動式のホームドアが設置されており、JRとしても今後ホームドアの設置駅を増やす上でのモデルケースとするそうだ。
 ホームの上から瓦の屋根が見える。位置関係からしてあれが総持寺である。結構近いものだ。
ホームの上から瓦の屋根が見える。位置関係からしてあれが総持寺である。結構近いものだ。


 ホームから改札方面に向かう。総持寺の山門と、総持寺の伝統行事である包丁式のイラストが描かれている。自動改札に向かうが、この時間は駅員が不在とある。ご用の方はインターフォンでオペレーターを・・とある。一般の利用客にはこれで事足りるのだろうが、私としてちょっと気になるのが、JRの西国三十三所のキャンペーン。こちらは、札所最寄のJR駅で(一部は近鉄などの私鉄や、札所の境内で)スタンプを押してもらい、その駅数に応じてプレゼントに応募できたり、全部集まったら散華台紙などとの引き換えができるものだ。総持寺の場合は寺から20分ほど歩いた摂津富田駅が最寄り駅だったが、JR総持寺駅ができたことで当然最寄駅はこちらに移る。で、駅員がいない、スタンプを押してもらえない・・・というのは、クレームにならないかが心配である(最近訪ねた四国八十八所でも、納経所に昼休みの時間帯があるというのでちょっとしたもめごとになっている札所があったが・・)。もっとも、これまで通り摂津富田でスタンプは押してもらえるとあるので、駅員がいなければ電車で1駅移動するだけで済む。
ホームから改札方面に向かう。総持寺の山門と、総持寺の伝統行事である包丁式のイラストが描かれている。自動改札に向かうが、この時間は駅員が不在とある。ご用の方はインターフォンでオペレーターを・・とある。一般の利用客にはこれで事足りるのだろうが、私としてちょっと気になるのが、JRの西国三十三所のキャンペーン。こちらは、札所最寄のJR駅で(一部は近鉄などの私鉄や、札所の境内で)スタンプを押してもらい、その駅数に応じてプレゼントに応募できたり、全部集まったら散華台紙などとの引き換えができるものだ。総持寺の場合は寺から20分ほど歩いた摂津富田駅が最寄り駅だったが、JR総持寺駅ができたことで当然最寄駅はこちらに移る。で、駅員がいない、スタンプを押してもらえない・・・というのは、クレームにならないかが心配である(最近訪ねた四国八十八所でも、納経所に昼休みの時間帯があるというのでちょっとしたもめごとになっている札所があったが・・)。もっとも、これまで通り摂津富田でスタンプは押してもらえるとあるので、駅員がいなければ電車で1駅移動するだけで済む。






 ここから総持寺に向かう。駅の玄関も総持寺の山門をイメージした造りだという。駅前にはエレベーターのメーカーであるフジテックの建物がある。線路に沿って歩くと府道に出る。ここを渡ることができれば近いのだが横断歩道はなく、100mほど先の交差点で渡ることになる。そこでまた線路のほうに戻り、茨木病院の横を歩くと寺に到着する。駅から徒歩5~6分というところで、阪急の総持寺と同じくらい、あるいはそれより少し近い距離に感じる。
ここから総持寺に向かう。駅の玄関も総持寺の山門をイメージした造りだという。駅前にはエレベーターのメーカーであるフジテックの建物がある。線路に沿って歩くと府道に出る。ここを渡ることができれば近いのだが横断歩道はなく、100mほど先の交差点で渡ることになる。そこでまた線路のほうに戻り、茨木病院の横を歩くと寺に到着する。駅から徒歩5~6分というところで、阪急の総持寺と同じくらい、あるいはそれより少し近い距離に感じる。

 山門をくぐる。先ほどまで彼岸の法要を行っていたようで、境内にはそこそこの人が訪ねている。元々拝観料を取るわけでもなく、駅から近い町中の寺ということで、気軽に訪ねる人の多いところ。
山門をくぐる。先ほどまで彼岸の法要を行っていたようで、境内にはそこそこの人が訪ねている。元々拝観料を取るわけでもなく、駅から近い町中の寺ということで、気軽に訪ねる人の多いところ。

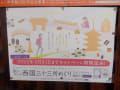






 せっかく来たのだからと、西国先達の輪袈裟を取り出し、本堂にてお勤めとする。この後は大師堂や、西国・四国のお砂踏み、その他のお堂を回る。すっかり春の景色となり、池の鯉や亀の元気そうな動きも見られる。
せっかく来たのだからと、西国先達の輪袈裟を取り出し、本堂にてお勤めとする。この後は大師堂や、西国・四国のお砂踏み、その他のお堂を回る。すっかり春の景色となり、池の鯉や亀の元気そうな動きも見られる。
 一通り回ったところで納経所に向かう。奥には「西国観音曼荼羅」の見本が掲げられている。額に入れるといっても、台紙は縦80cm、横77cmのサイズというから結構大きい。外で見ればこんなものかと思うが、もし部屋の壁に掛けるとなると結構大きく感じるだろう。
一通り回ったところで納経所に向かう。奥には「西国観音曼荼羅」の見本が掲げられている。額に入れるといっても、台紙は縦80cm、横77cmのサイズというから結構大きい。外で見ればこんなものかと思うが、もし部屋の壁に掛けるとなると結構大きく感じるだろう。
 引換券を差し出すと係の人はすぐに対応してくれて、まず台紙が収められた筒を渡される。この台紙を使うのは33枚の用紙すべてに朱印が入った後のことになるので、それまでは広げずに筒に収めたままにしておく。そして、10cm四方くらいの小箱を渡される。この中に札所番号が書かれた用紙が33枚入っている。
引換券を差し出すと係の人はすぐに対応してくれて、まず台紙が収められた筒を渡される。この台紙を使うのは33枚の用紙すべてに朱印が入った後のことになるので、それまでは広げずに筒に収めたままにしておく。そして、10cm四方くらいの小箱を渡される。この中に札所番号が書かれた用紙が33枚入っている。
 せっかくなので、総持寺の朱印をいただくことにする。「その中から22番を出してください」と言われ、取り出して渡す。朱印、墨書していただいた後で、「この用紙は乾きにくいので、ドライヤーを当ててください。ただ、風で飛ばないように気を付けて」と返される。1巡目では掛け軸に朱印をいただいており、その頃のことを思い出す。この用紙の場合は当て木は役に立たず、片手にドライヤーを持ち、もう片手で用紙を押さえて乾かす。その後で念のために当て紙をして小箱にしまう。
せっかくなので、総持寺の朱印をいただくことにする。「その中から22番を出してください」と言われ、取り出して渡す。朱印、墨書していただいた後で、「この用紙は乾きにくいので、ドライヤーを当ててください。ただ、風で飛ばないように気を付けて」と返される。1巡目では掛け軸に朱印をいただいており、その頃のことを思い出す。この用紙の場合は当て木は役に立たず、片手にドライヤーを持ち、もう片手で用紙を押さえて乾かす。その後で念のために当て紙をして小箱にしまう。
さて、西国めぐりの2巡目は残り12所残っているが、2巡目でこの曼荼羅の用紙を持って行くか。1巡目では掛け軸への朱印、2巡目ではご詠歌護符(これは先達としてついてくる)とカラーの本尊御影をいただいている。総持寺ではサンプルの意味もあって曼荼羅の用紙への朱印をいただいたが、途中から他のところを集めるのは中途半端なようにも思う。この流れだといずれは3巡目を行うことになるだろうから、曼荼羅用紙はそれに合わせて行うことにしようか。
 総持寺参りはこれで終わり、帰りは経路を変えて阪急の総持寺に向かう。こちらも普通のみの停車で、隣の茨木市で特急に乗り換えるのはJRと似たような位置づけだが、JRの新駅ができたというのは阪急にとってはこれから影響が出るだろうか。私も次に総持寺を訪ねる時は、阪急にするかJRにするか、迷うところである・・・。
総持寺参りはこれで終わり、帰りは経路を変えて阪急の総持寺に向かう。こちらも普通のみの停車で、隣の茨木市で特急に乗り換えるのはJRと似たような位置づけだが、JRの新駅ができたというのは阪急にとってはこれから影響が出るだろうか。私も次に総持寺を訪ねる時は、阪急にするかJRにするか、迷うところである・・・。
今年の初めに送られてきた西国三十三所の先達委員会からのお知らせによると、「掛け軸に替わる納経集印の新しいカタチ」として始めるものとある。専用の八角形、八色の用紙に朱印をいただき、33揃うと曼荼羅用の台紙に貼りつける。これを額に入れると、掛け軸のように床の間でなくても、洋間の壁に掛けることができる。三十三所を普段から身近にというものだ。
実はこれ、現在は先達のみが受けることができる。お知らせに同封されている引換券を持参すれば、33枚の八角形の用紙と台紙をいただくことができる。ただしこれはどこの札所というわけでもなく、地元の葛井寺では配布していない。先達委員会の札所として、紀三井寺、施福寺、岩間寺、革堂、総持寺、圓教寺、成相寺、松尾寺となっている。気のせいか、山の上にあるところが多いように感じるのだが・・。
この中で大阪から近いところとなると総持寺である。納経所が独立した建物になっており、西国関連のものも豊富に揃っている。2巡目としては参拝済みだが、今回は○巡目とカウントしない形で、この用紙をいただきに行くことにする。
総持寺に行こうと思ったのは、3月17日のダイヤ改正にて、新たにJR総持寺駅ができたこともある。新駅訪問も兼ねてちょっとの時間出かけてみる。

 JR総持寺(頭に「JR」がつくのが正式名称)は普通しか停まらないので、快速を手前の茨木で降りる。茨木の駅名標にも隣に「じぇいあーるそうじじ」と書かれている。次の普通に乗り、直線区間を走って次のJR総持寺で下車する。
JR総持寺(頭に「JR」がつくのが正式名称)は普通しか停まらないので、快速を手前の茨木で降りる。茨木の駅名標にも隣に「じぇいあーるそうじじ」と書かれている。次の普通に乗り、直線区間を走って次のJR総持寺で下車する。

 複々線の真ん中のスペースに島式ホームをはめ込み、線路を少し広げたような造りである。直線区間の真ん中ということで、ホームの端には撮り鉄の姿もちらほらと見える。ホームには高槻方面、大阪方面それぞれの列車を待つ人も結構いて、開業してまだ1週間だが自然に町中になじんでいる感じだ。周りは元々住宅やマンションも多く、病院や大学キャンパスもある。新駅の需要は元々あったところのようだ。ホームの両側には可動式のホームドアが設置されており、JRとしても今後ホームドアの設置駅を増やす上でのモデルケースとするそうだ。
複々線の真ん中のスペースに島式ホームをはめ込み、線路を少し広げたような造りである。直線区間の真ん中ということで、ホームの端には撮り鉄の姿もちらほらと見える。ホームには高槻方面、大阪方面それぞれの列車を待つ人も結構いて、開業してまだ1週間だが自然に町中になじんでいる感じだ。周りは元々住宅やマンションも多く、病院や大学キャンパスもある。新駅の需要は元々あったところのようだ。ホームの両側には可動式のホームドアが設置されており、JRとしても今後ホームドアの設置駅を増やす上でのモデルケースとするそうだ。 ホームの上から瓦の屋根が見える。位置関係からしてあれが総持寺である。結構近いものだ。
ホームの上から瓦の屋根が見える。位置関係からしてあれが総持寺である。結構近いものだ。

 ホームから改札方面に向かう。総持寺の山門と、総持寺の伝統行事である包丁式のイラストが描かれている。自動改札に向かうが、この時間は駅員が不在とある。ご用の方はインターフォンでオペレーターを・・とある。一般の利用客にはこれで事足りるのだろうが、私としてちょっと気になるのが、JRの西国三十三所のキャンペーン。こちらは、札所最寄のJR駅で(一部は近鉄などの私鉄や、札所の境内で)スタンプを押してもらい、その駅数に応じてプレゼントに応募できたり、全部集まったら散華台紙などとの引き換えができるものだ。総持寺の場合は寺から20分ほど歩いた摂津富田駅が最寄り駅だったが、JR総持寺駅ができたことで当然最寄駅はこちらに移る。で、駅員がいない、スタンプを押してもらえない・・・というのは、クレームにならないかが心配である(最近訪ねた四国八十八所でも、納経所に昼休みの時間帯があるというのでちょっとしたもめごとになっている札所があったが・・)。もっとも、これまで通り摂津富田でスタンプは押してもらえるとあるので、駅員がいなければ電車で1駅移動するだけで済む。
ホームから改札方面に向かう。総持寺の山門と、総持寺の伝統行事である包丁式のイラストが描かれている。自動改札に向かうが、この時間は駅員が不在とある。ご用の方はインターフォンでオペレーターを・・とある。一般の利用客にはこれで事足りるのだろうが、私としてちょっと気になるのが、JRの西国三十三所のキャンペーン。こちらは、札所最寄のJR駅で(一部は近鉄などの私鉄や、札所の境内で)スタンプを押してもらい、その駅数に応じてプレゼントに応募できたり、全部集まったら散華台紙などとの引き換えができるものだ。総持寺の場合は寺から20分ほど歩いた摂津富田駅が最寄り駅だったが、JR総持寺駅ができたことで当然最寄駅はこちらに移る。で、駅員がいない、スタンプを押してもらえない・・・というのは、クレームにならないかが心配である(最近訪ねた四国八十八所でも、納経所に昼休みの時間帯があるというのでちょっとしたもめごとになっている札所があったが・・)。もっとも、これまで通り摂津富田でスタンプは押してもらえるとあるので、駅員がいなければ電車で1駅移動するだけで済む。





 ここから総持寺に向かう。駅の玄関も総持寺の山門をイメージした造りだという。駅前にはエレベーターのメーカーであるフジテックの建物がある。線路に沿って歩くと府道に出る。ここを渡ることができれば近いのだが横断歩道はなく、100mほど先の交差点で渡ることになる。そこでまた線路のほうに戻り、茨木病院の横を歩くと寺に到着する。駅から徒歩5~6分というところで、阪急の総持寺と同じくらい、あるいはそれより少し近い距離に感じる。
ここから総持寺に向かう。駅の玄関も総持寺の山門をイメージした造りだという。駅前にはエレベーターのメーカーであるフジテックの建物がある。線路に沿って歩くと府道に出る。ここを渡ることができれば近いのだが横断歩道はなく、100mほど先の交差点で渡ることになる。そこでまた線路のほうに戻り、茨木病院の横を歩くと寺に到着する。駅から徒歩5~6分というところで、阪急の総持寺と同じくらい、あるいはそれより少し近い距離に感じる。
 山門をくぐる。先ほどまで彼岸の法要を行っていたようで、境内にはそこそこの人が訪ねている。元々拝観料を取るわけでもなく、駅から近い町中の寺ということで、気軽に訪ねる人の多いところ。
山門をくぐる。先ほどまで彼岸の法要を行っていたようで、境内にはそこそこの人が訪ねている。元々拝観料を取るわけでもなく、駅から近い町中の寺ということで、気軽に訪ねる人の多いところ。
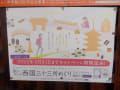






 せっかく来たのだからと、西国先達の輪袈裟を取り出し、本堂にてお勤めとする。この後は大師堂や、西国・四国のお砂踏み、その他のお堂を回る。すっかり春の景色となり、池の鯉や亀の元気そうな動きも見られる。
せっかく来たのだからと、西国先達の輪袈裟を取り出し、本堂にてお勤めとする。この後は大師堂や、西国・四国のお砂踏み、その他のお堂を回る。すっかり春の景色となり、池の鯉や亀の元気そうな動きも見られる。 一通り回ったところで納経所に向かう。奥には「西国観音曼荼羅」の見本が掲げられている。額に入れるといっても、台紙は縦80cm、横77cmのサイズというから結構大きい。外で見ればこんなものかと思うが、もし部屋の壁に掛けるとなると結構大きく感じるだろう。
一通り回ったところで納経所に向かう。奥には「西国観音曼荼羅」の見本が掲げられている。額に入れるといっても、台紙は縦80cm、横77cmのサイズというから結構大きい。外で見ればこんなものかと思うが、もし部屋の壁に掛けるとなると結構大きく感じるだろう。 引換券を差し出すと係の人はすぐに対応してくれて、まず台紙が収められた筒を渡される。この台紙を使うのは33枚の用紙すべてに朱印が入った後のことになるので、それまでは広げずに筒に収めたままにしておく。そして、10cm四方くらいの小箱を渡される。この中に札所番号が書かれた用紙が33枚入っている。
引換券を差し出すと係の人はすぐに対応してくれて、まず台紙が収められた筒を渡される。この台紙を使うのは33枚の用紙すべてに朱印が入った後のことになるので、それまでは広げずに筒に収めたままにしておく。そして、10cm四方くらいの小箱を渡される。この中に札所番号が書かれた用紙が33枚入っている。 せっかくなので、総持寺の朱印をいただくことにする。「その中から22番を出してください」と言われ、取り出して渡す。朱印、墨書していただいた後で、「この用紙は乾きにくいので、ドライヤーを当ててください。ただ、風で飛ばないように気を付けて」と返される。1巡目では掛け軸に朱印をいただいており、その頃のことを思い出す。この用紙の場合は当て木は役に立たず、片手にドライヤーを持ち、もう片手で用紙を押さえて乾かす。その後で念のために当て紙をして小箱にしまう。
せっかくなので、総持寺の朱印をいただくことにする。「その中から22番を出してください」と言われ、取り出して渡す。朱印、墨書していただいた後で、「この用紙は乾きにくいので、ドライヤーを当ててください。ただ、風で飛ばないように気を付けて」と返される。1巡目では掛け軸に朱印をいただいており、その頃のことを思い出す。この用紙の場合は当て木は役に立たず、片手にドライヤーを持ち、もう片手で用紙を押さえて乾かす。その後で念のために当て紙をして小箱にしまう。さて、西国めぐりの2巡目は残り12所残っているが、2巡目でこの曼荼羅の用紙を持って行くか。1巡目では掛け軸への朱印、2巡目ではご詠歌護符(これは先達としてついてくる)とカラーの本尊御影をいただいている。総持寺ではサンプルの意味もあって曼荼羅の用紙への朱印をいただいたが、途中から他のところを集めるのは中途半端なようにも思う。この流れだといずれは3巡目を行うことになるだろうから、曼荼羅用紙はそれに合わせて行うことにしようか。
 総持寺参りはこれで終わり、帰りは経路を変えて阪急の総持寺に向かう。こちらも普通のみの停車で、隣の茨木市で特急に乗り換えるのはJRと似たような位置づけだが、JRの新駅ができたというのは阪急にとってはこれから影響が出るだろうか。私も次に総持寺を訪ねる時は、阪急にするかJRにするか、迷うところである・・・。
総持寺参りはこれで終わり、帰りは経路を変えて阪急の総持寺に向かう。こちらも普通のみの停車で、隣の茨木市で特急に乗り換えるのはJRと似たような位置づけだが、JRの新駅ができたというのは阪急にとってはこれから影響が出るだろうか。私も次に総持寺を訪ねる時は、阪急にするかJRにするか、迷うところである・・・。
















