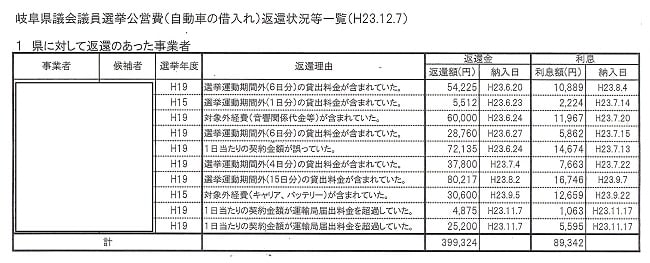雨が止んだので、そろそろ咲き終わりのビオラを抜いて、

ずいぶん前に買ってあったポーチュラカとマツバボタンを玄関横のスペースに植えました。



ビワもいろんだ頃だと思って見に行ったら、
なんと、熟した黄色い実がきれいになくなっていました。
木の下を見ると、食べた皮が一面に散らかっているし、
高い処の枝も折られているので、きっと留守中にサルに食べられたのでしょう。
まさかビワまで食べられるとは・・・・うーんがっかりです。。
次はイチジクがねらわれると思うので、はやくネットをかけなければ・・・。
畑の作物はだいじょうぶでしょうか。
応援クリック してね
してね 


本文中の写真をクリックすると拡大します。
ところで、
昨日の中日新聞の生活面は、稲熊さんの記事でした。
不妊治療関連の記事といっしょに紹介させていただきます。
最後まで読んでくださってありがとう

 クリックを
クリックを
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね

P-WANのバナーのトップページのリンクはこちらから。


ずいぶん前に買ってあったポーチュラカとマツバボタンを玄関横のスペースに植えました。



ビワもいろんだ頃だと思って見に行ったら、
なんと、熟した黄色い実がきれいになくなっていました。
木の下を見ると、食べた皮が一面に散らかっているし、
高い処の枝も折られているので、きっと留守中にサルに食べられたのでしょう。
まさかビワまで食べられるとは・・・・うーんがっかりです。。
次はイチジクがねらわれると思うので、はやくネットをかけなければ・・・。
畑の作物はだいじょうぶでしょうか。
応援クリック



本文中の写真をクリックすると拡大します。
ところで、
昨日の中日新聞の生活面は、稲熊さんの記事でした。
不妊治療関連の記事といっしょに紹介させていただきます。
| 不妊治療に職場支援を 両立できる仕組み必要 2013年6月21日 中日新聞 不妊治療と仕事の両立に悩む女性が増えている。生理周期に合わせて治療するため、日程を決めるのが難しく、急に休まなければならないことが多いからだ。経済的負担も大きく、働き続けるための支援が求められている。 約四年前から不妊治療を続ける大阪市の看護師柏本佐智子さん(37)は、何カ月も先まで印が付いたカレンダーを「休みが尽きるか、お金が尽きるか、どちらが先か」と見つめる。治療費は全額自己負担で、これまで三百万円を使った。 昨年治療のために受診したのは四十九回。時間単位で取れる休暇もあるが、不妊治療に通う大学病院は混み、一日がかりになることも。体外受精のための卵子採取後は体調を崩すことが多く、一週間ほど病気休暇を取ったこともあった。 「糖尿病看護認定看護師」の資格を持ち、患者との面談に加え、院内外で講演する。だが、予定が立てられずに講演を断ることもある。当初は仕事で治療を休むことがあったが、職場の理解もあり、今は治療最優先。「この日は休みそう」と同僚に伝えるが、その通りにならないこともある。 ◇ 「突然『明後日の午前、また受診して』と言われるので、仕事の予定を入れられずに困った」 IT企業に勤めていた神奈川県の女性(40)は振り返る。受診は多いと月七~八回。治療を上司に話すと「専念した方がいい」と強く勧められ、一年前に退職に追い込まれた。 医師に「仕事がストレスになっているかも」と言われたが、退職後は社会とのつながりがなくなり、より強いストレスを感じた。最近、派遣社員として別の職場で働き始めたが、治療のことは言えずにいる。「助成金も必要だが、働き続けられる仕組みづくりをしてほしい」と願う。 ◇ 空港で接客の仕事をしていた神奈川県の女性(35)は「治療していることを理解してほしいとも考えたが、言い出せる雰囲気ではなかった」と打ち明ける。隠したため、仕事の都合で治療のタイミングを逃すことも。勤務は未明からの早番と、午後から未明までの遅番の二交代。平日の日中に受診しやすかったが、朝治療してから出勤し、未明まで続く仕事は体力的にもきつく、一年半前に退職した。 「赤ちゃんを授かったときに貯金ゼロでは困る」との焦りもある。今後は、治療を隠さないつもりでいる。 ◆有給や短時間勤務など望む声 国立社会保障・人口問題研究所の二〇一〇年の調査では、不妊を心配したことのある夫婦の割合は31・1%と、五年前の調査より5ポイント増。実際に不妊の検査や治療を受けた夫婦の割合は16・4%で、子どものいない夫婦では28・6%に上る。 不妊の人たちを支援するNPO法人・Fine(ファイン、東京)が、治療中の約二千人に実施したアンケートによると、86・6%が「仕事などに支障をきたしたことがある」と回答。「職場で治療へのサポートがない」人も63・8%と、仕事の調整に苦心する様子がうかがえる。 理事長の松本亜樹子さんによると、治療と仕事を両立できず、悩んだ末に退職した人も多いという。「特効薬はない。まずは職場で理解を深めてもらうため、企業で研修を取り入れてほしい」と話す。注射や検査などは半日あればできるため、フレックス勤務や短時間勤務、時間単位で取得できる有給休暇などを要望する声が多い。 国内では百貨店や大手メーカーなど、不妊治療のための有給休暇や、短時間勤務制度などを導入した企業もある。 (稲熊美樹) |
| 【三重】不妊治療助成、国の年齢制限検討に困惑 2013年6月19日 中日新聞 妊娠を望んでいる県内の夫婦で、昨年度に体外受精の不妊治療で助成制度を利用した件数は、制度が始まった八年前に比べて八倍の二千三百二十五件に上った。国と県が折半する助成額は十一倍の三億二千万円に膨らんでいる。不妊治療のニーズが年々高まる中、国は財源不足に備えて対象を三十九歳までに制限することなどを検討しており、子を望む夫婦に困惑が広がっている。 顕微授精などの体外受精は保険が適用されないため、一回につき平均三十万~五十万円の治療費がかかる。助成制度は、治療一回につき上限十五万円、年二回まで利用できる。昨年度は県内で少なくとも一千組以上の夫婦が利用したことになる。上限額を超えた場合の上乗せ補助も県と十六市町が独自に実施。東員町、志摩市などは検査や薬物療法の費用にも対象を拡大し、利用者は制度の周知とともに増え続けている。 毎週火曜、県立看護大(津市)に開設される県不妊専門相談センターによると、年三~四回の治療を自己負担で受ける夫婦も少なくなく、依然として大きな負担に関する相談は多い。 昨年度センターに寄せられた電話相談二百七十三件のうち、三十歳代後半~四十歳代の女性が約三分の二を占めた。国が検討している年齢制限に関して、相談員を務める助産師は「妊娠を望む四十歳以上の女性に対し、国が生き方を制限することになる」と反発。別の看護師は「治療による心身への負担を考えるとやむを得ない部分もある。年齢ではなく、その人の体力や環境に応じて一番いい選択を考えたい」と話す。 助成件数は毎年二割増のペースで、県は本年度も三千件弱を見込む。毎年事業予算を増額計上しているが、年齢とともに妊娠しにくくなる傾向があるのも現実で、県の担当者は「年齢制限も含め、効果的な助成のあり方を見直す必要はある。国の議論を見守りたい」と話している。 (安藤孝憲) |
| 特定不妊治療の助成 県や市町村が上乗せ/山形 体外受精などの不妊治療を行っている夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策につなげようと、県内の自治体で特定不妊治療の助成が広がりをみせている。県は今年度、国の制度に加えて、独自に助成回数を年1回、5年間で通算5回分を拡充。市町村では、県の助成にさらに上乗せする制度も登場している。 特定不妊治療は「体外受精」と「顕微授精」の2種類。いずれも保険外診療で高額な医療費がかかるため、2004年度から国などが治療費の助成を行っている。母胎から採卵して体外受精などを行い、再び母胎に戻すまでを1回の治療として助成する。 国の制度は、初年度は年3回、2~5年度目は年2回対象で、5年間で通算10回まで助成が受けられる。1回当たり15万円だが、以前に凍結した胚を移植したり、状態の良い卵が得られず中止したりした場合は、1回7万5000円となる。夫婦の合計所得が730万円未満の世帯が対象。 県子ども家庭課によると、04年度に123件だった県内の助成利用実績は、制度の充実とともに伸び続け、12年度は774件。県は今回、不妊で悩んでいる夫婦が依然多いとして、2~5年度目も3回目の治療を受けられるように、助成回数の上乗せを決めた。助成額は国の制度と同じ。 こうした制度を利用しても、1回当たり15万円程度は利用者の自己負担となる。このため、村山市と長井市では、自己負担分も全額助成する制度を設けるなど、県内の33市町村が助成額についても上乗せ支援を行っている。 県はこのほかにも、治療について気軽に相談してもらおうと、山形大付属病院に不妊専門相談センター(023・628・5571)を設置している。月、水、金曜日の午前中に電話で予約し、指定された日に医師から治療や助成制度に関する説明が受けられる。 (2013年6月21日 読売新聞) |
最後まで読んでくださってありがとう

 クリックを
クリックを 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね


P-WANのバナーのトップページのリンクはこちらから。