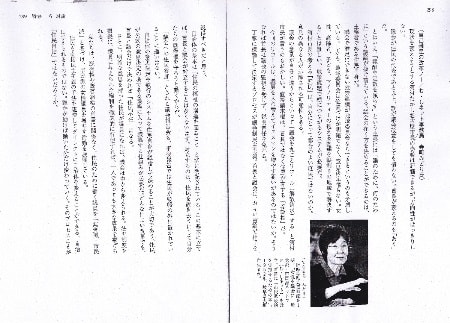きょうは立春。
お昼は、ともちゃんが東京駅で買ってきた六厘舎のつけめん。
お店で食べたことはないけれど、自宅で冷凍めんを説明書き通り作っても、
岐阜のラーメン屋で食べたことないくらいのおいしさ。

麺の量も大盛で、つけめんの具のチャーシューもメンマも入ってて
800円はお値打ち。お土産だけでなく通販でも手に入るみたいですね。
つけめんを食べたら体がポカポカしてきて、気温も上がってきたみたいなので、
午後からはちょっと庭仕事をすることにしました。
玄関横にはまだ何も植えてなくて、地面に張り付くように草が生えているので、

草むしりをして、球根とお花を植えることにしました。

年明けにバローで定価の半額の半額で購入した球根。

この場所には水仙を植えます。

きょうは時間がないので、ユリはまた暖かい日に庭に植えましょう。
鉢に植えたクロッカスも芽が生えそろったのですが、
根が詰まっているので植え替えて、



鉢植えの花たちも、このところの寒さで縮こまっているので、地面に卸してやりました。


 応援クリック
応援クリック してね
してね 

 本文中の写真をクリックすると拡大します。
本文中の写真をクリックすると拡大します。
市長選挙の告示を明日に控え、沖縄防衛局長の「有権者リスト」で揺れている宜野湾市ですが、
「普天間の辺野古移設を断念へ」というニュースが飛び込んできました。
この記事は沖縄タイムスの一面トップだったそうですが、
きょうの夕刊をみても、他の新聞には載っていません。
沖縄の基地問題を巡っては、いろんな情報が錯綜しているようです。
米、普天間の辺野古移設を断念へ
2012年2月4日 沖縄タイムス
【平安名純代・米国特約記者】在沖米海兵隊のグアム移転計画をめぐり、米国防総省が米議会との水面下の交渉で、米軍普天間飛行場の名護市辺野古沖への代替施設建設を断念する意向を伝達していたことが3日、分かった。同飛行場の移設・返還については日米間で協議をやり直す見通し。複数の米議会筋が本紙の取材に対して明らかにした。
米軍側は、中国の軍事力拡大を背景に沖縄に集中する海兵隊の拠点をアジア太平洋地域に分散させる必要性が高まったとして、2000~2500人規模の部隊編成に再構成。グアムやハワイやオーストラリア、フィリピンなどに分散移転させる案などを立案していた。
計画の変更について議会筋は「グアム移転協定の再交渉を視野に入れた再協議が必要となる」との見通しを示した。
オバマ政権は向こう10年間で国防費約4900億ドルと海兵隊員約2万人を削減する方針を打ち出した。一方、米議会は巨費を要する代替施設の建設は政権の方針に逆行しているとし、必要性を具体的戦略とともに示すよう要請。今春から本格化する議会で追及する構えをみせていた。
米上院のレビン軍事委員長(民主)とマケイン筆頭委員(共和)、ウェッブ外交委員会東アジア太平洋小委員長(民主)は昨年5月、在沖海兵隊のグアム移転計画について、巨額を要するため必要性に疑問を提示。「計画は非現実的で実現不可能」と述べ、普天間飛行場の名護市辺野古への移設を断念し、米軍嘉手納基地への統合の検討を含めた現行計画の見直しを米国防総省に要請していた。
米議会筋によると、当時から米政府内では「代替施設の建設は困難」との見方が出ていたという。
[ことば]
米海兵隊グアム移転 2006年の在日米軍再編に関する日米合意の柱で、沖縄の基地負担軽減のため在沖縄海兵隊約8千人と家族約9千人をグアムへ移転する計画。09年2月に中曽根弘文外相(当時)とクリントン米国務長官が協定に署名、国会が承認した。海兵隊移転は米軍普天間飛行場の県内移設進展と日本の資金面の貢献にかかっているとの表現で、移設とセットに位置付けられている。 |
沖縄説得、一層困難に=県内移設の撤回要求強まる-日本政府
日米両政府は6日、ワシントンで外務・防衛当局の審議官級協議を行い、在沖縄海兵隊のグアム移転計画の見直しなど在日米軍再編の修正協議を本格化させる。日本政府は、再編計画でパッケージとされたグアム移転と米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)移設が切り離されても、現行の同県名護市辺野古への移設手続きを着実に進めたい考え。一方、沖縄からは早くも移設案の白紙化を求める声が出始め、今後の国内調整は一層難航することが予想される。
「普天間の固定化につながらないことを大前提にしないといけない。辺野古案がベストだ」。渡辺周防衛副大臣は4日、記者団に対し、グアム移転の先行により普天間移設が遅れることに懸念を示した。
日本政府は今回の計画見直しに当たっては「普天間移設とグアム移転が共に進む方策について柔軟性をもって考える」(玄葉光一郎外相)とあくまで両立を目指す方針。6月にも仲井真弘多知事に移設先の埋め立てを申請したいとしている。
しかし、米国の海兵隊グアム移転見直しを受け、宜野湾市の米須清栄副市長は4日、「パッケージが崩れたことになり日米合意の見直しが必要だ」と辺野古案の撤回を要求。名護市の稲嶺進市長も「当然、辺野古移設は必要なくなる」と同調した。沖縄県では今月12日に宜野湾市長選、6月には県議選が予定される。選挙を前に県内移設の撤回要求が強まるのは必至で、野田政権は引き続き対応に苦慮しそうだ。(2012/02/04 時事通信) |
クローズアップ2012:沖縄防衛局長更迭へ 選挙に関与、半ば慣例化
野田政権が真部朗沖縄防衛局長を更迭する方針を固めたのは、これ以上、事態を長引かせれば、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設問題だけでなく、政権そのものに大きな打撃となりかねないからだ。しかし、真部氏が宜野湾市長選への投票を呼びかけた今回のケース以外にも、沖縄防衛局が選挙に関与していた例が次々と明らかになっており、沖縄は反発を強めている。
「選挙への不当介入だ」「非常に許し難い問題だ」。2日、防衛省聴取のため真部氏が上京し、トップ不在となった沖縄防衛局。宜野湾市長選に出馬表明した共産、社民、沖縄社会大衆各党が推薦する伊波(いは)洋一元市長と、自民、公明両党が推す佐喜真淳(さきまあつし)県議の双方の陣営関係者がそれぞれ抗議に訪れた。「本省の調査中なので回答を待ってほしい」。応対した局幹部は繰り返し頭を下げるほかなかった。
複数の沖縄防衛局関係者によると、沖縄では知事選と国政選挙で、局長講話などによる職員への投票呼びかけは半ば慣例化していた。局内の講堂に参加できる職員を集め、局長が「棄権せず、必ず投票に行ってください」「公務員の中立性を守ってください」などと話すのだという。幹部職員を集めた会議「局議」で局長が投票を呼びかけ、幹部職員がそれぞれの職場で伝えるパターンもあった。
基地問題を対立軸に、長く保革が伯仲してきた沖縄政界。日米安保体制維持のため「基地の安定的運用」が使命の防衛局にとって、各種選挙での革新側の勝利はその使命の妨げになりかねない。
「候補者名は出さなくとも、真意は十分に伝わる」と関係者は言う。
20年以上前の知事選では、沖縄防衛局の前身、那覇防衛施設局の幹部が局発注工事を受注した土木建設業者を集め、万票単位で集票のノルマを示したこともあったという。
防衛当局の意向が露骨に表れたのが97年に普天間代替施設の海上ヘリポート建設を巡って行われた名護市民投票。住民投票には公選法が適用されないこともあって、那覇防衛施設局は職員が2人1組になって戸別訪問し、基地建設に理解を求めた。
◇「普天間」進まぬ焦りか
ただ、今回表面化した真部氏の講話は宜野湾市長選を巡って行われたもので、職員をリストアップし、親戚への投票呼びかけにまで踏み込んでいた。防衛局関係者は「宜野湾市長選に絡んで局長講話があった例は知らない。中身も明らかにやり過ぎ」と明かす。
普天間飛行場移設で沖縄が保革とも「県外」で一致する中、沖縄防衛局は環境影響評価など移設に向けた手続きや防衛省と地元との調整に忙殺されている。関係者はそうした状況に「焦りがあったとしか思えない」と話した。【井本義親、吉永康朗】
◇官邸迷走、動き鈍く
藤村修官房長官は2日の記者会見で「(講話)全体の評価はできる段階ではない。防衛省の適正化委員会(調査チーム)で判断していく」と語り、事実関係の調査にあたることを強調するにとどめた。
今回、藤村氏の言動は迷走した。講話問題が発覚した1月31日の記者会見では「重大な事案。厳正に対処をしていく方針だ」と重い処分をにおわせた。首相官邸のこうしたムードに防衛省内では「更迭はやむなし」とのムードが広がった。ところが、1日の会見では一転、「全体像をつかんだ上で判断したい。逆にいいことだという評価も出るかもしれない」と火消しにまわり、政権としてのスタンスが定まっていないことを印象づけた。
政権が揺れたのは、講話問題が政権に与える影響を測りかねていたからだ。講話の内容が公選法違反にあたらなければ、訓告や厳重注意などの「形式的な処分で乗り切れるかもしれない」(政府関係者)との迷いが当初はあった。だが、真部氏が「名護の選挙でも(講話を)やった」と、普天間飛行場の移設受け入れが争点になった10年9月の名護市議選でも投票呼びかけの講話をしたことを明かし、事態は深刻化した。
動きが鈍かった自公両党が徹底追及に方針を転換したことも、官邸には誤算だった。自民党の谷垣禎一総裁は2日、党本部で記者団に「防衛省の政策に少しでも有利なように選挙結果を導こうとした疑念がある」と批判。公明党の山口那津男代表も党本部での会合で「公務員の政治的中立性が有権者から疑われる事態は正さなければならない」と強調した。
同日の衆院予算委員会では遠山清彦氏(公明)が「講話は局長の発意となっているが本当か。私が知る局長の人柄や仕事ぶりから考えて、本省、政務三役に判断を仰いでいなかったか」と追及。渡辺周副防衛相は「そういう話は一切なかった。天地神明にかけてお誓い申し上げる」と否定したが、組織ぐるみの疑惑すら浮上している。
事態の深刻化に野田政権は真部氏の更迭方針を固めたが、与党幹部は「防衛局の講堂に(職員を)集めたのは真部局長の判断。こういうのは長引かせたらダメだ。そういうことを官邸はまったく分かってない」と政権の動きの鈍さを批判した。【佐藤丈一、坂口裕彦、小山由宇】
==============
◆沖縄防衛局長問題を巡る主な経緯◆
2011年
12月 19日 不適切発言で更迭された田中聡氏の後任として、真部朗氏が沖縄防衛局長に就任
28日 沖縄防衛局が普天間飛行場移設の環境影響評価書を沖縄県に未明に提出
2012年
1月 4日付 沖縄防衛局総務部が各部へのメールで宜野湾市に本人か親族が在住する職員をリストアップして6日までに提出するよう指示
13日 内閣改造で田中直紀氏が防衛相に就任
18日付 沖縄防衛局総務部が各部へのメールでリストアップされた職員に真部氏の講話を聴くよう呼びかけ
23、24日 真部氏が防衛局庁舎内でリストアップされた職員(80人のうち66人が参加)
に講話し宜野湾市長選への投票を呼びかけ
31日 共産党の赤嶺政賢氏が衆院予算委でメールの存在を指摘し問題発覚
藤村修官房長官が記者会見で「重大な事案だ」と指摘
2月 1日 防衛省が衆院予算委理事会で事実関係を認める
防衛省が政務三役らによる調査チーム設置を決める
真部氏が法律違反の疑いを「自覚している」と発言
2日 真部氏が防衛省政務三役の聴取に「軽率だった」と非を認める
5日 宜野湾市長選告示
12日 同投開票
毎日新聞 2012年2月3日 |
最後まで読んでくださってありがとう 

 クリックを
クリックを
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね 


 してね
してね 


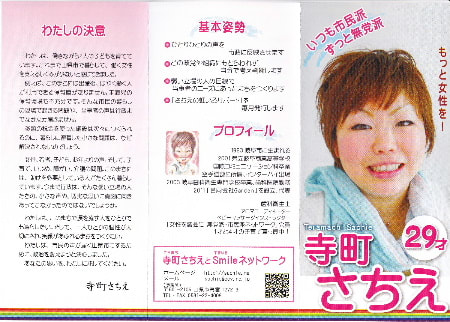


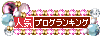 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ  クリックを
クリックを 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。





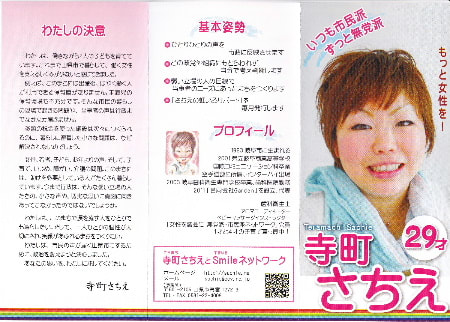


 クリックを
クリックを 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。