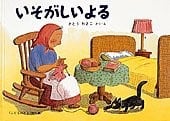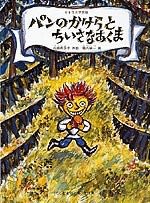てのひらむかしばなし はなさかじい/長谷川摂子・文 伊藤秀男・絵/岩波書店/2008年
日本の昔話といえば「はなさかじい」は、かかせません。長谷川さんの昔話方言と擬音語のリズムにあっという間に、ひきこまれました。
じいさまが、山で狩りをする場面、イヌのシロのほえる声
「ひがしの いのしし こっちゃこー、にしの うさぎも こっちゃこー、ワンワン」
臼から、小判が出るさま
「大判 小判が チャラリン パラリン」
しものじいさまが 臼をひく場面
「うまの くそが モッコン モッコン」
かみの じさまが 灰をまく場面
「こがね サラサラ ホホラホーッ」
じさまが 灰で花を咲かせる前段階では、じさまの ブスーッ という へで 灰がとんで冬枯れの木に かかったとおもったら えだという えだに、ぱっぱ ぱっぱと 桜の花が咲きます。
じさま、川で魚をとったり、山で猟をしたりと、漁師と猟師を兼ねていたんですね。
「かわに どっこを しかけると まいにち さかなが びんご びんご」というのはどっこに 魚がはいるようすですが、”どっこ”が、なにかわからなくても 気にすることがないのは、ここちよいリズムが続くからでしょう。
桜がさくようすも綺麗です。

はなさかじい/よしざわかずお・文 さくらいまこと・絵/ポプラ社/1967年
「はなさかじい」は絵本だけでも30冊はこえています。長谷川さんとの比較でみてみました。
吉沢文では、いぬとじいさま、ばあさまがであって、子どもになるところからはじまります。山で見つけるのは大判、小判としています。オーソドックスな展開です。
松の木が一晩で大きくなるのが長谷川文ですが、吉沢文では、じいさまばあさまが松の木をうえ、水を一ぱいやると、すっとのび、また一ぱいやると、すっとのびていきます。
吉沢文では、臼をつくるきっかけが鳥の声で、隣のじじばばが、さらっとしています。
さらに、文章が長めなのが特徴でしょうか。
擬音語がリズミカルなのは共通しています。
灰をまく場面は、「ちんぱらりん ごようのまつ、ひとふり ふれば はなつぼむ、ふたふり ふれば はながさく」です。
作者は方言を基礎とした再話用の用語を使いこなす自信がなかったので共通語を用いたとしています。
・花咲かじい(子どもに語る日本の昔話②/稲田和子・筒井悦子/こぐま社/1995年)
山形の昔話。
ばばが川へ洗濯にいって流れてきた赤い小箱をあけると、かわいい犬の子がはいっていたのが導入部。
犬ころは じじとばばのふたりをのせて山にでかけます。隣のじいさまが山でみつけるのが馬のふん、牛のふん。臼から出てくるのも馬、牛のふんです。
花を咲くようすは、チチンポン、パラリン、パラリン。
隣のじいさまは、殿さまのお城まで出かけて、灰をまきます。
・花咲爺(日本昔話百選改訂新版/稲田浩二・稲田和子:編・著/三省堂/2003年)
岐阜県の昔話。
ばあさが川に流れてきた柿をもちかえると、なかから子犬がでてきます。
隣のじいさまが、宝物のかわりに、山でほりあてたのは、臭い水だけ。臼をつくと 臭いとも何ともしょうがないもの。最後は花を咲かせられず、殿さまに牢屋にいれられてしまいます。
・花さかじい(大分のむかし話/大分県小学校教育研究会国語部会編/日本標準/1975年)
大分の昔話。
正直なじいさんとばあさんが、臼で、お米をつくと 一升が二升、二升が三升と、お米が増える。
一方、よくばりばあさんが、臼をつくと、一升つきおったら五合になり、五合が二合半と半分になってしまう。
よくばりじいさん、ばあさんが 臼をつくと、ガラクタがでてくるのが定番ですが、それではかわいそうに思ったのかどうか。話者のかたの年齢が92歳と紹介されていますが、このかたが聞かれた話では、どんなふうになっていたのでしょうか。