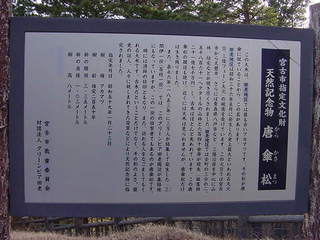一関市遊水地記念緑地のツクバネウツギ(衝羽根空木)
2007年5月16日



2007年5/16(水)、一関市総合体育館のすぐ隣にある公園
(一関遊水地記念緑地)に植えられている「ツクバネウツギ
(衝羽根空木)」が、花の内側に濃い黄橙色の網目状の模様
があるクリーム色の花を沢山咲かせていました。






ツクバネウツギ(衝羽根空木)スイカズラ科 ツクバネウツギ属
Abelia spathulata
山地に生える落葉低木。よく枝分かれして、高さは2mほど
になる。樹皮は灰白色。葉は対生し、長さ2~5cmの広卵形ま
たは長楕円形。縁はしばしば紫色を帯びる。
5月ごろ、枝先に長さ2~3cmのクリーム(淡黄色)色の花を
2個ずつ開く。花冠は筒状鐘形で、先は5浅裂する。5個の萼片
は全部同じ大きさで、プロペラのように開いている。
花の内側には濃い黄橙色の網目状の模様がある。
果実は線形。果実の先端に5個の萼片が残り、羽根つきの羽根
(衝羽根)のように見えることからこの名がある。
分布:本州、四国、九州
本州の関東地方や中部地方の深山には紅色のやや小型の花を
つける「ベニバナツクバネウツギ(紅花衝羽根空木)」が自生
する。
良く似た仲間に、本州の関東以西、四国、九州などに分布する
「オオツクバネウツギ(大衝羽根空木)」や長野、静岡県以西
から四国、九州などに分布する「コツクバネウツギ(小衝羽根
空木)」がある。
前者の花はツクバネウツギより大きく、5個の萼片のうち1個だ
けが非常に小さいという特徴があり、後者は、全体が小さく、
萼片がふつう2個、ときに3個という特徴がある。
2007年5月16日



2007年5/16(水)、一関市総合体育館のすぐ隣にある公園
(一関遊水地記念緑地)に植えられている「ツクバネウツギ
(衝羽根空木)」が、花の内側に濃い黄橙色の網目状の模様
があるクリーム色の花を沢山咲かせていました。






ツクバネウツギ(衝羽根空木)スイカズラ科 ツクバネウツギ属
Abelia spathulata
山地に生える落葉低木。よく枝分かれして、高さは2mほど
になる。樹皮は灰白色。葉は対生し、長さ2~5cmの広卵形ま
たは長楕円形。縁はしばしば紫色を帯びる。
5月ごろ、枝先に長さ2~3cmのクリーム(淡黄色)色の花を
2個ずつ開く。花冠は筒状鐘形で、先は5浅裂する。5個の萼片
は全部同じ大きさで、プロペラのように開いている。
花の内側には濃い黄橙色の網目状の模様がある。
果実は線形。果実の先端に5個の萼片が残り、羽根つきの羽根
(衝羽根)のように見えることからこの名がある。
分布:本州、四国、九州
本州の関東地方や中部地方の深山には紅色のやや小型の花を
つける「ベニバナツクバネウツギ(紅花衝羽根空木)」が自生
する。
良く似た仲間に、本州の関東以西、四国、九州などに分布する
「オオツクバネウツギ(大衝羽根空木)」や長野、静岡県以西
から四国、九州などに分布する「コツクバネウツギ(小衝羽根
空木)」がある。
前者の花はツクバネウツギより大きく、5個の萼片のうち1個だ
けが非常に小さいという特徴があり、後者は、全体が小さく、
萼片がふつう2個、ときに3個という特徴がある。