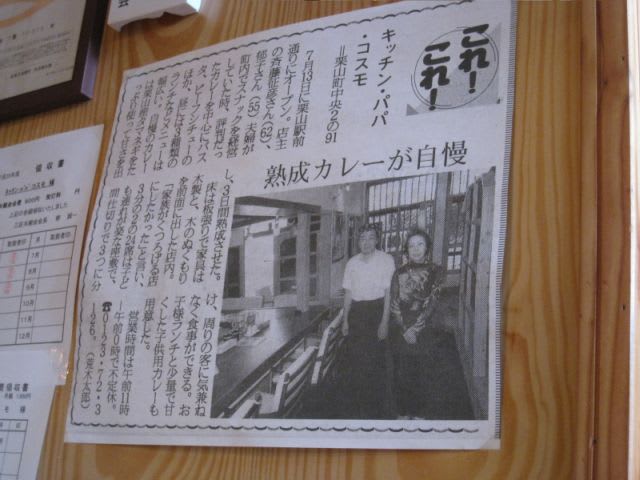新しい科学論 「事実」は理論をたおせるか, 村上陽一郎, 講談社 ブルーバックス B-373, 1979年
・話題の中心は『認識論』。人間が世界(科学)をどうとらえているのか。このテーマに対する世間一般の常識をくつがえす試み。『事実』と『理論』の戦い。勝つのはどちらか。
・何の気なしに手に取った本ですが、意外なガッチリした読み応えと面白さでした。約30年前に出版された本ですが内容に全く古さは感じません。まだまだ、現代が本書で示唆している『新しい』時代には移行していないということなのでしょう。
・「つまり科学は、善かれ悪しかれ、これまで考えられていたより何かもっとずっと人間的な営みだ、ということをわかっていただきたいのです。」p.26
・「要するに「データ」という語は《与えられたもの》という意味をもつ語であることがわかりました。ときどき「データ」に対して日本語で「所与」という難しい訳語が当てられることがあるのもそのためです。」p.33
・「その第一は、二つの観測データから一つの仮設を思いつく過程です。このような過程を、普通「帰納」ということばで呼ぶことにしています。」p.38
・「ここでは、仮設「すべてのXの足の数は三本である」から、まだ観察されていない「X3の足の数も三本であろう」という、一種の予言が導出されることが示されています。この種の導出の過程は、一般に「演繹」といわれます。ちなみに英語では、これは《deduction》と呼ばれ、「帰納」の《induction》と対をなしています。」p.44
・「哲学では、帰納は経験的、演繹は論理的という形容詞で呼ぶことがよくありますが、その意味はこれでわかっていただけたことと思います。一般に数学と論理学とは、演繹的だといわれるのも、同じ理由からです。数学では、公理を認める限り、そこから導かれる定理を認めないわけにはいかないのです。」p.47
・「アド・ホックということばはラテン語ですが、日本語にこれにぴったりのことばがない(実は、英語やその他のヨーロッパ語にも適当な語がないので、このラテン語がそのまま使われているのですが)ため、こんな呪文のような片仮名を使わせていただきます。この語の元々の意味は、「このために」ということなのです。つまり、「ある特定のこれだけのために」という意味ですが、うんと意訳をしてしまうと、アド・ホックな方法というのは、こそくな方法と言い換えられるかもしれません。全面的に書き換えるのではなく、「特定のこの」例、つまり「X3の足の数は三本でない」という観察例だけを何とかつぎはぎ的に処理しようとする方法と考えていただいてよいと思われるからです。」p.59
・「このように、時代が進んで観察データがより多く蓄積されて行くに従って、法則の側では、より包括力(包み込む力)の大きな法則に書き換えられて行く、今までに立てられていた法則を自分のなかに包み込み、さらにそこでは言われなかったいろいろな新しい事態をもうまく説明してくれるような、そういう新しい法則が立てられて行く、ということが、法則の「進歩」ということのもっとも根本的な意味の一つだ、と考えられないでしょうか。」p.78
・「「データ」という語一つのなかにも、実は、このような「人間=バケツ」論のような、認識論的な立場が隠されている、という点に気をつけておいていただきたいと思います。」p.84
・「ボルツマンという天才的な物理学者が、たいへんおもしろいことを言っています。「科学者は裸がお好き」というのです。この場合の「裸」というのは、いろいろな余計なものを取り去ってしまった、ありのままの、裸のデータ、ということなのですが、人間は、自らのなかのあらゆる先入観や偏見を捨て去り、ただひたすら眼をしっかり見開いていれば(穴をちゃんと開けていれば)、かならず、ありのままの、裸の、正しい外界からの情報をみて取ることができるのだし、科学者こそ、そうした態度を強く維持しなければならない、という信念を、これほどたくみに表現したことばもありますまい。」p.88
・「データ――帰納――法則――演繹――検証(反証)というサイクルにしても、そこに含まれる知識の「蓄積性」、科学の「進歩」、法則の「包括性」などの概念上の特徴、あるいはそれを支えるあの「バケツ理論」的認識論、そこにからんでくる「裸好き」の精神などにしても、一応大筋としては、もっともであるとお考えになる方がかなりいらっしゃるでしょう。」p.94
・「コペルニクスの『天球の回転について』を読んでいて気づくことは、これの頭のなかにはつねに、この世界を支配しているのが神(もちろんこの場合はキリスト教的な神ですが)である、という基本図式が存在していたことです。」p.104
・「今ここにあげた人びとは、いずれも、ふつうは近代科学の基礎を築いた科学者と考えられています。中世の宗教的迷妄を打破し、近代的で合理的な自然科学を建設するのにもっとも力があったと考えられている人たちです。 ところがコペルニクスやケプラーやニュートンはもちろんのこと、キリスト教会から厳しい迫害を受けたと信じられているガリレオさえ、熱誠溢れるキリスト教的な神への信仰に燃えていた、というのはどういうことなのでしょうか。」p.111
・「ここで一つの提案をしてみましょう。その提案は、かなり大胆なものに思われるかもしれませんが、わたくしどもが外の世界を見て取れるのは、先入観や偏見あってのことなのだ、と考えてしまってはどうか、というものなのです。裸の目というのはカメラのレンズと同じであって、それは何も見ていないのと同じことになるのだ、と考えてしまってはどうか、ということなのです。」p.136
・「もう少しだいたんに言えば、わたくしどもが知っているこの花は紅、柳は緑の世界のありさまは、もっとも根本的なところで、わたくしども自身、すなわち人間が最初からア・プリオリに与えられている生理的な能力の篩(ふるい)を通じて、選びとられたものだ、と考えてもよいのではないでしょうか。」p.152
・「何だか話がややこしくなったようですが、要は、かりに、わたくしが「赤」と「青」に関して、通常の人びとと全く反対の感覚知覚をもっていたとしても、それをはっきりさせる手段はまったくない、ということなのです。もちろんそこには条件があります。通常の人が「青」色の感覚としてもっているものに、わたくしが(通常の人の)「赤」色の感覚をもったとしても、わたくしはそれを「あお」という名まえで呼ぶことができ、かつ「あお」という名まえによって制御されるもろもろの行動(例えば交差点で歩くとか、車を進めるとかの)を支障なく行っている限りは、という条件が必要です。」p.156
・「例えば電気スタンドの柄の部分が、電気スタンドの柄であると認知されるためには、それが、背景の部分からは独立して受け取られなければならないことは、おわかりいただけると思いますが、その部分のある色の面分が背景の一部なのか、まさしく電気スタンドの柄であるのかは、自分の視点をずらしてみれば、その部分と他の背景の部分との関係の変化によってわかります。しかし、視点をずらすということは、今まで見えていた部分のうちの何がしかが見えなくなり、今まで見えていなかった部分の何がしかが見えるようになったということです。そしてそのときには、すでにどのような部分が見えてくるかをあらかじめ知っていなければ、言い換えればこのような情勢の変化に伴なって「電気スタンド」というもの(あるいはその柄)が、どのように見えるはずなのかをあらかじめ知っていなければならないでしょう。」p.161
・「「事実」が「人の手で造り出された虚構」である、というのはいかにもふしぎなようですが、先に述べたように「見る」という行為がそもそも、人間の側からの「造り出す」という作業を含んでいるとすれば、それは当然なことになるでしょう。「裸の事実」というのはむしろあり得ず、あるのはつねに、人間の側のある働きを媒介として「造り出された事実」であることになるからです。」p.166
・「ただ、ここで非常に奇妙な論点が現れてきたことになります。と言いますのも、第一章でご紹介したような、科学についての常識的な考え方に従えば、理論は、データから、帰納によって造られることになっていました。しかし、ここに到って事態は完全に逆転したからです。「事実」が科学理論によって造られるものと考えられることになりました。この逆転こそ、わたくしがこの本で申し上げようとしていることの一つの中心となるものです。」p.180
・「そこで科学理論の変換の起こる過程は、単に特定の科学理論の場面だけでの操作が関与しているのではなく、それを組み込んでいる全体的な世界像や自然観などとの有機的な構造の総体が関与している、ということだけはいえると思います。」p.194
・「要するに、現代の科学は、その長所も欠点も、わたくしども自身のもっている価値観やものの考え方の関数として存在していることを自覚することから、わたくしどもは出発すべきではないでしょうか。今日の自然科学は、今日のわたくしども人間存在の様態を映し出す鏡なのです。」p.201
?アマルガム(英amalgam フランスamalgame) 1 水銀と他の金属との合金の総称。歯科用はスズやカドミウムを使う。 2 (比喩的に)異種のものが融合したものをいう。
・話題の中心は『認識論』。人間が世界(科学)をどうとらえているのか。このテーマに対する世間一般の常識をくつがえす試み。『事実』と『理論』の戦い。勝つのはどちらか。
・何の気なしに手に取った本ですが、意外なガッチリした読み応えと面白さでした。約30年前に出版された本ですが内容に全く古さは感じません。まだまだ、現代が本書で示唆している『新しい』時代には移行していないということなのでしょう。
・「つまり科学は、善かれ悪しかれ、これまで考えられていたより何かもっとずっと人間的な営みだ、ということをわかっていただきたいのです。」p.26
・「要するに「データ」という語は《与えられたもの》という意味をもつ語であることがわかりました。ときどき「データ」に対して日本語で「所与」という難しい訳語が当てられることがあるのもそのためです。」p.33
・「その第一は、二つの観測データから一つの仮設を思いつく過程です。このような過程を、普通「帰納」ということばで呼ぶことにしています。」p.38
・「ここでは、仮設「すべてのXの足の数は三本である」から、まだ観察されていない「X3の足の数も三本であろう」という、一種の予言が導出されることが示されています。この種の導出の過程は、一般に「演繹」といわれます。ちなみに英語では、これは《deduction》と呼ばれ、「帰納」の《induction》と対をなしています。」p.44
・「哲学では、帰納は経験的、演繹は論理的という形容詞で呼ぶことがよくありますが、その意味はこれでわかっていただけたことと思います。一般に数学と論理学とは、演繹的だといわれるのも、同じ理由からです。数学では、公理を認める限り、そこから導かれる定理を認めないわけにはいかないのです。」p.47
・「アド・ホックということばはラテン語ですが、日本語にこれにぴったりのことばがない(実は、英語やその他のヨーロッパ語にも適当な語がないので、このラテン語がそのまま使われているのですが)ため、こんな呪文のような片仮名を使わせていただきます。この語の元々の意味は、「このために」ということなのです。つまり、「ある特定のこれだけのために」という意味ですが、うんと意訳をしてしまうと、アド・ホックな方法というのは、こそくな方法と言い換えられるかもしれません。全面的に書き換えるのではなく、「特定のこの」例、つまり「X3の足の数は三本でない」という観察例だけを何とかつぎはぎ的に処理しようとする方法と考えていただいてよいと思われるからです。」p.59
・「このように、時代が進んで観察データがより多く蓄積されて行くに従って、法則の側では、より包括力(包み込む力)の大きな法則に書き換えられて行く、今までに立てられていた法則を自分のなかに包み込み、さらにそこでは言われなかったいろいろな新しい事態をもうまく説明してくれるような、そういう新しい法則が立てられて行く、ということが、法則の「進歩」ということのもっとも根本的な意味の一つだ、と考えられないでしょうか。」p.78
・「「データ」という語一つのなかにも、実は、このような「人間=バケツ」論のような、認識論的な立場が隠されている、という点に気をつけておいていただきたいと思います。」p.84
・「ボルツマンという天才的な物理学者が、たいへんおもしろいことを言っています。「科学者は裸がお好き」というのです。この場合の「裸」というのは、いろいろな余計なものを取り去ってしまった、ありのままの、裸のデータ、ということなのですが、人間は、自らのなかのあらゆる先入観や偏見を捨て去り、ただひたすら眼をしっかり見開いていれば(穴をちゃんと開けていれば)、かならず、ありのままの、裸の、正しい外界からの情報をみて取ることができるのだし、科学者こそ、そうした態度を強く維持しなければならない、という信念を、これほどたくみに表現したことばもありますまい。」p.88
・「データ――帰納――法則――演繹――検証(反証)というサイクルにしても、そこに含まれる知識の「蓄積性」、科学の「進歩」、法則の「包括性」などの概念上の特徴、あるいはそれを支えるあの「バケツ理論」的認識論、そこにからんでくる「裸好き」の精神などにしても、一応大筋としては、もっともであるとお考えになる方がかなりいらっしゃるでしょう。」p.94
・「コペルニクスの『天球の回転について』を読んでいて気づくことは、これの頭のなかにはつねに、この世界を支配しているのが神(もちろんこの場合はキリスト教的な神ですが)である、という基本図式が存在していたことです。」p.104
・「今ここにあげた人びとは、いずれも、ふつうは近代科学の基礎を築いた科学者と考えられています。中世の宗教的迷妄を打破し、近代的で合理的な自然科学を建設するのにもっとも力があったと考えられている人たちです。 ところがコペルニクスやケプラーやニュートンはもちろんのこと、キリスト教会から厳しい迫害を受けたと信じられているガリレオさえ、熱誠溢れるキリスト教的な神への信仰に燃えていた、というのはどういうことなのでしょうか。」p.111
・「ここで一つの提案をしてみましょう。その提案は、かなり大胆なものに思われるかもしれませんが、わたくしどもが外の世界を見て取れるのは、先入観や偏見あってのことなのだ、と考えてしまってはどうか、というものなのです。裸の目というのはカメラのレンズと同じであって、それは何も見ていないのと同じことになるのだ、と考えてしまってはどうか、ということなのです。」p.136
・「もう少しだいたんに言えば、わたくしどもが知っているこの花は紅、柳は緑の世界のありさまは、もっとも根本的なところで、わたくしども自身、すなわち人間が最初からア・プリオリに与えられている生理的な能力の篩(ふるい)を通じて、選びとられたものだ、と考えてもよいのではないでしょうか。」p.152
・「何だか話がややこしくなったようですが、要は、かりに、わたくしが「赤」と「青」に関して、通常の人びとと全く反対の感覚知覚をもっていたとしても、それをはっきりさせる手段はまったくない、ということなのです。もちろんそこには条件があります。通常の人が「青」色の感覚としてもっているものに、わたくしが(通常の人の)「赤」色の感覚をもったとしても、わたくしはそれを「あお」という名まえで呼ぶことができ、かつ「あお」という名まえによって制御されるもろもろの行動(例えば交差点で歩くとか、車を進めるとかの)を支障なく行っている限りは、という条件が必要です。」p.156
・「例えば電気スタンドの柄の部分が、電気スタンドの柄であると認知されるためには、それが、背景の部分からは独立して受け取られなければならないことは、おわかりいただけると思いますが、その部分のある色の面分が背景の一部なのか、まさしく電気スタンドの柄であるのかは、自分の視点をずらしてみれば、その部分と他の背景の部分との関係の変化によってわかります。しかし、視点をずらすということは、今まで見えていた部分のうちの何がしかが見えなくなり、今まで見えていなかった部分の何がしかが見えるようになったということです。そしてそのときには、すでにどのような部分が見えてくるかをあらかじめ知っていなければ、言い換えればこのような情勢の変化に伴なって「電気スタンド」というもの(あるいはその柄)が、どのように見えるはずなのかをあらかじめ知っていなければならないでしょう。」p.161
・「「事実」が「人の手で造り出された虚構」である、というのはいかにもふしぎなようですが、先に述べたように「見る」という行為がそもそも、人間の側からの「造り出す」という作業を含んでいるとすれば、それは当然なことになるでしょう。「裸の事実」というのはむしろあり得ず、あるのはつねに、人間の側のある働きを媒介として「造り出された事実」であることになるからです。」p.166
・「ただ、ここで非常に奇妙な論点が現れてきたことになります。と言いますのも、第一章でご紹介したような、科学についての常識的な考え方に従えば、理論は、データから、帰納によって造られることになっていました。しかし、ここに到って事態は完全に逆転したからです。「事実」が科学理論によって造られるものと考えられることになりました。この逆転こそ、わたくしがこの本で申し上げようとしていることの一つの中心となるものです。」p.180
・「そこで科学理論の変換の起こる過程は、単に特定の科学理論の場面だけでの操作が関与しているのではなく、それを組み込んでいる全体的な世界像や自然観などとの有機的な構造の総体が関与している、ということだけはいえると思います。」p.194
・「要するに、現代の科学は、その長所も欠点も、わたくしども自身のもっている価値観やものの考え方の関数として存在していることを自覚することから、わたくしどもは出発すべきではないでしょうか。今日の自然科学は、今日のわたくしども人間存在の様態を映し出す鏡なのです。」p.201
?アマルガム(英amalgam フランスamalgame) 1 水銀と他の金属との合金の総称。歯科用はスズやカドミウムを使う。 2 (比喩的に)異種のものが融合したものをいう。