本日はちょっと変わり種のオムニバス作品として、ワーナーブラザーズが総勢27人ものトロンボーン奏者を起用して作り上げた「トロンボーンズ・インク」をご紹介します。録音されたのは1958年12月。1曲目から5曲目が東海岸ニューヨークのセッションで、トロンボーンの第一人者であるJ・J・ジョンソンが合計11本のトロンボーン・アンサンブルをアレンジしています(ちなみに彼自身は演奏しません)。メンバーはフランク・リハック、ジミー・クリーヴランド、ボブ・ブッルクマイヤー、エディ・バート、メルバ・リストン、ベニー・パウエル、ヘンリー・コーカー、ベニー・グリーンらで、さらにピアノのハンク・ジョーンズがキラリと光るソロでアクセントをつけてくれます。6曲目から11曲目は西海岸ロサンゼルスでのセッションで、合計16人ものトロンボーン奏者が参加しています。うちソロを取るのはフランク・ロソリーノ、ボブ・エネヴォルセン、ステュ・ウィリアムソン、デイヴ・ウェルズらです。こちらはマーティ・ペイチがアレンジャーまたはピアニストとして参加しています。
演奏は複数のトロンボーンによる重厚なアンサンブルをバックに、各トロンボーン奏者がソロを取るという、まさにトロンボーン尽くしの内容。トランペットやサックスに比べ地味な印象が強いトロンボーンですが、さすがに東西のジャズシーンを代表する名手が揃っているだけあってアンサンブルにソロに聴き所たっぷりです。お薦めは東海岸セッションが、各人が次々とソロを受け渡す疾走感あふれる“Neckbones”“Tee Jay”、アンサンブルの美しいバラード“Long Before I Knew You”。西海岸セッションが急速調の“Lassus Trombone”、美しいバラードの“Polka Dots And Moonbeams”“Impossible”でいずれもフランク・ロソリーノが高らかに成り響く素晴らしいソロを聴かせてくれます。最後にソロのリレーで締めくくる“Heat Wave”もいいですね。どちらかと言うと西海岸セッションの方が完成度が高いと思います。古今東西ここまでトロンボーンに特化した作品も少ないですが、決してマニア向けの珍品ではなく普通のビッグバンドジャズとして楽しめる造りになっているのがポイント高し!ですね。
50年代のハードバップ全盛期にはジャムセッション形式によるアルバムが多く録音されました。特定のリーダーがいるわけでもなく、レコード会社の呼びかけでミュージシャン達が集まり、その場限りのセッションが開かれる。演奏前におそらく簡単な打ち合わせが行われるだけで、後は参加ミュージシャンが思う存分にアドリブ演奏を行う。はっきり言ってかなりアバウトなやっつけ仕事ですが、それでも綺羅星のごとく才能溢れるジャズメン達が揃っていたこの時代には多くの名演奏が生み出されました。特にプレスティッジはジャムセッション形式の作品が多く、「オール・ナイト・ロング」「オール・デイ・ロング」「アフター・アワーズ」「テナー・コンクレイブ」「インタープレイ・フォー・2トランペッツ&2テナーズ」等多くの名盤を残しています。今日ご紹介する「ルーツ」もそのうちの1枚です。
セッションは1957年10月25日と12月6日の2回に分けて行われ、どちらもトロンボーン、トランペット、バリトンの3管編成からなるセクステットです。うち両方に参加しているのはトランペットのイドリース・スリーマンとベースのダグ・ワトキンスの2人だけで、後は10月のセッションがジミー・クリーヴランド(トロンボーン)、セシル・ペイン(バリトン)、トミー・フラナガン(ピアノ)、エルヴィン・ジョーンズ(ドラム)。12月のセッションがフランク・リハック(トロンボーン)、ペッパー・アダムス(バリトン)、ビル・エヴァンス(ピアノ)、ルイス・ヘイズ(ドラム)という顔ぶれです。
曲は全部で3曲しかありませんが、そのうち12月録音の“Roots”だけで27分を超える長尺の演奏です。ジャムセッションは明確なアレンジもなく、各人のアドリブに自由に任せるため、演奏が長くなりがちですがそれにしてもここまで長いのは珍しいですね。ゴリゴリと吹くアダムスのバリトン、力強いスリーマンのトランペット、そして意外とブルージーなピアノを弾く若き日のエヴァンスと聴き所はありますが、さすがに冗長さを感じずにはおれません。半分くらいにまとめてくれると良かったんですけど。残りの2曲は10月のセッションからの収録で、どちらも古いゴスペル曲をモダンジャズにアレンジしたもの。“Down By The Riverside”ではセシル・ペインのバリトンに続き、再びスリーマンがブリリアントなソロを聴かせます。“Sometimes I Feel Like A Motherless Child”はマイナーキーのナンバーでクリーヴランドのトロンボーン、ペインのバリトン、フラナガンのピアノとソロが受け渡されていきます。ちと暗すぎるのが難点です。以上、豪華ハードバッパーの共演ですが、内容的にはまあまあと言った感じの1枚です。
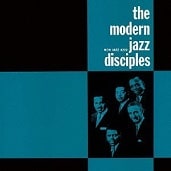
そんな得体の知れないグループですが、アルバムの中身は超がつくほどストレートな王道ハードバップです。パーカー直系の小気味良いアルトを聴かせるペグラー、バルブトロンボーンの一種であるノーマフォンを軽快に吹きならすケリー、抜群のスイング感ときらびやかなタッチでアクセントを付けるブラウン。シンシナティという地方都市でプレイしていたがために脚光を浴びることはありませんでしたが、演奏のクオリティは当時絶頂だったブルーノートの面々と比べても遜色はないと思います。選曲も素晴らしくスタンダードをアップテンポに料理した“After You've Gone”に始まり、スライド・ハンプトンの“Slippin' & Slidin'”、キャノンボール・アダレイの“Little Taste”、パーカーの“Perhaps”、リー・タッカー“Dottie”とミドルからアップテンポのバップチューンがずらりと連なります。結局一度もスターダムに登ることもなく歴史の片隅で忘れ去られた彼らですが、本作はハードバップ愛好者なら99%気に入ること間違いなしの隠れ名盤です。
半年以上クラシックばかりUPしてきましたが、その間にジャズCDの旧譜も随分発売されていましたので、またしばらくジャズに戻りたいと思います。特に最近はプレスティッジの50年代の作品が続々と再発されており、ハードバップマニアなら思わず食指が伸びる魅惑のラインナップとなっています。今日ご紹介するのはモダンジャズを代表する名ドラマーであるアート・テイラーがプレスティッジの傍系レーベルであるニュージャズに1959年に吹き込んだ1枚です。テイラーと言えばブルーノート盤「AT’Sデライト」、プレスティッジ盤「テイラーズ・ウェイラーズ」あたりはこれまでもたびたび再発されていましたが、本作は入手困難な1枚でしたので待望のゲットですね。
タイトル通りテイラーが2人のテナー奏者と共演した作品で、その2人とはフランク・フォスターとチャーリー・ラウズ。前者はカウント・ベイシー楽団で長らくフロントマンとして活躍し、後者はセロニアス・モンクの相棒として知られています。一見相反するスタイルの持ち主のように思えますが、作品のフォーマットが典型的ハードバップなので、互いに強烈な個性のようなものを前面に出さず、あくまで軽快なブロウに徹しています。なので正直ソロもどっちがどっちだか私にはわかりません。リズム・セクションはウォルター・デイヴィス・ジュニア(ピアノ)、サム・ジョーンズ(ベース)、そしてテイラーで、スインギーなデイヴィスのピアノも素晴らしいですね。なお、テイラーは特に目立ったドラムソロを披露するわけでもなく(あえて言うならラストの“Dacor”ぐらいか?)、もっぱら裏方に徹しています。リーダーというのは名目上だけみたいですね。全6曲、“Rhhythm-A-Ning”“Straight, No Chaser”という2曲のモンク・ナンバーもいいですが、個人的にはこれぞ王道ハードバップと言うべき“Cape Millie”“Fidel”がお薦めです。














