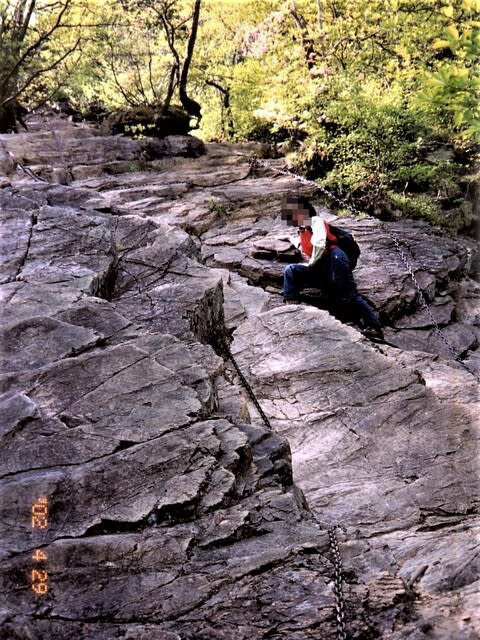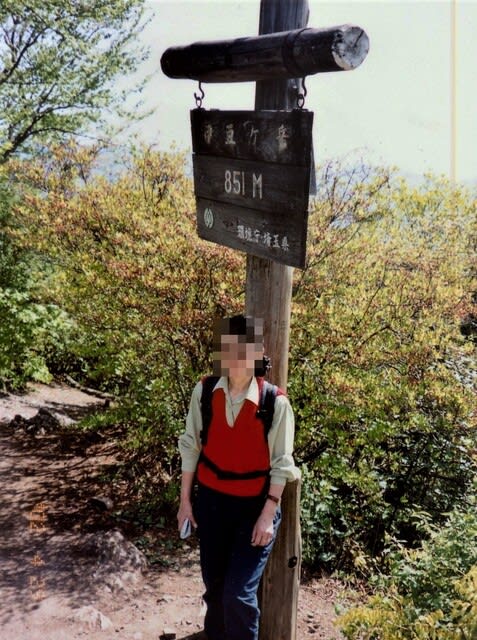1月23日、「今日は、何の日?」
ネットで検索してみると、「電子メールの日」「八甲田山の日」「真白き富士の嶺の日」「アーモンドの日」「ワンツースリーの日」等々、いろいろ有りだが、
「真白き富士の嶺の日」・・・???、
解説を読むと、1910年(明治43年)1月23日に、神奈川県鎌倉市七里ガ浜で、逗子開成中学校の生徒12人を乗せたボートが転覆し、全員が死亡する事故が有った日なのだそうだ。その追悼式に、開成中学の系列校の鎌倉女学校(現・鎌倉女学院)の教師だった三角錫子が鎮魂歌として作詞した「哀歌(真白き富士の根)」が歌われ、1915年(大正4年)には、そのレコードが発売されたのだそうだ。
子供の頃、「真白き富士の嶺」を、学校で習ったものかどうかの記憶は曖昧だが、何故か強烈に脳裏に焼きついている楽曲のひとつである。そして、「泣ける歌」でも有る。
メロディーの原曲は、アメリカの讃美歌なのだそうだ。
三角錫子 作詞
「真白き富士の根(嶺)(七里ヶ浜の哀歌)」
真白き富士の嶺、緑の江の島、
仰ぎ見るも、今は涙、
帰らぬ十二の、雄々しきみたまに、
捧げまつる、胸と心、
ボートは沈みぬ、千尋(ちひろ)の海原(うなばら)、
風も浪も、小(ち)さき腕(かいな)に、
力も尽き果て、呼ぶ名は父母、
恨みは深し、七里ヶ浜辺、
み雪は咽(むせ)びぬ、風さえ騒ぎて、
月も星も、影を潜め、
みたまよ何処に、迷いておわすか、
帰れ早く、母の胸に、
みそらにかがやく、朝日のみ光、
暗(やみ)に沈む、親の心、
黄金(こがね)も宝も、何にし集めん、
神よ早く、我も召せよ、
雲間に昇りし、昨日の月影、
今は見えぬ、人の姿、
悲しさあまりて、寝られぬ枕に、
響く波の、音も高し、
帰らぬ浪路に、友呼ぶ千鳥に、
我も恋し、失(う)せし人よ、
尽きせぬ恨みに、泣くねは共々、
今日も明日も、かくてとわに、
「真白き富士の根(嶺)(七里ヶ浜の哀歌)」・唄 ミス・コロムビア(松原 操)