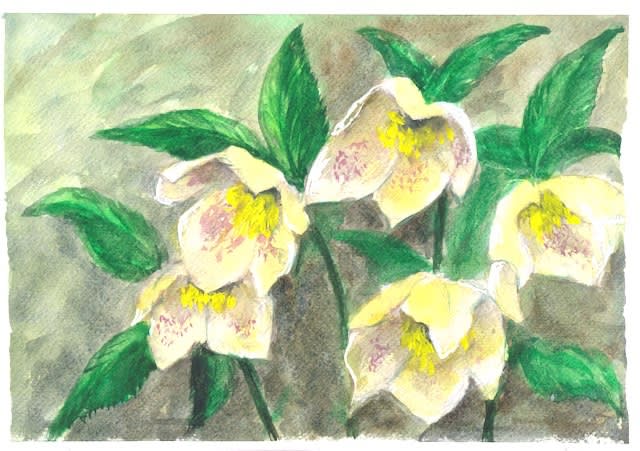
クリスマスローズ
1月28日に埼玉県八潮市の交差点で発生した大規模な道路陥没では、深さが15メートルほどの穴ができていて、土砂などが底から8メートルほどまで積み重なっているという。写真で見ると広さは20メートル四方に及び、トラックと運転者が犠牲になった。
この事故は、都市のインフラのあり方を巡って様々な問題を投げかけているように思う。
私が思うに、一番の問題は汚水処理の方法だ。
現在、各地で進められている下水管による汚水処理は、道路に沿って管を通す方法。管は昔風の土管から、今では、ポリエチレンや塩化ビニル樹脂などの合成樹脂に変えられている。劣化の度合いが違うので当然である。今回の八潮市の下水管がどんなものであったかは、詳報がないので分からないが、樹脂製のものではなかったに違いない。だから一部が劣化して漏れ出し、その汚水が浸食し道路を陥没させたのだろう。
とはいえ、丈夫な樹脂製だとしても、100年、200年と持つものではない。当然劣化が進む。同じような事故が再発する恐れがないわけではない。
問題の根本は、下水・汚水管を地中に埋め込む工法だと思う。
水の特徴は、比重が軽いこと、そして毛細管現象があること。だからどんな細い隙間でも、地上に滲み出たり、潜ったりする。そして、今回のような事故につながる。だから根本は水を地下に閉じ込めないことである。汚水といえども地下ではなく、地上に流すのが理にかなっている。
汚水を地上に流すためには、もちろん、浄化する必要がある。その浄化槽を改善し、各地に、あるいはビルごとに設置し、浄化した水を地上で流す。
大岡昇平が「少年時代」で明治期の渋谷周辺の様子を聞き語り風の書いているところによると、今は暗渠になっている渋谷川が雨が降るとよく氾濫したそうだ。渋谷は名の通り谷になっていて雨水が流れ込む地形であるから当然である。それを整備し、暗渠として埋め込んで、現在の渋谷の繁栄を築いている。渋谷周辺の下水道はどうなっているのか、心配である。
技術が未熟だった時代は、雨水を管理するのは、土管で地中に埋め込むしかなかったことだったろう。しかし、現代はもっと違う方法があるはず。
汚水は浄化して地上に流そう。それが自然に適った方法である。そのための技術を開発しないと、地中に埋め込んだ下水管はまた必ず破損し、道路を陥没させることになる。側溝に清水が流れている情景は、この上もなく好ましいはずだ。【彬】


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます