
ODA予算は、1997年度の 1兆1687億円をピークに減少傾向にあるのですね。世界第二位のGDPを誇る経済大国の中国に対しても、いまだ支援が継続されていることは、諸兄がご承知の通りです。
ODAを実施して、その仕事を自国企業も受注して恩恵にあずかる。国内で財政投資をして、経済を活性化させるものを海外にも展開したことになる政策です。中国が盛んに行う札束外交でもあり、日本のこのビジネスモデルを真似たものですが、日本との違いは、たとえば、公共の建設工事を行う場合、受注を中国企業が取り込み、場合によっては労働者も中国から同道させ、全ての利益を中国が吸い上げるという方式です。中国の支援を喜んでいた国々やその国民も、その戦略に気づき始めているのですね。
ODA予算が減っている日本ですが、中国を真似た訳ではないのでしょうが、新たな「開発協力大綱」を閣議決定し、日本の国益を重視した内容となる様軌道修正されたのですね。ただし中国と異なるのは、相手国とウインウインの関係を築くことを掲げている点です。
少子高齢化で人口が減り続け、市場が縮小し、国内投資先も減っていく日本は、海外市場も取り込んで、活性化を計らねばならないのです。アベノミクス第三の矢は、実質経済の成長力アップを進める本命政策が必要ですが、決め手がなく低迷しています。国益を重視したODAは、柱のひとつとなりえますので、この方向転換は、期待しています。
開発協力大綱の決定 ; 外務省国際協力局
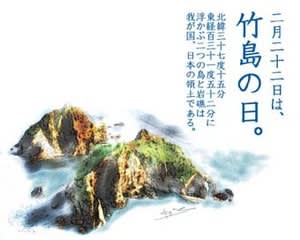
竹島に関する動画 / 政府広報 - YouTube
↓よろしかったら、お願いします。




ODAを実施して、その仕事を自国企業も受注して恩恵にあずかる。国内で財政投資をして、経済を活性化させるものを海外にも展開したことになる政策です。中国が盛んに行う札束外交でもあり、日本のこのビジネスモデルを真似たものですが、日本との違いは、たとえば、公共の建設工事を行う場合、受注を中国企業が取り込み、場合によっては労働者も中国から同道させ、全ての利益を中国が吸い上げるという方式です。中国の支援を喜んでいた国々やその国民も、その戦略に気づき始めているのですね。
ODA予算が減っている日本ですが、中国を真似た訳ではないのでしょうが、新たな「開発協力大綱」を閣議決定し、日本の国益を重視した内容となる様軌道修正されたのですね。ただし中国と異なるのは、相手国とウインウインの関係を築くことを掲げている点です。
少子高齢化で人口が減り続け、市場が縮小し、国内投資先も減っていく日本は、海外市場も取り込んで、活性化を計らねばならないのです。アベノミクス第三の矢は、実質経済の成長力アップを進める本命政策が必要ですが、決め手がなく低迷しています。国益を重視したODAは、柱のひとつとなりえますので、この方向転換は、期待しています。
開発協力大綱の決定 ; 外務省国際協力局
ODA 外交戦略に活用 元対象国も支援 カリブ・中東 (2/11 読売朝刊 [スキャナー])
政府は10日、今後の政府開発援助(ODA)に関して、日本の国益の確保を重視する姿勢を打ち出した新たな「開発協力大綱」を閣議決定した。ODA予算の減少が続く中、戦略を明確に持ち、効果的に活用する狙いがある。(政治部 石川有希子、仲川高志)
国連票・石油供給狙う
「日本と援助される側が(双方に利益をもたらす)ウィンウィンの関係を作り上げる協力のあり方を目指さなければいけない」
岸田外相は10日の記者会見で、援助相手国との関係強化に意欲を示した。
政府が開発協力大綱で新たに可能にしたのは、決して低所得とは言えない国への支援だ。従来は、経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会が定めた「1人当たりの国民総所得1万2745ドル以下」のODA対象国に援助してきた。それを、この基準を上回った「ODA卒業国」も、戦略的に重要と判断した場合は支援できるようにした。
政府が当面、想定しているのは、カリブ諸国のODA卒業国であるバルバドス、トリニダード・トバゴなど4か国だ。いずれも国民総所得は基準を上回るが、ハリケーンなどの自然災害や地球温暖化に伴う海面上昇など、小さな島国特有の課題を抱えている。
昨年7月、トリニダード・トバゴで行われた安倍首相と「カリブ共同体」(14か国・1地域)との首脳会合では、バルバドスのスチュワート首相が「OECDの基準で『卒業』させられている。財政余力がなく、国内の生活改善の投資ができない」と訴えた。相次ぐ日本への期待に、安倍首相はODA卒業国を支援する方針を伝えた。すでに国際協力機構(JICA)は、省エネの技術協力や防災対策、水産資源の保護の3分野で可能な支援について調査を始めている。
政府がカリブ諸国のような小国に焦点をあてるのは、国連安全保障理事会の常任理事国入りを目指す日本として、国連改革にあたり、より多くの支持国を増やしたいからだ。外務省幹部は「国連で計14票を持つカリブ共同体は一致した行動を取ることが多く、日本が支援する効果は高い」と狙いを語る。
政府が警戒しているのは、途上国を中心に積極的な投資や援助を展開する中国の動きだ。中国は今年1月、中南米とカリブ諸国との閣僚級会議を北京で開き、総額300億ドルの借款の供与や投資の拡大を約束した。日本政府関係者は「中国の物量には対抗できないが、省エネなど日本の強みを生かした質重視の支援で浸透したい」と話す。
政府はカリブ諸国以外では、オマーンやアラブ首長国連邦(UAE)など中東湾岸諸国への支援も検討している。産油国で資金力は豊富だが、省エネやゴミ処理などで技術協力を要請している。原油を運ぶシーレーン(海上交通路)に面した湾岸諸国に、日本の得意分野で協力し、エネルギーの安定供給につなげたい考えだ。
日本はODAを対外貢献の柱として、1997年度まで援助を増額させてきた。ただ、財政の悪化に伴い、ODA予算は減少傾向が続く。かつて世界1位だったODA支出額は、2013年は4位となり、量から質への転換を迫られている。国益との結び付きを重視するのはこうした背景があり、岸田外相は10日の記者会見で「新大綱の下、より戦略的な開発協力を推進する」と強調した。
-----------------------------------
◆政府開発援助(ODA=Official Development Assistance)
政府機関が開発途上国の経済開発や福祉向上のために行う援助。〈1〉主に基礎生活分野を対象とする「無償資金協力」(贈与)〈2〉社会資本整備事業などに長期低利で融資する有償資金協力(円借款)〈3〉専門家派遣などの技術協力〈4〉国際機関への拠出――に大別される。予算は1997年度の1兆1687億円をピークに減少傾向にあり、2015年度予算案では5422億円とほぼ半減した。
-----------------------------------
「非軍事に限定」厳格運用
新大綱は、他国の軍隊でも、非軍事分野には支援する方針を明文化し、軍事転用の恐れがないか個別具体的に検討することにした。国によっては、災害救助や紛争後の復旧・復興などを軍が担っているケースがあるためだ。
外務省によると、過去にも非軍事分野にODAを使った例はある。西アフリカ・セネガルの軍病院の産科棟を改修したケースがその一つで、「一般人も多く利用する西アフリカ随一の拠点医療機関であり、母子保健の向上のためには支援する必要性がある」(幹部)と判断したという。
ただ、「軍事的用途と国際紛争助長への使用を回避」するとの原則は維持する。軍事転用や流用の恐れがないかを詳細に調査するとともに、相手国政府から証文などで確約を取るなど、非軍事分野への支援であるか厳格に運用する方針だ。
日本は「非軍事分野への支援」に細心の注意を払っている。例えば、政府機関が主催するセミナーに識者として軍幹部を招く際は、防衛省や自衛隊の関係者と接触しないことを条件とする。沿岸警備を目的に巡視艇の供与を求められても、相手国の軍と海上警察が一体となっている場合は軍事転用が疑われるため、応じないという。
岸田外相は10日の記者会見で、「非軍事目的の活動でも軍が重要な役割を果たすようになっている」と指摘する一方、「国民から理解され、(運用の)透明性を高めるような取り組みは重要だ」と述べた。
政府は10日、今後の政府開発援助(ODA)に関して、日本の国益の確保を重視する姿勢を打ち出した新たな「開発協力大綱」を閣議決定した。ODA予算の減少が続く中、戦略を明確に持ち、効果的に活用する狙いがある。(政治部 石川有希子、仲川高志)
国連票・石油供給狙う
「日本と援助される側が(双方に利益をもたらす)ウィンウィンの関係を作り上げる協力のあり方を目指さなければいけない」
岸田外相は10日の記者会見で、援助相手国との関係強化に意欲を示した。
政府が開発協力大綱で新たに可能にしたのは、決して低所得とは言えない国への支援だ。従来は、経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会が定めた「1人当たりの国民総所得1万2745ドル以下」のODA対象国に援助してきた。それを、この基準を上回った「ODA卒業国」も、戦略的に重要と判断した場合は支援できるようにした。
政府が当面、想定しているのは、カリブ諸国のODA卒業国であるバルバドス、トリニダード・トバゴなど4か国だ。いずれも国民総所得は基準を上回るが、ハリケーンなどの自然災害や地球温暖化に伴う海面上昇など、小さな島国特有の課題を抱えている。
昨年7月、トリニダード・トバゴで行われた安倍首相と「カリブ共同体」(14か国・1地域)との首脳会合では、バルバドスのスチュワート首相が「OECDの基準で『卒業』させられている。財政余力がなく、国内の生活改善の投資ができない」と訴えた。相次ぐ日本への期待に、安倍首相はODA卒業国を支援する方針を伝えた。すでに国際協力機構(JICA)は、省エネの技術協力や防災対策、水産資源の保護の3分野で可能な支援について調査を始めている。
政府がカリブ諸国のような小国に焦点をあてるのは、国連安全保障理事会の常任理事国入りを目指す日本として、国連改革にあたり、より多くの支持国を増やしたいからだ。外務省幹部は「国連で計14票を持つカリブ共同体は一致した行動を取ることが多く、日本が支援する効果は高い」と狙いを語る。
政府が警戒しているのは、途上国を中心に積極的な投資や援助を展開する中国の動きだ。中国は今年1月、中南米とカリブ諸国との閣僚級会議を北京で開き、総額300億ドルの借款の供与や投資の拡大を約束した。日本政府関係者は「中国の物量には対抗できないが、省エネなど日本の強みを生かした質重視の支援で浸透したい」と話す。
政府はカリブ諸国以外では、オマーンやアラブ首長国連邦(UAE)など中東湾岸諸国への支援も検討している。産油国で資金力は豊富だが、省エネやゴミ処理などで技術協力を要請している。原油を運ぶシーレーン(海上交通路)に面した湾岸諸国に、日本の得意分野で協力し、エネルギーの安定供給につなげたい考えだ。
日本はODAを対外貢献の柱として、1997年度まで援助を増額させてきた。ただ、財政の悪化に伴い、ODA予算は減少傾向が続く。かつて世界1位だったODA支出額は、2013年は4位となり、量から質への転換を迫られている。国益との結び付きを重視するのはこうした背景があり、岸田外相は10日の記者会見で「新大綱の下、より戦略的な開発協力を推進する」と強調した。
-----------------------------------
◆政府開発援助(ODA=Official Development Assistance)
政府機関が開発途上国の経済開発や福祉向上のために行う援助。〈1〉主に基礎生活分野を対象とする「無償資金協力」(贈与)〈2〉社会資本整備事業などに長期低利で融資する有償資金協力(円借款)〈3〉専門家派遣などの技術協力〈4〉国際機関への拠出――に大別される。予算は1997年度の1兆1687億円をピークに減少傾向にあり、2015年度予算案では5422億円とほぼ半減した。
-----------------------------------
「非軍事に限定」厳格運用
新大綱は、他国の軍隊でも、非軍事分野には支援する方針を明文化し、軍事転用の恐れがないか個別具体的に検討することにした。国によっては、災害救助や紛争後の復旧・復興などを軍が担っているケースがあるためだ。
外務省によると、過去にも非軍事分野にODAを使った例はある。西アフリカ・セネガルの軍病院の産科棟を改修したケースがその一つで、「一般人も多く利用する西アフリカ随一の拠点医療機関であり、母子保健の向上のためには支援する必要性がある」(幹部)と判断したという。
ただ、「軍事的用途と国際紛争助長への使用を回避」するとの原則は維持する。軍事転用や流用の恐れがないかを詳細に調査するとともに、相手国政府から証文などで確約を取るなど、非軍事分野への支援であるか厳格に運用する方針だ。
日本は「非軍事分野への支援」に細心の注意を払っている。例えば、政府機関が主催するセミナーに識者として軍幹部を招く際は、防衛省や自衛隊の関係者と接触しないことを条件とする。沿岸警備を目的に巡視艇の供与を求められても、相手国の軍と海上警察が一体となっている場合は軍事転用が疑われるため、応じないという。
岸田外相は10日の記者会見で、「非軍事目的の活動でも軍が重要な役割を果たすようになっている」と指摘する一方、「国民から理解され、(運用の)透明性を高めるような取り組みは重要だ」と述べた。
記事では、国連常任理事国入りの票獲得を目標のひとつに挙げています。この点については、遊爺は反対です。まさに、票をお金で買おうとしているのが見え見えである(相手国は心から喜ぶでしょうか)ことがひとつと、そもそも常任理事国入りは可能なのか。中国が居て拒否権が使用できる限り、困難です。戦勝国が主役の集まりの国連ですから、「敵国条項」も手つかずで残ったままです。もしも、拒否権を無くすなど、国連改革を達成できたとしても、常任理事国になることによって、どんな利益があるのでしょう。誤ったプロパガンダで、慰安婦は性奴隷と言って、過ちを認めない輩の集団です。国際紛争を収める力も亡くなってきています。
二国間や、グループ(例=TPP)での相互発展を計る活動に注力すべきです。政治的には、力で覇権を拡大する中国の抑止力を構築することに注力したほうが、アジアや世界の平和によほど貢献します。
余談ですが、中国へのODAは、止めるといいつつ止められていません。もういいかげんにすべきですね。
経済大国となった中国になぜODAは支払われるのか?(1)79年から合計額は3兆3164億円に… | アサ芸プラス
非軍事目的と、軍事目的の線引きは微妙ですね。双方の国にとってメリットが大きい支援は何か。世界の平和と発展に役立つものなのか否か。ODAの出発の理念に立ち戻って判断することですね。
# 冒頭の画像は、「開発協力大綱」の閣議決定に臨む安倍首相と閣僚
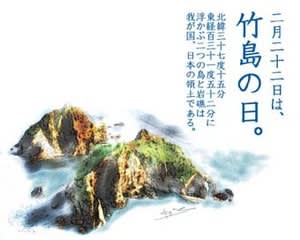
竹島に関する動画 / 政府広報 - YouTube
↓よろしかったら、お願いします。



 |
 |


























