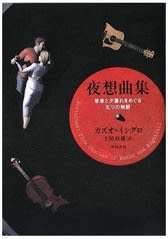学齢前は朝から夜までが永久に近い長さがあったように思うが,このごろはあっという間だ.しかし,現在と,たとえば20台を比べてどうか と言われるとあまりはっきりしない.
書店で
A 一川 誠「大人の時間はなぜ短いのか」集英社新書 (2008/09)
を見かけたので,ネットでチェックしたら
B 竹内薫 「一年は、なぜ年々速くなるのか」 青春新書INTELLIGENCE (2008/11)
もあった.2 冊とも市の図書館で借り出した.
B のほうが後発だが,B のあとがきにあるように,執筆は同時期だったらしい.A の著者は文科系,B は理科系.B では時間が逆行しない理由としてエントロピーを紹介しているところが理科系らしい.B のほうは科学エッセイ,A はもうすこし踏み込んだ啓蒙書という感じがしないでもない.
この 2 冊はすぐに読めてしまった.
学齢前の1日が長かったのは B にあるように「ゾウの時間ネズミの時間」説で説明がつきそうだ.しかしそれ以上に何がはっきりしたかと考えると疑問.要するに定説はない,ということらしい.
「体感時間は年齢に反比例する」というのが,A ではジャネーの法則,B ではマリリン・ダプカスの説として紹介されている.この法則 (仮設?) の内容を,A はたいして評価せず,B は「さらに深い原因から生じた表面的な結果」としている.
自分を例にとると,朝は早く目が覚め,夜はすぐ眠くなる.J 子はそうではない.こちらの体内時計では1日が24時間より短く,J 子では長いのかもしれない (個人差大!).
自分は熱しやすく冷めやすい...飽きっぽい...のだが,これは体内時計と関係しているのだろうか.しかしこの性格が年齢とともに顕著になったということはない,と思う.
でもジャズのアドリブでひどいときは 4 小節単位で跳ばしたりするのは,やはり歳のせい?
書店で
A 一川 誠「大人の時間はなぜ短いのか」集英社新書 (2008/09)
を見かけたので,ネットでチェックしたら
B 竹内薫 「一年は、なぜ年々速くなるのか」 青春新書INTELLIGENCE (2008/11)
もあった.2 冊とも市の図書館で借り出した.
B のほうが後発だが,B のあとがきにあるように,執筆は同時期だったらしい.A の著者は文科系,B は理科系.B では時間が逆行しない理由としてエントロピーを紹介しているところが理科系らしい.B のほうは科学エッセイ,A はもうすこし踏み込んだ啓蒙書という感じがしないでもない.
この 2 冊はすぐに読めてしまった.
学齢前の1日が長かったのは B にあるように「ゾウの時間ネズミの時間」説で説明がつきそうだ.しかしそれ以上に何がはっきりしたかと考えると疑問.要するに定説はない,ということらしい.
「体感時間は年齢に反比例する」というのが,A ではジャネーの法則,B ではマリリン・ダプカスの説として紹介されている.この法則 (仮設?) の内容を,A はたいして評価せず,B は「さらに深い原因から生じた表面的な結果」としている.
自分を例にとると,朝は早く目が覚め,夜はすぐ眠くなる.J 子はそうではない.こちらの体内時計では1日が24時間より短く,J 子では長いのかもしれない (個人差大!).
自分は熱しやすく冷めやすい...飽きっぽい...のだが,これは体内時計と関係しているのだろうか.しかしこの性格が年齢とともに顕著になったということはない,と思う.
でもジャズのアドリブでひどいときは 4 小節単位で跳ばしたりするのは,やはり歳のせい?