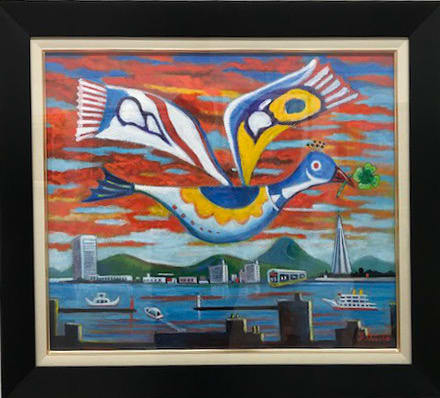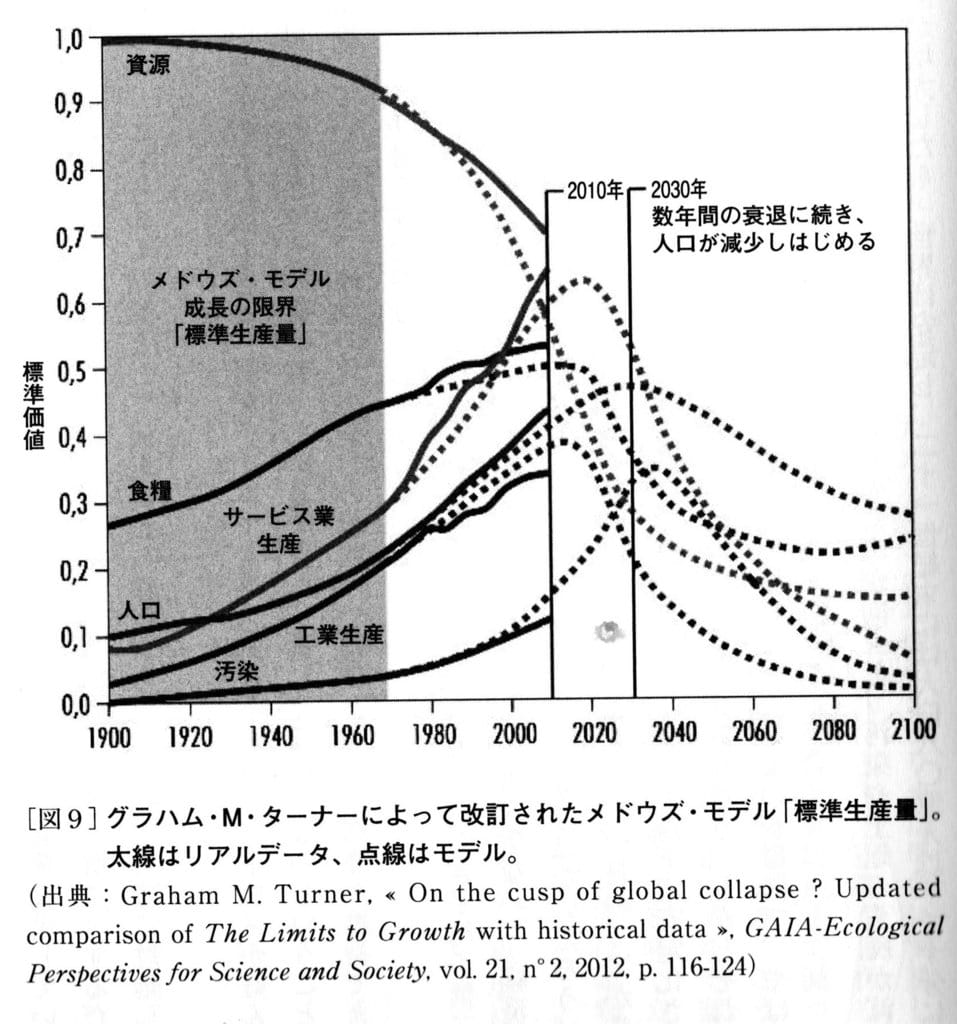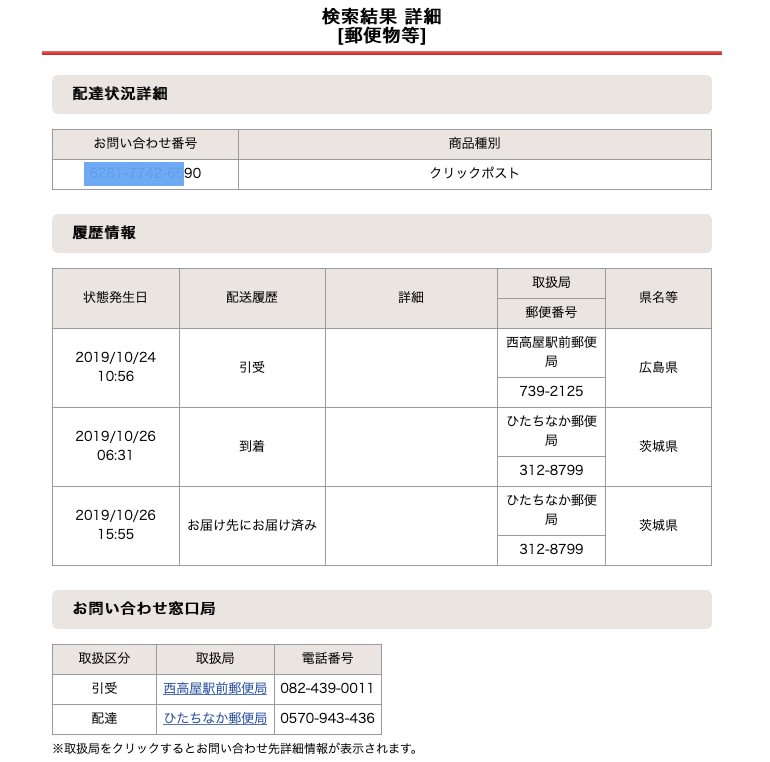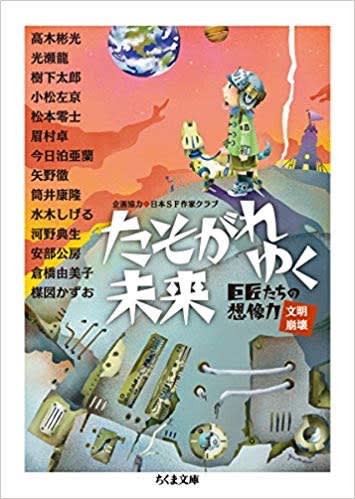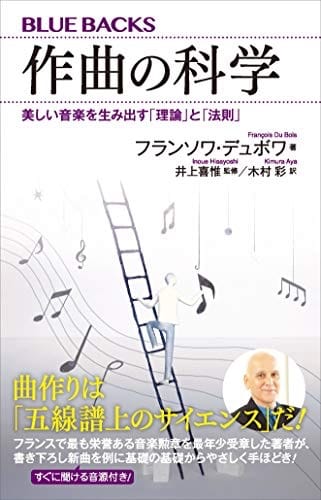フランソワ・デュポア,木村彩 訳,井上 喜惟 監修.
いわゆる翻訳本と異なり,フルーバックスを対象にしたフランス語による書き下ろしを,日本語に直したように思う...ちがうかな? 著者の慶應義塾大学での講義が下敷きになっているのかもしれない.訳文は,です・ますの口語調で読みやすい.音源をウェブの特設サイトで聴きながら読み進めることができる.
内容は
第1楽章 作曲は「足し算」である──音楽の「横軸」を理解する
第2楽章 作曲は「かけ算」である──音楽の「縦軸」を理解する
第3楽章 作曲のための「語彙」を増やす──楽器の個性を知るということ
第4楽章 作曲の極意──書き下ろし3曲で教えるプロのテクニック
第1-3楽章は楽典の説明と著者自身の経験を中心としたエピソード.この本のタイトルに惹かれて購読する人なら,第4楽章から読み始め,必要に応じて前を参照する程度で良さそう.
第1・第2楽章の,横軸は足し算,縦軸は掛け算の意味はよくわからない.理工系なら,楽譜の横軸は線形目盛り,縦軸はいわば対数目盛りと言ってしまいたいところだが,そう解釈していいのだろうか.
そういえば,本のタイトルの「科学」の意味も,他のブルーバックス本の意図する科学とは違うようだ.ここでは音楽を生み出す「理論」と「法則」を記述していることが,「科学」なんだろう.
著者は有名な作曲家にしてマリンバ奏者だそうだが,第4楽章に挙げられた曲例の作曲者は,Chic,Gibson Brothers, Dianna Ross, Barry Manilow, Grover Washington Jr., Eagles, Beatles, Queen, Eminem... と,クラシックやジャズのひとはほとんどいない.この第4楽章は,モード,コード(王道コード進行),作曲指南の順番.正統的な作曲の教科書は知らないが,わかりやすかった.
第4楽章はコード→メロディではなく,メロディ→コードを勧めている.この方法で
パン音階の曲を書いてみたいとは思うが (昔書いた曲が
ここにあります),第1-3楽章の内容をこの音階向けに構築し直すことから始めなければならないだろう.
単純作業はAIに取って代わられる,ヒトが為すべきは創造的作業といわれる.しかし作曲はAIにとって最も取り組みやすい創造的作業のひとつ.作曲を「科学」すればするほど,AIに付け込まれやすくなりそうだ.