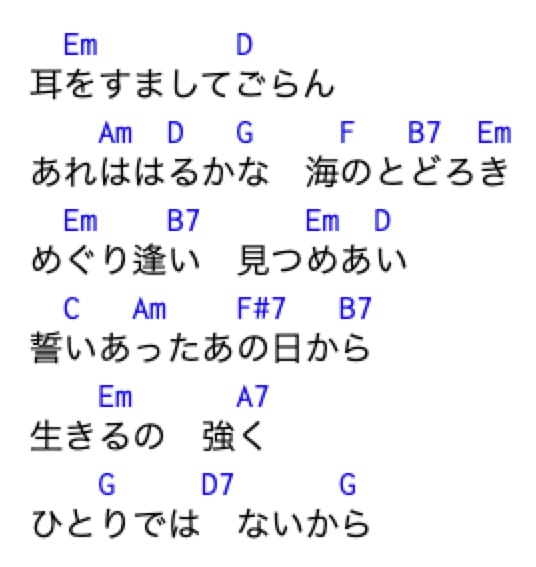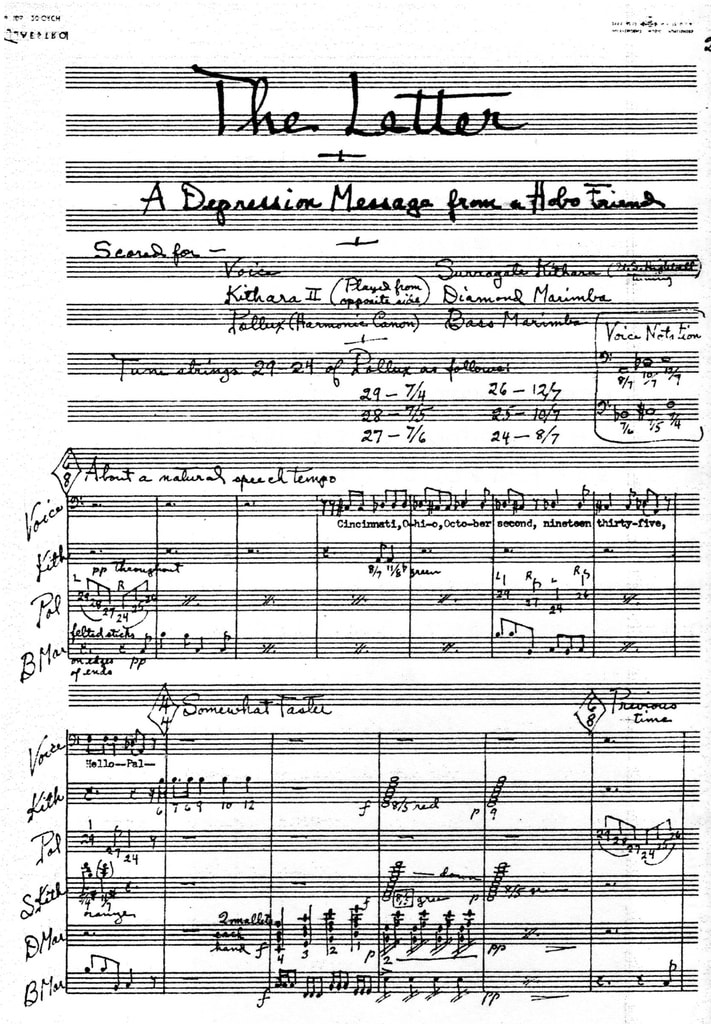また、NHKの大河ドラマ「元禄太平記」や「徳川慶喜」、それに、「おかあさんといっしょ」の音楽など、テレビや映画の音楽も数多く手がけました。*****
また、NHKの大河ドラマ「元禄太平記」や「徳川慶喜」、それに、「おかあさんといっしょ」の音楽など、テレビや映画の音楽も数多く手がけました。*****
訳 B
いかにも夏だ
はためいている
洗い立ての
白いジーンズ
遠くに見える
天の
香具山
コード
- コード進行*1 : [8小節] (全終)15634151進行: C|G|Am|Em|F|C|G7|C
- 調: Cメジャー/Aマイナー(♯・♭なし)
メロディーのスタイル
- メインモデル*2 : サザンオールスターズ 風
- Bpm: 100.0
- メロディー楽器: ピアノ
- 最高音: D5
- 最低音: A3
- 遊び度: 1.3
- 和音の当てはまり度: 1.5
伴奏のスタイル
- 伴奏パターン 1: ストローク 4分8分ミックス 3
- 伴奏楽器 1: アコースティックギター
- 伴奏パターン 2: ベース:単純4ビート
- 伴奏楽器 2: アコースティックベース
- ドラムパターン: 8ビート 型15(BSHSp)
片山杜秀「大楽必易:わたくしの伊福部昭伝」新潮社 (2024/1)
支那事変が起きた際に,哀愁に満ちた歌詞,郷愁をさそうメロディーなどから「厭戦的である」として人々が歌うことが禁じられ,陸軍も将兵がこの歌を歌う事を禁止した.しかし下士官・古参兵が「今回で戦友を歌うのをやめる.最後の別れに唱和を行う」とし,それを士官・上官が黙認する場合も多々あり,兵隊ソングとして認知されていた.*****
新聞の折込で知って,車で 10 分たらずの隣町の公民館の竪琴講習会に参加.生徒は3人だった.
名古屋に本部がある,ライリッシュ・竪琴連盟主催.トップ画像は同 連盟のHPから拝借した.
26 弦の竪琴 (ライアー lyre) で,ご指導のもと きらきら星などを合奏した.
写真のように,上枠に弦に対応してベグ (とは言わないのかもしれないが) が並んでいて,ピアノで言えば上が白鍵,下が黒鍵.右側が低音側.白鍵対応弦は写真で手前,黒鍵の弦はやや奥に張ってあり,原則として白鍵弦は表から右手の指で,黒鍵弦は裏から すなわち窓の向こうから左手の指で弾く.
ぼくの下ごごろ : オクターブを16分割する平均律とか,PAN音階とかを midi で作ったけれど,アコースティックな楽器でこうした変則音階を演奏したい.このライアーを使えばチューニングできるのではないか... 楽器としての「つくり」も頑丈だし.
フレームの白鍵・黒鍵的構成が変則音律にとっては迷惑ではある.
むしろヴルクマイスターだのキルンベルガーだのの,古典音律実践には最適だろう.
写真の楽器は税込 88,000 円.共鳴胴がないタイプは 66,000 円.
音律を別にすれば,楽器としての魅力はポータブルで,ピアノなみに多重音が出せること.ハーモニーやグリサンドの魅力はギターに勝るかも.音量が小さいのでセッションにはアンプが必要.早いパッセージは練習次第かな ?
動画はライアー版「月の光」.
バート・バカラックが亡くなった.94歳,自然死だったとのこと.
このブログに Raindrops ... のことを書いたばかりだった.
1960 年代後半,アメリカにいたことがあり,Do You Know the Way to San Jose,The Guy's in Love with You,I7ll Never Fall in Love Again などをハナ歌していた.
トップ画像は中本マリさんの 1992 年のアルバムで,バックはヴァイブとギターのグループ,デル・マーレ (浜田均(vib, marimba),井上博(acg, elg, computer programming),桜井郁雄(acb),大坂昌彦(ds),三島一洋(perc)).
この頃はマリさんのライブによく行った.
後年バカラック・ナンバーを自分で演奏するようになった.楽譜では 2/4 と 4/4 がしていても,そんなことは意識せず楽しく弾けるのだった.
動画のカーペンターズ・ナンバーもバカラック !
ここまで昨夜書いたのだけれど,今朝の朝日朝刊では4段抜きで死亡が報じられていた...そんなに偉いひとだったの ?
「大学4年間のデータサイエンスが10時間でざっと学べる」で,昔のことを思い出した.
名古屋大学プラズマ研究所に助手として就職したのが 1960 年代末で,物理実験のために相関計を作るというテーマを与えられた.アナログ回路を組み合わせて作る,というのが当時の常識だったが,物理信号をアナログ・デジタル変換して,デジタルデータを計算機にたくわえ,そこで相関計算をすることを提案し,認められた.
計算機は写真右上のミニ・コンピュータ HITAC10 で,メモリ 4kW=8kByte (2Byte/W=16bit/W だった) ,左下の 16 個のランプとスイッチで1word の 16 ビットのそれぞれに1か0かを指定し,状態を知る.入出力機器は写真左下のテレタイプだけ.横方向1列に孔があるかないかでビット値を知る (パリティチェックもあったと思うが,忘れてしまった).プログラムもデータも,読み書きはテレタイプ鍵盤の左側の穿孔紙テープで行う.
当時の月給は3万円くらいだったと思うが,ミニコンビュータはテレタイプ付きで 500 万円だった.
プログラムは機械語と1対1対応のアセンブラで書いた.「大学4年間の...」にも書いてあるが,今でも計算機が処理できるのは機械語だけだし,その計算機もノイマンアーキテクチュアであることは 1960 年代と変わらない.クロックが速くなり,記憶容量が増しただけ.
この分野にいたのは十数年.写真のように幼稚で可愛かったノイマン計算機は,この間高速大容量化とともに一大官僚機構と化し,ご機嫌をとらないと動かないようになった.職場 (日本原子力研究所に移っていた) が自分と合わないと感じたのを機会に,計算機からも足を洗った.